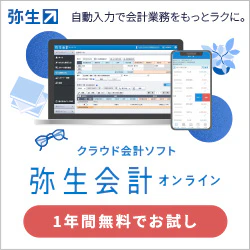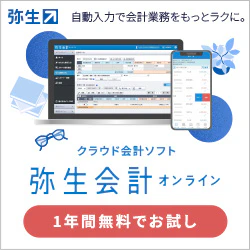「売上原価」は損益計算書に記載されるもので、利益に大きく関わる勘定科目です。しかし、計算の仕方や言葉の意味を理解するのが難しいという人も多いのではないでしょうか。この記事では、売上原価の意味や計算方法、製造原価との違いなどについてわかりやすく解説します。
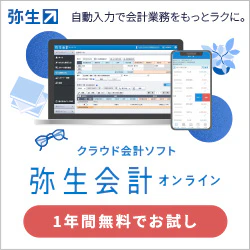
西日本シティ銀行は創業期の皆さまを支援!
さまざまな連携サービスをご用意しています
売上原価の意味・内訳・求め方

売上原価とは
「売上原価」とは、簡単にいうと、販売した商品をいくらで買ってきたかを表すものです。たとえば120円でカップラーメンを売るとき、100円で仕入れたのであれば、カップラーメンの売上原価は100円です。
つまり、売上原価とは売上を上げるために直接かかった費用のことです。実際に製品や商品が売れたときに、製造や仕入れにかかった費用として計上します。サービスの場合は、サービスを生み出すために直接かかった費用のことを指します。
売上になるまでは在庫資産として扱い、売上原価として計上しないので注意しましょう。サービス業では「外注費や人件費」、製造業では「製造費」、小売業では「商品の仕入れ代」が売上原価に該当します。
売上原価の内訳
売上原価の内訳として、以下の3つがあります。
●原価
●棚卸減耗費
●商品評価損
「原価」とは製品を作るのにかかった材料代などのことです。「棚卸減耗費」とは、倉庫で保管中に紛失してしまった商品の損失を表します。そして「商品評価損」とは、商品を仕入れたときに比べて商品の価値が下がったことによる損失のことを指します。
\原価計算について学ぶ/
売上原価の計算式
売上原価は、基本的には仕入れをした金額と同じになりますが、販売した商品の分しかカウントしません。ですから、仕入れた商品でも売れなかった在庫品は、仕入れ金額から省く必要があります。売上原価の計算式は、以下の通りです。
●売上原価=期首商品棚卸高+当期商品仕入高ー期末商品棚卸高
まず、原価を計算する期間の始めに抱えている在庫(期首商品棚卸高)に、仕入れた商品の金額(当期商品仕入高)を加えます。そして期末の在庫品の分(期末商品棚卸高)を引くことで、売れた商品分の売上原価を求めることができます。
売上原価は決算書の損益計算書に記載される
売上原価は損益計算書に記載されるものです。「売上高」のすぐ下に記載されるため、製造や仕入れにいくらかかり、商品を売っていくら儲けたのかを知るのに役立ちます。
>>決算書の読み方【入門編】初心者でも正しく理解できる決算書の見方
売上原価を記載する際のルール
売上原価の記載方法について、製造業を例に説明します。売上原価は小売業では「仕入れ分」を意味しますが、モノを作っている製造業では、自社の商品をいくらで作ることができたのかを表しています。製品を作るために必要な費用(コスト)には、人件費や材料費、経費などがあります。
これらのコストを集計し、1年間で生産された製品の原価を計算します。そして、販売された製品の原価のみを損益計算書に反映させます。これを「費用収益対応の原則」といいます。
企業会計原則によると、費用収益対応の原則は以下のように定められています。
●費用収益対応の原則:費用及び収益は、その発生源泉に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示しなければならない。
費用収益対応の原則が必要な理由
たとえば小売業の場合、商品の仕入れ代金は売上のために生じたものです。売上という収益が計上されたときに仕入代金を費用化することで、損益計算書で収益と費用が対応表示されます。
もし収益と費用が対応表示されていないと、ある期では費用が先に計上され、その後の期において収益(売上)が計上される場合があります。これでは会社の経営成績が適正に表示されているとはいえません。
会社の経営成績を正しく表示するために、費用収益対応の原則は必須とされています。
\決算書がわかるようになる/
売上原価は売上総利益を求める際に用いられる

損益計算書に出てくる利益には、以下の5つの利益があります。そのうち、売上高から売上原価を引いたものが「売上総利益」です。
●売上総利益
●営業利益
●経常利益
●税引前当期純利益
●当期純利益
売上総利益の計算式
●売上総利益=売上高ー売上原価
売上総利益は損益計算書の上の方に位置する利益であり、売上高から売上原価を差し引くことで求められます。売上原価が材料や商品などの仕入れ分を表す費用であるのに対し、売上高とは会社が稼いだ収益のことです。

西日本シティ銀行は創業期の皆さまを支援!
さまざまな連携サービスをご用意しています
売上原価と製造原価の違い

製造業では、売上原価の代わりに「製造原価」という用語が使われます。また、製造業では貸借対照表や損益計算書のほかに、1年間で生産された製品の原価の計算過程を示した「製造原価明細書(製造原価報告書)」を作成します。
それでは、売上原価と製造原価の違いはどのような点にあるのでしょうか。
売上原価は売れた商品に対して計上されるもの
売上原価とは、販売したサービスや商品の製造・仕入れ・提供に必要となった費用や原価のことです。たとえば自社で製品を製造するのにかかった費用や、販売した製品を仕入れた費用などが売上原価に該当します。
しかし、売上原価はあくまでも売れた商品に対して計上されるので、仕入れた商品のすべての原価が当てはまるわけではありません。つまり、売れなかった商品の製造や仕入れにかかった費用は売上原価には含まれないのです。
製造原価は製造にかかった費用のこと
製造原価は、サービスや商品を製造するために必要な原価や費用を表しますが、売上原価とは違って、製造原価は売上には関わっていません。通常は製造部門の原価を「製造原価」、販売部門の原価を「売上原価」として使用します。
また、会計上では製造原価は「製品」に分類されますが、売上原価は「商品」に分類されるという違いがあります。ただし、売上原価は売れた商品の製造にかかった費用であるため、広義の意味では製造原価が売上原価に含まれることもあります。
製造原価の内訳
製造原価には、主に「労務費」「材料費」「経費」の3つがあります。労務費は商品の製造に携わった従業員の賃金のことです。材料費は商品を作るときに必要な材料や、製造するために必要な消耗品などの費用を指します。そして経費は、労務費や材料費に含まれない費用のことです。
売上原価と販売管理費の違い

売上原価と「販売管理費」は、営業利益の計算に使われるものです。費用を仕分けられるように、それぞれの違いについてきちんと理解しておく必要があります。
売上原価は販売された製品や商品、サービスを生み出すためにかかる費用です。一方、販売管理費とは製品や商品、サービスの販売にかかる費用を表します。
>>販管費とは?営業利益の計算に関わる販売管理費の内訳、売上原価との違いまで解説
販売管理費は管理や販売に必要な費用
販売管理費とは「販売費及び一般管理費」のことで、売上を上げるのに間接的にかかった費用のことを指します。間接部門の経費や人件費、広告宣伝費、企業全体の管理費などが販売管理費に該当します。
たとえば製造業なら、製造に関わる従業員の人件費は売上原価で計上されますが、販売活動にかかる従業員の人件費は販売管理費で計上されます。同じ企業の従業員であっても、計上する費用項目が業務によって異なるので注意しましょう。
まとめ
売上原価は、売れた商品の製造や仕入れにかかった費用のことです。損益計算書に記載され、売上総利益を算出するのに用いられます。売上原価と似ている製造原価や販売管理費との違いを理解し、きちんと計算できるようにしておきましょう。
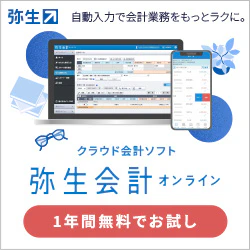
西日本シティ銀行は創業期の皆さまを支援!
さまざまな連携サービスをご用意しています
証券会社でマーケットアナリスト・デリバティブディーラーを経て個人投資家に転身。投資歴は20年以上。現在は、日経225先物を中心に、現物株、FX、CFDなど幅広い商品に投資している。
このライターの記事を読む >