プロが教えるキャッシュフロー計算書の作り方!基礎知識・作成方法を伝授
キャッシュフロー計算書とは、会社のお金の流れがわかる決算書です。これを見れば、会社に余裕があるのか、危険な状態にあるのかが一目でわかります。この記事では、キャッシュフロー計算書の仕組みと作成方法について解説します。
\決算書作成を手軽に/
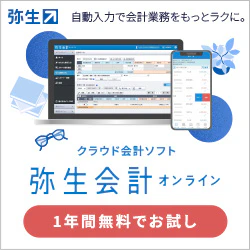
目次
キャッシュフロー計算書とは
キャッシュフロー計算書は、会社の1年間のお金の流れ、つまり、どのような理由でお金が入ってきて、どのような理由でお金が出ていったかを表した表です。企業は毎年決算書を作成しますが、決算書はキャッシュフロー計算書を含む「財務3表」で構成されています。
財務3表とは
財務3表とは、「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」のことです。ただ、キャッシュフロー計算書の作成を義務づけられているのは上場企業だけなので、「貸借対照表」と「損益計算書」の2つを決算書とすることも可能です。
貸借対照表でも前期と比較すれば、どのぐらい現金が増えたかがわかります。しかし、キャッシュフロー計算書を見れば詳しい現金の増減を一目で見分けることができます。
キャッシュフロー計算書の「キャッシュ」とは
キャッシュフロー計算書の「キャッシュ」とは、現金・預金と現金同等物のことです。
現金・預金
手元にある現金と、預金者の請求でただちに払い戻される預金(要求払預金)のことです。
現金同等物
現金同等物は、期間が3カ月以内であるかどうかが目安になります。簡単に換金でき、価格変動リスクのない短期投資のことで、3カ月満期のスーパー定期や、公社債投資信託などがあります。
キャッシュフロー計算書の項目
通常、キャッシュフロー計算書は以下のような構成になっています。
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動によるキャッシュフローでは、会社が本来の営業活動からどのくらいお金を得たかがわかります。
商品を売ったことでどのくらいお金が入ってきたか、商品を購入したことでいくらお金が出ていったか、家賃や給料の支払いでお金がいくら出ていったか、といった項目が記載されているのです。
営業活動によるキャッシュフローには、次の2つの表示方法があります。
間接法
税引前当期純利益に、キャッシュのズレを生じさせる項目を加減する方法で、多くの上場企業で採用されています。損益計算書とのつながりがわかりやすいというメリットがあります。
直接法
入金総額から出金総額を引いて、営業活動によるキャッシュフローを算出する方法です。会計的な知識がなくても作れますが、連結決算では手間がかかります。
お金を生み出す力を判断できる
営業活動によるキャッシュフローがプラスなら、本来の営業活動でお金を生み出す力があることを意味します。しかしマイナスの場合は本業でお金を生み出す力が弱く、資金ショートを起こす可能性があると判断できます。
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフローは、会社の将来の利益を獲得するために、どのくらいのお金を投資して回収したかを表しています。会社はお金に余裕があれば、それを利用して儲けることを考えます。
たとえば、誰かにお金を貸して利息を得たり、株を購入したりすることです。また、固定資産(土地や建物・機械など)に投資して、商売の拡大を図ったりもします。
設備投資などの積極性を判断できる
投資活動によるキャッシュフローがマイナスの場合、積極的に設備投資などをおこなっていると判断できます。一方でプラスの場合は、資産を売り払ってお金を得ていることを意味しているのです。
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフローでは、会社の営業活動や財務活動をおこなうために、どのくらいの資金を調達、または返済したかを表しています。
会社は資金が不足してくると、銀行から借入れをするなどして会社経営に充てます。銀行からお金を借り、いくら現金が増えたのか、返済していくら減ったのかが財務活動によるキャッシュフローに記載されるのです。
借入れ・返済具合を判断できる
財務活動によるキャッシュフローがプラスの場合、積極的に借入れをおこなっていることを意味します。一方マイナスの場合は、借入金などの返済が進み、財務体質が強くなっていることを表しているのです。
3つのキャッシュフローの合計金額からわかること
営業活動によるキャッシュフロー、投資活動によるキャッシュフロー、財務活動によるキャッシュフローの3つの合計金額が、プラスなら1年間でお金が増えたことを意味し、マイナスなら1年間でお金が減ったことを意味しています。
キャッシュフロー計算書の重要性
たとえ会社が利益を出していても、現預金が直接増えるわけではなく、借入金の返済が多ければ会社の現金は減ると考えられます。このような点からキャッシュフロー計算書の重要性がわかるでしょう。「利益は出ているけど、お金がない」、キャッシュフロー計算書はそんな悩みの原因を示してくれるのです。
\決算書作成を手軽に/
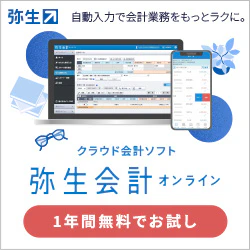
キャッシュフロー計算書の役割
キャッシュフロー計算書はもっとも信頼性の高い決算書
キャッシュフロー計算書は、ウソがつけない決算書です。現金の出入りというのは客観的なので、誰が見ても明らかです。ですから、キャッシュフロー計算書はもっとも信頼性の高い決算書といえます。
黒字倒産を見抜くことができる
会社にとって利益も大事ですが、会社を続けていくためにはキャッシュが不可欠です。利益が出ていても、売上代金を回収できなかったり、借金の返済が多かったりといった理由でお金が足りなくなってしまえば、倒産に追い込まれる可能性もあるからです。これを「黒字倒産」といいます。
貸借対照表や損益計算書だけで黒字倒産を見抜くのは難しいですが、現金の出入りを表すキャッシュフロー計算書なら見抜ける可能性があります。
キャッシュフロー計算書の簡単な作成方法
【ステップ1】2期比較(前期・当期)の貸借対照表を作成
キャッシュフロー計算書の作成は、2期比較(前期・当期)の貸借対照表を作るところから始めます。借方項目(資産)は「当期-前期」、貸方項目(負債・純資産)は「前期-当期」で計算し、マイナス項目は「▲」で表示します。
具体例を見ていきましょう。以下は、当期と前期を比較した貸借対照表(比較貸借対照表)の仕分けです。エクセルなどで作成すると便利です。
借方項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
現金・預金 | 400 | 200 | 200 |
売掛金 | 800 | 400 | 400 |
たな卸資産 | 400 | 800 | ▲400 |
固定資産 | 2000 | 1200 | 800 |
借方合計 | 3600 | 2600 | 1000 |
借方項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
買掛金 | 400 | 200 | ▲200 |
借入金 | 600 | 0 | ▲600 |
資本金 | 2000 | 2000 | 0 |
利益剰余金 | 600 | 400 | ▲200 |
貸方合計 | 3600 | 2600 | ▲1000 |
増減合計 | 0 |
【ステップ2】増減を「営業」「投資」「財務」の3つに分類する
この例では、「現金・預金(キャッシュ)」が200増加しています。キャッシュフロー計算書では、この増加がどの要因で起こっているのかを明らかにするため、キャッシュ以外の増減を「営業」「投資」「財務」の3つに分類します。
キャッシュフロー計算書の区分に従って増減を並べ替える
貸借対照表の増減を、キャッシュフロー計算書の区分に従って以下のように並べ替えましょう。
- 資金(現金預金)の増減は一番下
- 固定資産は「投資活動」
- 借入金、資本金等は「財務活動」
- それ以外は「営業活動」
資金の増減以外の項目は、符号を逆にする
そして資金の増減以外の項目は、符号を逆にします。キャッシュフローの増減(営業活動キャッシュフロー+投資活動キャッシュフロー+財務活動キャッシュフロー)は、現金預金の200に一致します。
貸借対照表 | 増減 | キャッシュフロー計算書 | 増減 |
|---|---|---|---|
現金預金 | 200 | 利益剰余金 | 200 |
売掛金 | 400 | 売掛金の増減 | ▲400 |
たな卸資産 | ▲400 | たな卸資産の増減 | 400 |
固定資産 | 800 | 買掛金の増減 | 200 |
買掛金 | ▲200 | 営業活動CFの合計 | 400 |
借入金 | ▲600 | 固定資産の増減 | ▲800 |
資本金 | 0 | 投資活動CF | ▲800 |
利益剰余金 | ▲200 | 借入金の増減 | 600 |
財務活動CF | 600 | ||
資金の増減 | 200 |
(CF=キャッシュフロー)
支出のない費用を調整することが必要
減価償却費と固定資産除却損
固定資産とは
さきほどの「固定資産」では、減価償却費が計上される場合もあります。固定資産とは、会社で長期間使う目的で購入した資産であり、自社で販売する商品のように転売を目的として購入された資産ではありません。
自社で使うことを目的として購入されたことに加え、1年を超えて使う場合が固定資産になります。固定資産は「有形固定資産」「無形固定資産」「投資その他の資産」の3つに分類できます。
有形固定資産と減価償却
有形固定資産とは、会社で長期の使用目的で購入した資産のことで、建物や備品、土地、車両などです。
貸借対照表に記載されている有形固定資産の金額は、購入したときの金額がそのまま載っているわけではありません。有形固定資産の中には、車両や建物など使用することによって価値がどんどん減少していくものがあるからです。
毎年の価値の減少分が、損益計算書に計上される「減価償却」になります。有形固定資産の購入価額から減価償却の累計額を控除した結果が、貸借対照表に有形固定資産の現在価値として計上されているのです。
減価償却費
減価償却費は、費用として利益を減らしますが、資金が出ていくわけではありません。このような損益科目を「非資金損益項目」といいます。
減価償却は支出のない費用なので、営業活動によるキャッシュフローに加え、同額を「有形固定資産の増減(投資活動によるキャッシュフロー)」からマイナスするのです。
固定資産除却損
また、固定資産除却損も支出のない費用なので、減価償却費と同じ処理をします。固定資産除却損とは、有形固定資産の利用をやめたとき、その資産を帳簿から除却するための勘定科目です。
固定資産売却損とその他の損失を合わせ、「事業撤退損」などで表示されている場合は、固定資産除却損だけを抜き出す必要があります。
支出のない費用を調整する
具体的には、以下のように処理します。
【ステップ1】貸借対照表科目の増減を分析
貸借対照表の減価償却費と、固定資産除却損が以下の値になったとします。
減価償却費 | ▲100 |
固定資産除却損 | ▲30 |
【ステップ2】貸借対照表の増減をキャッシュフロー(CF)に換算
貸借対照表科目の増減をキャッシュフローに換算します。減価償却費と固定資産除却損は資産のマイナスですが、キャッシュフローに換算するときは-1倍します。
増減額 | CF換算 | |
|---|---|---|
減価償却費 | ▲100 | 100 |
固定資産除却損 | ▲30 | 30 |
【ステップ3】キャッシュフロー科目に整理する
減価償却費と固定資産除却損を営業活動によるCFに加えます。同額(減価償却費+固定資産除却損)を、投資活動によるCFから「有形固定資産の増減」としてマイナスします。
営業活動によるCF | |
|---|---|
減価償却費 | 100 |
固定資産除却損 | 30 |
投資活動によるCF | |
有形固定資産の増減 | ▲130 |
営業活動でない売却損益を調整する
固定資産売却益は、営業活動の結果ではないのでマイナス入力し、同額を有形固定資産の増減にプラスします。同じように、有価証券売却益も営業活動の結果ではないのでマイナス入力し、同額を投資有価証券の増額にプラスします。売却損の場合は、それぞれ符号が逆になります。
たとえば、以下のように固定資産売却損益と有価証券売却益を処理します。
営業活動によるCF | ||
|---|---|---|
固定資産売却益 | ▲80 | |
固定資産売却損 | 60 | |
有価証券売却益 | ▲50 | |
投資活動によるCF | ||
有形固定資産の増減 | 80 | ▲60 |
投資有価証券の増減 | 50 | |
\決算書作成を手軽に/
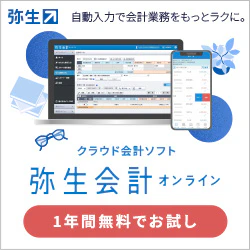
キャッシュフローの区分から会社のタイプがわかる
キャッシュフロー計算書は3つに分類できますが、その会社の良し悪しは単独で各区分を見るのではなく、トータルで判断することが大切です。
本業がうまくいっていても、資金運用で失敗して傾きかけている会社や、反対に本業がうまくいってなくても資産を売って会社を維持しているなど、1つの区分を見るだけでは正確な判断ができないからです。
3つの区分の数字がプラスなのかマイナスなのかで、主に次の3つのタイプ別に分析することが可能です。
利益・設備投資・返済が順調
- 営業キャッシュフロー:プラス
- 投資キャッシュフロー:マイナス
- 財務キャッシュフロー:マイナス
営業キャッシュフローがプラスになっているということは、本来の商売できちんとお金を稼いでいるということです。そして、投資キャッシュフローがマイナスということは、本業で得た資金を将来のための設備投資に回せている証拠です。
また財務キャッシュフローのマイナスは、余ったお金で借金を返済していることを表し、会社にとって望ましいタイプといえます。ただし、単年度だけではなく数年間この状況が続くことが大切です。
利益を出しつつ、借入れして設備投資をしている
- 営業キャッシュフロー:プラス
- 投資キャッシュフロー:マイナス
- 財務キャッシュフロー:プラス
営業キャッシュフローがプラスなので、本業でしっかり稼ぎ、設備投資に資金を回すこともできています。ただし、営業活動から得たキャッシュだけでは足りないので、借入れして設備投資を行っていると考えられます。
しかし、資金調達の理由が設備投資であれば、将来を見据えた積極的な借入れといえるので、会社の状況としては問題ないといえるでしょう。
利益・資産・返済のすべてが良くない状態
- 営業キャッシュフロー:マイナス
- 投資キャッシュフロー:ゼロ
- 財務キャッシュフロー:マイナス
営業活動で出ていくお金が多く、銀行への借入金の返済も迫られていると考えられます。そして投資キャッシュフローがゼロなので、切り売りする資産もなくなっていると判断できます。この場合、手元の現金がなくなった時点で、倒産になってしまう可能性が高いといえます。
\決算書作成を手軽に/
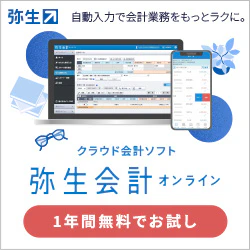
まとめ
キャッシュフロー計算書は3つに分類でき、それぞれの区分から会社の状態を見極めることができます。キャッシュフロー計算書を作るには、当期と前期を比べた比較貸借対照表が必要です。まずは基礎的な部分を押さえ、細かいルールやテクニックはその都度覚えていくことをおすすめします!
- キャッシュフロー
Writer

証券外務員1種
証券会社でマーケットアナリスト・デリバティブディーラーを経て個人投資家に転身。投資歴は20年以上。現在は、日経225先物を中心に、現物株、FX、CFDなど幅広い商品に投資している。
このライターの記事を読む >おすすめの記事

対談記事【ビジネスのヒント】|接骨院から建設業へ。驚きの経歴と経緯
経営に関する悩みや課題を抱える事業経営者の皆さまにとって、銀行の営業担当者は心強いサポーターの一人です。そこで、リニュー編集部では、事業経営者と西日本シティ銀行の営業担当者にスポットをあててインタビュー。サポートのきっかけや、事業の成功までの道のりなどをざっくばらんにお話しいただきます。

【今月のZero-Ten Park】株式会社ストリ|心と体に美しさと健やかさを
福岡を中心に世界5カ国15拠点を展開するシェアオフィス&コワーキングスペース「Zero-Ten Park」。そこに入居している、今注目したい企業をピックアップ。今回は「株式会社ストリ」をご紹介します。

働き方改革に注力している企業ってどんなところ?|次世代ワークスタイル応援私募債「ミライへの路」
これから就職先を探している学生のみなさんにとって、どんな企業が自分にとって働きやすいのか、気になりますよね。そこで今回は、西日本シティ銀行が取り扱う次世代ワークスタイル応援私募債『ミライへの路*』を発行している企業のみなさんにご協力をいただき、その企業で実際に働いている若手の社員に直撃インタビュー。なぜ入社を決めたのか、実際に働いてみてどんな感じなのか、などをヒアリングしました。また、併せて、各企業の経営者にも、求める人材像や今後の展望などをお話しいただきました。取材に協力いただいた企業は、地元・福岡で働き方改革に注力している、優良企業ばかりです。ぜひ、就職希望先の候補の一つとして、働く先輩たちのリアルな声をご一読ください。

【ミライへの路に挑む企業】地球を守り働く人の成長を支える環境調査会社|株式会社ENJEC
多様な生き方や働き方が広がりつつある現代。企業にはこれからますます、さまざまな人が働きやすい環境を整えることが求められます。社員の働きやすさを叶える企業の取り組みとは?この連載では、実際に働き方改革を積極的に取り組む企業で働く人や経営者にインタビュー。今回は、九州を中心に、水質、大気、土壌といった環境にまつわる調査・分析の事業を手がける、福岡市の株式会社ENJEC(エンジェック)に取材しました。

質の高い人材紹介サービスで、企業も求職者も従業員も幸せに |株式会社GR8キャリア 小畑和貴さん
医療・福祉業界の人材紹介サービスをメインに事業展開する株式会社GR8(グレイト)キャリア。代表の小畑和貴さんは宮城県出身で福岡に移住し、住宅メーカーから人材紹介業界に転職したという異色のキャリアの持ち主です。創業から1年足らずでメンバーは20人ほどに増え、順調な滑り出しといえます。しかし、組織や利益の拡大は求めず、あくまでも「質の高いサービス提供」と「社員とその家族が笑顔で過ごせること」にこだわり続けたいという小畑さんに、その思いの根源や起業のストーリーを聞きました。

番組・動画制作から拠点の運営まで、幅広い事業を展開|株式会社move on.e 岩谷直生さん
20歳から放送局の番組制作に関わり、個人事業主を経て、41歳で番組と動画制作を主軸にした株式会社move on.eを設立した岩谷直生さん。長年のディレクター経験を生かして、マスメディアの番組やイベントを手掛ける一方で、子どもに向けた全く新しい事業にも意欲的にチャレンジしています。

【事業継続力強化計画認定制度】概要や認定のメリット、申請支援事業も紹介
近年、地震や台風などの自然災害、感染症の流行など、企業経営を取り巻くリスクが多様化しています。 こうした中で注目されているのが、災害や緊急事態に備えて事業を継続できる体制を整える「事業継続力強化計画(BCP)」です。 この計画の認定を受けることで、補助金申請時の加点や税制優遇など、さまざまなメリットがあります。 そこでこの記事では、事業継続力強化計画認定制度の概要や認定メリットに加えて、計画策定・申請を支援する取り組みについても解説します。

【中小企業必見】最低賃金引上げに伴う負担軽減策とは?福岡県の支援策も紹介
令和7年度の最低賃金引上げにより、全国的に人件費の負担が増加しています。特に中小企業や小規模事業者にとっては、賃上げへの対応が経営上の大きな課題となっています。 こうした状況を受け、国や自治体では、最低賃金の引上げに伴う事業者の負担を軽減するため、各種支援策を打ち出しています。 この記事では、最低賃金引上げに対応するための国の主な支援策に加え、福岡県独自の支援制度について解説します。


