貸借対照表(バランスシート)の見方・読み方のポイントを基礎から解説
貸借対照表は、会社にどれだけの資産があって、どれくらいの借金があるかという財務内容がわかる決算報告書です。会社の状態を理解するためには、貸借対照表をきちんと読めるようになることが大切といえます。この記事では、貸借対照表の見方とポイントについて解説します。
\決算書作成を手軽に/
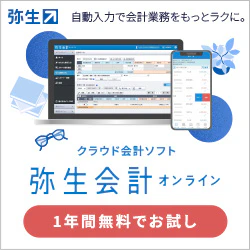
貸借対照表 [たいしゃくたいしょうひょう](バランスシート)とは
そもそも貸借(たいしゃく)とは?賃借との違いは?
漢字が表現するとおり、「貸借(たいしゃく)」は貸し借りを意味します。
似た漢字に「賃借(ちんしゃく)」があり、「賃借対照表」と表現してしまう人もいますが、これは誤用ですので注意しましょう。なお、「賃借(ちんしゃく)」は「相手方に賃料を支払い、物を借りること」を意味します。
貸借対照表(バランスシート)は決算書の一種
貸借対照表は、損益計算書やキャッシュ・フロー計算書と並ぶ重要な決算書で、バランスシート(B/S)とも呼ばれています。企業のある時点における財政の状態を「資産」「負債」「純資産」から見ることができるものです。
つまり、決算時(一定時点)、会社はどんな財産(資産)を持っていて、その財産の元になるお金(負債・純資産)はどうやって集めてきたかがわかるようになっています。決算の時期になると経理部門はとても忙しくなるほど、会社にとって法人決算はとても大切な業務といえます。
決算日にどれくらいの資産・借金があるかを表す
貸借対照表(バランスシート)には、決算日における資産や負債の内容が表示されています。つまり、決算日にどれくらいのお金があって、どれくらいの借金があるのかという財務状態を明らかにした表なのです。
たとえ経営がうまくいっているように見える会社でも、貸借対照表(バランスシート)の純資産がマイナスなら、他人から借りたお金で会社を継続している可能性があります。
貸借対照表(バランスシート)の構成
貸借対照表の大まかな構成としては、左側に資産が、右側に負債と純資産が記入されます。資産の部は、集めたお金をどのように運用・保有しているかを表しています。そして、負債と純資産の部は、事業に必要なお金を会社がどのように集めたかを示しています。
貸借対照表では、必ず左右の金額が一致するというのがポイントです。
(資産=負債+純資産)
貸借対照表(バランスシート)の簡単な読み方
貸借対照表(バランスシート)の要旨
貸借対照表は、資産の部・負債の部・純資産の部に区分しなければいけないもので、株式会社は当てはまる事項をすべて記載する必要があります。それでは、資産・負債・純資産について詳しく解説します。
資産とは
資産とは、現金や売ればお金になるもので、貸借対照表の左側に表示されます。たとえば、現金や商品・土地・建物などです。そして、1年以内に現金化できる「流動資産」と、長期にわたり会社が保有する「固定資産」に分類できます。
貸借対照表では現金化しやすいものから並べるのが通常で、上から流動資産、固定資産と並べます。
(資産=流動資産+固定資産)
流動資産
流動資産とは、現金や短期的(2~3か月以内)に現金化される資産のことで、下記の3つに分類できます。
- 当座資産
- 棚卸資産
- その他の資産
当座資産
当座資産とは、現金と、短い期間で現金になる資産で、「現金」「受取手形」「売掛金」「有価証券」があります。
棚卸資産
棚卸資産は、製品や商品のことです。製造業であれば、仕掛品(つくりかけの製品)や原材料が在庫として存在しますが、これらも棚卸資産に含まれます。
ただし、棚卸資産は現金のように多ければいいというわけではありません。たくさんの商品を持っていると、売れ残りの危険性も高まるからです。売れ残って廃棄処分になれば、利益面でのダメージは大きくなります。ですから、棚卸資産は適正な水準を維持することが大切といえます。
その他の資産
その他の資産には、「短期貸付金」「前払費用」「前払金」「未収金」などがあります。代表的なのが「短期貸付金」です。1年以内に返済してもらうことになっている仕入れ先や取引先などへの貸付金で、返済日までは現金にできません。
固定資産
固定資産は自分の会社で使うことを目的に購入し、1年を超えて使う資産で、「有形固定資産」「無形固定資産」「投資その他の資産」の3つに分類できます。
有形固定資産
有形固定資産とは、形があって長期間使用するもので、土地や建物、車両や備品などです。ただし、貸借対照表に掲載されている有形固定資産は、有形固定資産の購入価額から、減価償却累計額を引いた金額が計上されているものもあります。
減価償却とは、固定資産を使用するにつれ、財として減価するものを費用計上し、新しいものと替えるときに備える会計手続きのことです。
無形固定資産
無形固定資産は形のない資産で、特許権や商標権などの権利、給与計算ソフトや会計ソフトなどのソフトウェアなどです。
また、見えない企業の収益力として「のれん代」があります。のれん代とは、企業の買収価額と純資産の差額で、収益を稼ぎ出す力を表しています。
投資その他の資産
投資その他の資産は、長期投資に関係したものと、有形固定資産や無形固定資産に記載されない長期の資産で、投資有価証券や関連会社株式、子会社株式などがあります。
負債とは
負債とは借金のことです。返さなければいけないお金で、「他人資本」とも呼ばれています。支払手形や買掛金も、約束の日にお金を支払わなければいけないため、負債といえます。
負債は、1年以内に返さなければいけない「流動負債」と、1年を超えて返済する「固定負債」に分類できます。
(負債=流動負債+固定負債)
流動負債
流動負債とは、1年以内に支払い期限がやってくる負債のことで、支払手形や買掛金など商品代金の未払いが代表的です。貸借対照表では、支払い義務の強いものが上から順番に並べられ、支払手形が一番上になります。
固定負債
固定負債とは、1年を超えて返済する負債で、長期借入金と社債などがあります。固定負債は時間をかけて返済できるので、新規店舗の出店や高額な設備投資などに使われます。
長期借入金は、銀行などからの借入のうち、返済期限が1年超のものをいいます。社債とは、企業が資金調達の手段として、投資家からお金を借りることです。通常、社債の返済期限は1年を越えるので、固定負債に分類されます。
退職給付引当金は固定負債に計上する
退職金の制度がある企業では、「退職給付引当金」を計上する必要があります。退職金は、従業員が働いてくれたことに対して支払われます。20~30年と長期にわたって積立てたものを退職時に支払うので、支払いが1年超の固定負債に計上されるのです。
純資産とは
純資産は資産総額から負債総額を差し引いた差額で、「株主資本」がメインです。株主資本とは、株主が会社に出したお金(資本金・資本剰余金)と、会社が過去に稼いだ利益のうち、会社に残っている分です。
株主資本の分類
株主資本は、主に「資本金」「資本剰余金」「利益剰余金」に分類できます。資本金と資本剰余金は株主が会社に出したお金で、利益剰余金は会社の利益の蓄えです。
純資産の方が負債より多いときは、健全な財政状態だといえます。一方、負債が純資産を大幅に上回っているときは、会社の財務状況は厳しいと判断できます。
\決算書作成を手軽に/
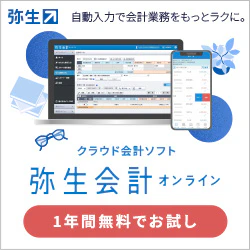
貸借対照表(バランスシート)でチェックするポイント
自己資本比率がどのくらいあるか
会社の資産のうち、返さなくていい純資産(自己資本)がどのくらいあるかを表した比率が「自己資本比率」です。
[自己資本比率(%)=自己資本(純資産)÷総資産(資産の合計)×100]
経営状態の安定性
自己資本は返済の必要がないお金なので、総資産の中に占める自己資本の割合が大きければ大きいほど、返済の必要がない資金で会社が運営されていると考えられます。
つまり、自己資本比率が高いほど経営は安定しており、倒産しにくい会社といえます。一方、自己資本比率が低いほど他人資本(負債)の影響を受けやすく、経営が不安定だと判断できます。
また、1年以内に現金化できる流動資産も大切で、特に現預金は多ければ多いほど経営が安定していると考えられます。
流動比率
流動比率は、短期的に支払いが生じる流動負債に対して、すぐに現金化できる流動資産の比率がどの程度かを計算したものです。
[流動比率(%)=流動資産÷流動負債×100]
余力のある会社かどうか
流動資産が流動負債より大きいほど、余力のある会社だと判断できます。流動資産と流動負債は貸借対照表の上部に記載されており、計算も簡単で理解しやすい指標といえます。
一般的には130~150%を維持しておきたいところですが、120%程度あればよい業界もあります。ただ、100%を切っている場合は注意が必要といえます。
当座比率
当座資産はもっとも現金に近い存在で、当面の支払い能力を表しています。当座資産を流動負債で割ったのが「当座比率」です。
[当座比率(%)=当座資産÷流動負債×100]
短期の債務返済能力
当座比率が100%以上あれば、短期の債務返済能力は十分あると判断できます。反対に当座比率が100%未満だと、短期の債務返済能力があるとはいえないので注意が必要です。
固定比率
固定比率は、自己資本に対する固定資産の割合です。長期的な会社の安全性を分析する指標で、資金の調達と運用がバランスよく行われているかを判断できます。
[固定比率(%)=固定資産÷自己資本×100]
長期的な会社の安全性
固定比率が低ければ、企業の長期的な安全性は高いといえます。100%以下ということは、借入などの他人資本に頼っていないということになり、自己資本をもとにして資金調達をしていると判断できるからです。
固定長期適合率
固定資産を、どの程度の自己資本と固定負債でまかなえているかを見る指標が「固定長期適合率」です。
固定負債は1年以内に返済期日がこないものなので、自己資本に近い安定した資金といえます。そのため、固定資産を調達する原資として考えられます。
[固定長期適合率(%)=(自己資本+固定負債)÷固定資産×100]
固定資産を自己資本と固定負債でまかなえているか
固定長期適合率が100%を超えていれば、自己資本と固定負債という安定した資金で固定資産をまかなえているといえます。反対に100%を下回るようだと、長期の支払い能力が危ない可能性があると判断できます。
有利子負債が多い企業かどうか
有利子負債が多い企業は利益が生じにくい
有利子負債とは、利息の支払いが必要な負債のことで、銀行からの借入金が代表です。有利子負債が多ければそれだけ支払い利息も増えるので、損益計算書の営業外費用の金額が大きくなります。
営業外費用が多くなれば利益も減ってしまうので、有利子負債の多い会社は利益を生じにくいと判断できます。
\決算書作成を手軽に/
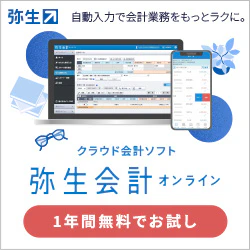
貸借対照表(バランスシート)のまとめ
貸借対照表(バランスシート)は、どれくらいの資産と借金があるのかといった、会社の財務内容がわかる決算報告書で、資産・負債・純資産の3つに分けられます。貸借対照表を読めるようになると、会社の状態を把握することが可能です。今回の記事で説明したポイントを押さえ、仕事などに役立ててください。
- 貸借対照表
Writer

証券外務員1種
証券会社でマーケットアナリスト・デリバティブディーラーを経て個人投資家に転身。投資歴は20年以上。現在は、日経225先物を中心に、現物株、FX、CFDなど幅広い商品に投資している。
このライターの記事を読む >おすすめの記事

対談記事【ビジネスのヒント】|接骨院から建設業へ。驚きの経歴と経緯
経営に関する悩みや課題を抱える事業経営者の皆さまにとって、銀行の営業担当者は心強いサポーターの一人です。そこで、リニュー編集部では、事業経営者と西日本シティ銀行の営業担当者にスポットをあててインタビュー。サポートのきっかけや、事業の成功までの道のりなどをざっくばらんにお話しいただきます。

【今月のZero-Ten Park】株式会社ストリ|心と体に美しさと健やかさを
福岡を中心に世界5カ国15拠点を展開するシェアオフィス&コワーキングスペース「Zero-Ten Park」。そこに入居している、今注目したい企業をピックアップ。今回は「株式会社ストリ」をご紹介します。

働き方改革に注力している企業ってどんなところ?|次世代ワークスタイル応援私募債「ミライへの路」
これから就職先を探している学生のみなさんにとって、どんな企業が自分にとって働きやすいのか、気になりますよね。そこで今回は、西日本シティ銀行が取り扱う次世代ワークスタイル応援私募債『ミライへの路*』を発行している企業のみなさんにご協力をいただき、その企業で実際に働いている若手の社員に直撃インタビュー。なぜ入社を決めたのか、実際に働いてみてどんな感じなのか、などをヒアリングしました。また、併せて、各企業の経営者にも、求める人材像や今後の展望などをお話しいただきました。取材に協力いただいた企業は、地元・福岡で働き方改革に注力している、優良企業ばかりです。ぜひ、就職希望先の候補の一つとして、働く先輩たちのリアルな声をご一読ください。

【ミライへの路に挑む企業】地球を守り働く人の成長を支える環境調査会社|株式会社ENJEC
多様な生き方や働き方が広がりつつある現代。企業にはこれからますます、さまざまな人が働きやすい環境を整えることが求められます。社員の働きやすさを叶える企業の取り組みとは?この連載では、実際に働き方改革を積極的に取り組む企業で働く人や経営者にインタビュー。今回は、九州を中心に、水質、大気、土壌といった環境にまつわる調査・分析の事業を手がける、福岡市の株式会社ENJEC(エンジェック)に取材しました。

質の高い人材紹介サービスで、企業も求職者も従業員も幸せに |株式会社GR8キャリア 小畑和貴さん
医療・福祉業界の人材紹介サービスをメインに事業展開する株式会社GR8(グレイト)キャリア。代表の小畑和貴さんは宮城県出身で福岡に移住し、住宅メーカーから人材紹介業界に転職したという異色のキャリアの持ち主です。創業から1年足らずでメンバーは20人ほどに増え、順調な滑り出しといえます。しかし、組織や利益の拡大は求めず、あくまでも「質の高いサービス提供」と「社員とその家族が笑顔で過ごせること」にこだわり続けたいという小畑さんに、その思いの根源や起業のストーリーを聞きました。

番組・動画制作から拠点の運営まで、幅広い事業を展開|株式会社move on.e 岩谷直生さん
20歳から放送局の番組制作に関わり、個人事業主を経て、41歳で番組と動画制作を主軸にした株式会社move on.eを設立した岩谷直生さん。長年のディレクター経験を生かして、マスメディアの番組やイベントを手掛ける一方で、子どもに向けた全く新しい事業にも意欲的にチャレンジしています。

【事業継続力強化計画認定制度】概要や認定のメリット、申請支援事業も紹介
近年、地震や台風などの自然災害、感染症の流行など、企業経営を取り巻くリスクが多様化しています。 こうした中で注目されているのが、災害や緊急事態に備えて事業を継続できる体制を整える「事業継続力強化計画(BCP)」です。 この計画の認定を受けることで、補助金申請時の加点や税制優遇など、さまざまなメリットがあります。 そこでこの記事では、事業継続力強化計画認定制度の概要や認定メリットに加えて、計画策定・申請を支援する取り組みについても解説します。

【中小企業必見】最低賃金引上げに伴う負担軽減策とは?福岡県の支援策も紹介
令和7年度の最低賃金引上げにより、全国的に人件費の負担が増加しています。特に中小企業や小規模事業者にとっては、賃上げへの対応が経営上の大きな課題となっています。 こうした状況を受け、国や自治体では、最低賃金の引上げに伴う事業者の負担を軽減するため、各種支援策を打ち出しています。 この記事では、最低賃金引上げに対応するための国の主な支援策に加え、福岡県独自の支援制度について解説します。


