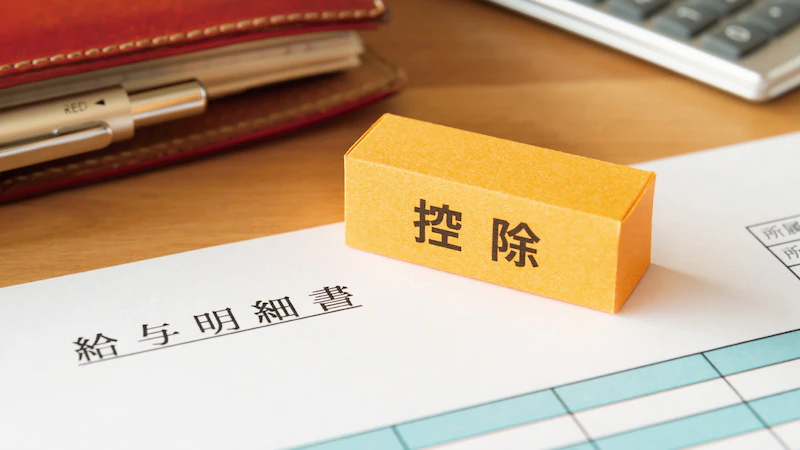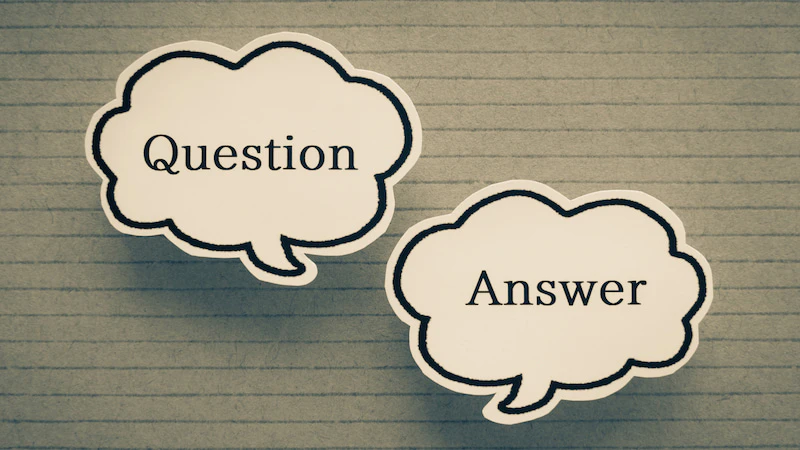給与明細にはさまざまな項目や金額が載っており、最初はどこを見れば良いか分からず混乱するでしょう。そこで本記事では、給与明細の記載内容やそれぞれの項目の意味などを解説します。新社会人になった人はもちろん、「実はよく給与明細の見方が分からない」という人もぜひ参考にしてください。
毎月もらう給与明細!まずは基本のポイントを押さえよう
給与明細の形式にはいろいろありますが、記載内容はどの会社もほとんど同じです。まずは、給与明細に関する基本のポイントから見ていきましょう。
給与明細の構成は「支給・控除・勤怠」
給与明細は、大きく3つの構成要素から記載されています。
- 支給:会社から受け取る収入(基本給や手当)
- 控除:給与から天引きされる支出(税金や保険料)
- 勤怠:勤務時間数や休日数などの状況
労働基準法において、給与明細の発行は義務ではありません。しかし所得税法や健康保険法では、給与支払明細書の交付義務や控除額の通知義務があります。給与明細を見れば毎月いくら給与をもらっているのか、いくら税金を払っているのかが分かります。
賃金から税金や保険料などの金額が天引きされる
毎月の賃金は、丸ごと手元に入るわけではありません。賃金からは所得税や健康保険料などが天引き(給与から差し引かれること)され、残りが手取り額となります。なお税金や保険料に限らず、会社が対応していればiDeCoや財形貯蓄などの掛け金を天引きすることも可能です。
残業時間の増減や特別手当の臨時支給があるなど、月によって手取り額が変わることは珍しくありません。口座に振り込まれた額だけ見ても給与の内訳が分からないため、それを示すのが給与明細の役割です。
給与明細の構成要素①「支給」
ここでは、会社から受け取る収入である「支給」の項目を細かく見ていきましょう。

基本給
給与のメインとなる金額です。他の手当やインセンティブ(成果給・歩合給など)の金額は、基本給に含まれません。ボーナスは、基本給を基準にします。ボーナス支給額が2.5ヶ月分であれば、「基本給×2.5ヶ月分」という意味になります。
残業手当(休日出勤・深夜残業)
残業時間に対して発生する手当です。一般的に残業手当・休日出勤手当・深夜残業手当の総称が残業代と呼ばれています。残業代が細かい項目に分かれているのは、それぞれの割増賃金率が変わるためです。
残業代の割増賃金率
残業代の割増率は、以下のとおりです。
- 時間外手当:25%割増
- 休日出勤手当:35%割増
- 深夜残業手当(22時〜5時の間に行う残業):時間外手当に加え25%割増
なお労働基準法では、法定労働時間である1日8時間または週40時間を超えて働いた時間に対し割増賃金が支払われます。もし所定労働時間が1日7時間の職場の場合、1時間分の残業代については割増されないことがあるのです。その場合は1時間当たりの通常賃金のみが支払われます。会社によって規定が異なるため、気になる人は確認してみましょう。
通勤手当
会社までの通勤に掛かった交通費などの項目です。通勤手当の額は、会社によって取り決めが異なります。公共交通機関の料金に準ずる場合や、勤務先と自宅の距離単価で決める場合などさまざまです。
その他各種手当
その他、各種手当の金額が記載されています。手当の種類は会社によって異なりますが、代表的なものには以下のような手当があります。
役職手当 | 主任、課長などの役職や責任に応じて支給される手当 |
住宅手当 | 家賃や住宅ローンを補助する目的として支給される手当 |
資格手当 | 業務に関する試験費用や資格取得代として支給される手当 |
出張手当 | 出張にかかった交通費や宿泊代として支給される手当 |
給与明細の構成要素②「控除」
給与明細の控除項目は、大きく分けると「法定控除」と「法定外控除」があります。法定控除は法律により給与からの控除が定められており、法定外控除は労使協定により給与から控除できる金額です。法定外控除は会社や従業員によって異なるため、ここでは法定控除のみ解説します。
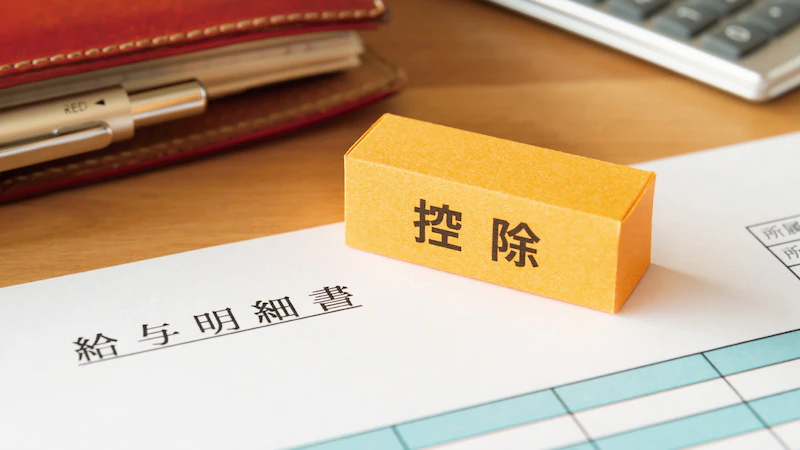
健康保険料
健康保険に加入するために必要な料金です。健康保険の加入者には健康保険証が発行され、病院の診察代などの医療費が3割負担になります。これまでは学生で親の扶養に入っていた人も、社会人として働き始めたら自分で健康保険料を支払うことになるのです。
なお、40歳になると健康保険料に加え、介護保険料も控除されるようになります。
厚生年金保険料
老後や障害を負ったときに、加入者とその家族の生活を安定させるための年金制度です。会社員の場合は国民年金と厚生年金に加入し、両方の保険料が厚生年金保険料として給与から天引きされます。
厚生年金保険料は会社と従業員の折半になり、給与明細に記載されているのは自分が負担している額です。
雇用保険料
失業時の生活を安定させるための保険です。万が一会社を辞めても、給付条件を満たせば失業手当を受け取れます。また、離職後に他の会社へ転職した場合は、再就職手当を受けることも可能です。雇用保険料も会社と従業員それぞれに負担割合があり、従業員の負担分のみ給与明細に記載されています。
源泉所得税(源泉徴収)
所得に応じて課せられる税金が所得税です。所得税は本来、納税者(=従業員)が自ら申告し納税します。しかし、会社が従業員の代わりに納税手続きをする制度があるため、源泉所得税として給与から天引きしています。この制度が源泉徴収です。
会社員の場合、12月に「年末調整」という納税の精算手続きをします。源泉徴収された所得税に過不足があれば、還付金や追加徴収の金額が12月または1月の給与明細に記載されます。
住民税
住民票のある自治体に納める税金です。住民税の金額は、前年の所得をもとに決定します。そのため、前年所得がない新社会人は住民税を徴収されません。社会人2年目の6月から徴収が始まり、給与明細にも徴収税額が記載されます。
給与明細の構成要素③「勤怠」
「勤怠」は1ヶ月の労働記録となる項目です。勤怠項目を見れば1ヶ月に何日働いたのか、残業時間はどのくらいあったのかなどが分かります。細かい項目を見ていきましょう。

出勤日数
実際に働いた日数です。出勤日数の他に、就業日数(所定就労日)といった項目がある場合もあります。就業日数(所定就労日)は、会社から労働することを求められた日数です。1日も休まずに出勤していれば、「就業日数=出勤日数」となります。
有休日数
有給休暇を取得した日数です。年次有給休暇は労働基準法によって「その雇入の日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と規定されています。有給休暇の付与日数は勤続年数により異なり、労働基準法で以下のように定められています。
勤続年数 | 付与日数 |
|---|
半年 | 10日 |
1年半 | 11日 |
2年半 | 12日 |
3年半 | 14日 |
4年半 | 16日 |
5年半 | 18日 |
6年半以上 | 20日 |
欠勤日数
会社を休んだ日数です。基本的には1日に一度も出勤しなかった日を指すため、早退や遅刻などは欠勤日数には含まれません。給与明細に有休日数の項目がない場合は、欠勤日数に有給休暇取得日を含めて記載されていることもあります。この辺りは会社によって書き方が異なるので、日数に疑問点があれば会社に確認してみましょう。
実働時間
実際に働いた時間数です。シフト勤務のような働く時間数が変わりやすい職種では、給与明細に実働時間が記載されていることが多々あります。
実働時間は働いた時間のみ記載されるので、休憩時間は含まれません。例えば勤務時間が9時~18時の場合、お昼休憩の1時間を除いた8時間が実働時間です。また、遅刻や早退、残業などがあれば、その分の時間数を足したり引いたりした合計時間が記載されます。
残業時間(休日勤務時間・深夜勤務時間)
1日の所定労働時間を超えて働いた時間数です。残業代は働く時間帯などによって計算が変わるため、休日勤務時間や深夜勤務時間など細かく分けて書かれていることもあります。
なお休日勤務時間は、法定休日(週1回以上の休みの日)または法定外休日(会社で定めた休みの日)に働いた時間数です。深夜勤務時間は、夜22時~朝5時までに働いた時間数です。
初任給の給与明細でよくある疑問
初めて給与明細を受け取ると、ふと疑問を抱くこともあるでしょう。ここでは、初任給の給与明細でよくある疑問に回答します。
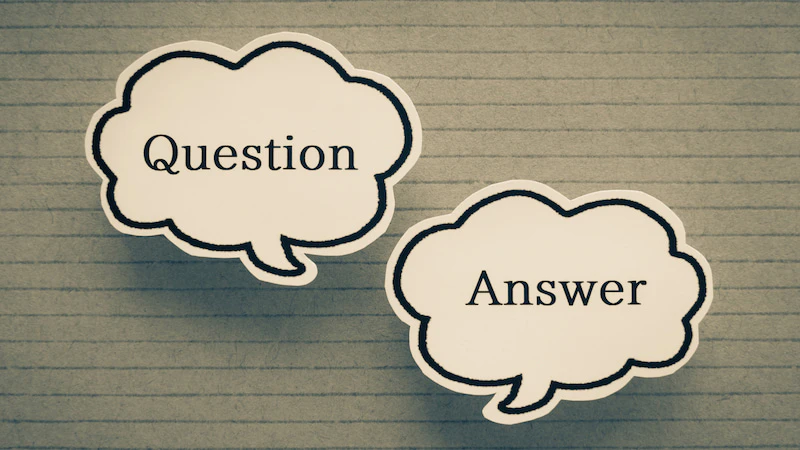
給与明細の保管は必要?
給与明細を保管すべき決まりはないため、内容を確認した後は自分の好きなように処理して構いません。ただし、給与明細を保管しておくと、収入を証明したい場合や確定申告をする場合などに便利です。例えば、以下のような場合に給与明細があると役立ちます。
- ローンを組むために収入証明が必要となったとき
- 失業手当の給付金額を計算したいとき
- 確定申告書類の収入欄を記載するとき
未払い給与があった場合は2年前までさかのぼって請求できるため、確認用の書類として残しておくのも良いでしょう。
給与明細を見れば年収は分かる?
給与明細に年収自体は載っていませんが、自分で計算すれば年収が分かります。年収は控除される前の「総支給額」をベースに計算します。計算式は、以下のとおりです。
年収=(総支給額×12ヶ月)+ボーナス年額
給与の細かい内訳を見るには給与明細が欠かせませんが、手取り額を知りたい場合は銀行口座を見ればすぐに分かります。多くの銀行ではネットバンキングを用意しており、わざわざ通帳を記帳しなくてもスマホやPCから残高確認が可能です。西日本シティ銀行でも、スマホから残高確認やATM入出金手続きができる便利なアプリを用意しています。
まとめ
給与明細には基本給や残業代の他、各種控除額や欠勤日数までさまざまな項目が載っています。支給額や控除額など、自分の給与について細かく知っておくことは非常に大切です。どの項目も必要な情報のため、最初のうちに給与明細の見方を覚えておきましょう。
地方銀行へ入社し、貯金・ローンなど金融商品の販売に従事。 その後、不動産業界へ転職して社会保険や労務管理を担当しながらFP資格を取得。自身の経験から“お金を無駄にしないための”アドバイスをおこなう。
このライターの記事を読む >