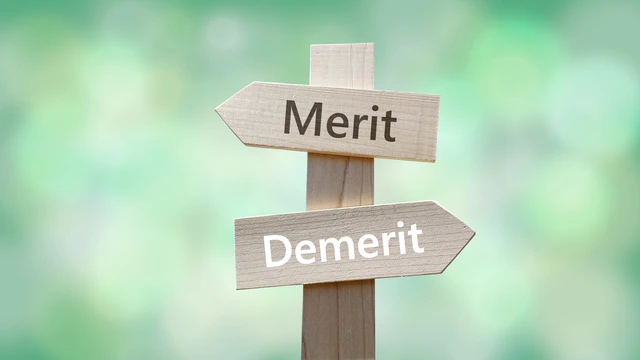株式投資をしていると、自分の保有している銘柄がTOB(株式公開買付け)の対象になることがあります。TOBが実施されると株主にはどのような影響があり、どう対応すればよいのでしょうか。この記事では、TOBの基礎知識と投資家が取れる選択肢について解説します。
TOB(株式公開買付け)をわかりやすく解説

TOB(株式公開買付け)とは、ある企業の経営権を持ちたい企業が、相手の株式を取引所外で買い集める方法のことです。公開買付けを行う企業は株式の「買付け期間」「買付け株数」「買付け価格」を公示し、保有する株主に売却を呼びかけます。
TOBの目的
TOBは他社の経営権を握る以外に、自社株を集める目的としても活用されます。
経営権を得るため
多くのTOBの目的は、企業買収や子会社化です。株主の権利は、配当など利益分配を受け取るだけではありません。株主総会での議決権も、株主の重要な権利です。株主が一定以上の株数を持つのは、その企業の経営権を持つことを意味します。持ち株比率により、株主は次のような権利を持ちます。
- 3分の1超:特別決議への拒否権を持つ
- 2分の1超:普通決議を単独で可決できる(取締役の選任、解任など)
- 3分の2超:特別決議を単独で可決できる(事業譲渡・合併など)
自社株を集めるため
TOBは自社株を買い集めるために行われる場合もあります。自社株を収集する主な目的は、上場廃止や他社からの買収への防衛などです。
TOBの種類
買収する側(買手)と相手企業(売手)の関係によって、友好的TOBと敵対的TOBに分類されます。
友好的TOB
買収する企業が相手企業から了承を得たうえで行うTOBを、友好的TOBといいます。グループ内の企業を完全子会社化するケースなどが、友好的TOBに該当します。日本におけるTOBは、友好的TOBであることがほとんどです。
敵対的TOB
敵対的TOBとは、相手企業の了承なしで行うTOBのことです。敵対的TOBのターゲットになった企業は買収されないための対抗策を打つことが多いので、成功しない可能性もあります。
TOBをする側のメリット・デメリットとは

TOBでの企業買収には、他の買収方法にはないメリットやデメリットがあります。
TOBをする側のメリット
TOBによる買収は、相手企業の株式を一定の価格で一度に買い集めることが可能です。ここでは、買収する企業のメリットについて解説します。
一定の価格で株式を取得できる
市場で株式を買うケースと違い、決められた価格で株式を買い取ります。そのため、市場の株価変動の影響を受けずに株式の買付けが可能です。買取りに必要な費用もあらかじめ見積もれます。
多くの株式を一度に取得できる
TOBでは大量の株式を一括で取得できます。市場で株式を買い集めるには、手間と時間が必要です。TOBは効率的に支配権を握りたい企業にとって、有効な手法といえます。
予定の株式が集まらない場合はキャンセルできる
TOBで買付け株数が目標に達しなかった場合、買付けのキャンセルが可能です。市場で株式を買い集めると、目標株数を取得できなかった場合は相手企業の株式が中途半端に残ってしまいます。TOBでは買付けのキャンセルができるため、余分なコストがかかりません。
目標達成までのスケジュール管理がしやすい
TOBは買付け期間を決めて実施するため、目標達成までのスケジュール管理が容易です。相手企業の株式を市場で買付ける場合、目標とする株数が集まる時期や取得に要する費用は事前にわかりません。目標達成までの時期やコストの見通しが立てられることは、TOBのメリットの1つです。
自社に不足していた経営資源が得られる
TOBが成功し相手企業を支配できるようになると、自社にはない販売網や技術、人材などの経営資源が得られます。新たな経営資源により自社の経営規模が拡大し、事業の成長が見込めることはTOBの大きなメリットです。
TOBをする側のデメリット
買収する企業にとってメリットの多いTOBですが、次のようなデメリットもあります。
市場価格より高く買い取らなければならない
相手企業の株式の目標株数を確実に取得しなくてはならないため、TOBの買付け価格は市場価格より高く設定されています。よって、実施には多くの資金が必要となります。
TOBに失敗することもある
TOBが必ず成功するとはかぎりません。敵対的TOBの場合、相手企業の抵抗によって失敗に終わるケースがあります。友好的TOBの場合、競合する企業が現れて買収できないこともあるのです。
買付けを公開しなければならない
TOBでは、公開買付けに関する情報を公表しなければなりません。敵対的TOBやTOBの実施によって生じたトラブルにより、企業イメージを損なうことも考えられます。たとえTOBが成功しても、社会的な評価が下がるリスクがあることを想定しておくべきでしょう。
期待した効果を得られないリスクがある
TOBによる企業買収が成功しても思ったような効果が得られず、却って業績が悪化してしまうリスクもあります。買収を検討する段階では好ましい結果を想定しますが、負の要素も考えておくことが大切です。
TOBをされる側のメリット・デメリットとは
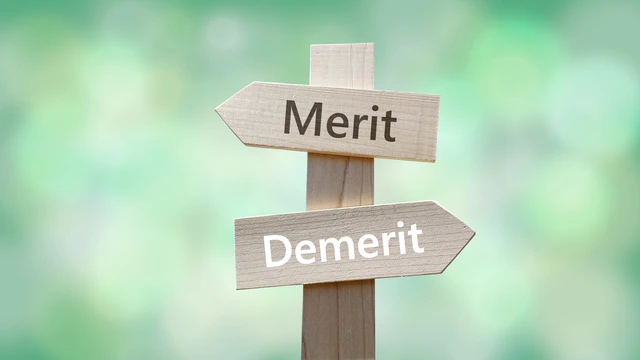
TOBは、買収される企業にもメリットやデメリットがあります。
TOBをされる側のメリット
TOBで買収される企業のメリットは、経営改善や事業拡大が期待できることです。買収企業の資金やブランドにより停滞していた事業が活性化し、買収される側の持つ経営資源が活かされる可能性があります。
TOBをされる側のデメリット
TOBにより買収される企業には、次のようなデメリットがあります。
経営権を失う
TOBによって買収されることは、買収した企業に経営権を握られる状態を意味します。買収される前の経営者の影響力は、持ち株の比率によっては全くなくなる可能性もあるのです。
TOB失敗のリスク
友好的TOBが失敗に終わった場合、買収される側の企業に経営上の問題が生じるおそれがあります。経営統合に向けて準備していたことが、ムダになってしまうからです。TOBのよさと株主のメリットが結びつかないときがあるので、注意しましょう。
社風の変化
TOBが成功すると、買収された企業の社員は別会社の支配のもとで働くことになります。買収した企業と自社の社風や理念が違いすぎると、退職する社員も出てくるでしょう。人材は企業の重要な経営資源なので、社風の急激な変化がマイナスに働かないような配慮が必要です。
業績が悪化する場合も
TOBでは、買収側と相手先企業の相互のシナジー効果が期待されます。しかし、TOBにより経営が統合されると却って経営が悪化する場合もあります。友好的TOBであっても、双方にどのようなメリットがあり懸念すべき点はないかを慎重に精査しましょう。
保有している株式がTOBされたらどうする?

上場企業の株式を保有している一般的な投資家は、TOBに遭遇する可能性があります。保有している株式がTOBの対象になったら、どうすればよいのでしょうか。
TOBに応じる
TOBでは買取り価格が市場価格を上回るケースがほとんどです。自分が買付けた価格よりTOB価格が高いのであれば、TOBに応じるメリットは大きいといえます。ただし、市場価格が上昇してTOB価格を上回ることもあるので、TOB発表後の株価を確認してから申し込むようにしましょう。また、TOBでは買付け株数に上限が設けられているケースもあり、申し込んでも買ってもらえない可能性があります。その場合はTOBに申し込まず、市場で売却したほうが賢明です。
市場で売る
TOBの対象になった株式の市場での売却も可能です。市場での売却には手数料が必要ですが、TOBに応じるよりも手間がかかりません。株式全部買付けの場合、TOBが発表されるとTOB価格に近い金額で売却できる可能性が高くなります。またTOBが不成立になったり、買取り上限を設けられていると買い取ってもらえなかったりする可能性もあります。それらを考慮すると、TOBに申し込まないで市場で売却することも有力な選択肢です。
保有を続ける
保有株式がTOBの対象になったからといって、必ず手放さなければならないわけではありません。そのまま保有し続けることも可能です。仮にTOB価格や市場価格がTOB発表前より高水準だとしても、株式をより高値で買い付けている場合は損失が確定してしまいます。そのようなケースでは、そのまま保有することも選択肢の1つです。
上場廃止に注意
株式全部買付けなどの場合、TOB完了後に上場廃止が予定されていることがあります。保有株式が上場廃止になると市場での売買ができなくなり、証券会社では取り扱えなくなります。TOB後の上場廃止の可能性の有無については、該当企業のホームページなどで必ずチェックするようにしましょう。
強制的に買い取られることも
TOBに応じなくても、成立後に買取り企業が一般の株主から株式を強制的に取得することがあります(スクイーズアウト)。このような場合、保有し続けたくてもTOB価格で株式を手放さなくてはなりません。
まとめ
上場株式を保有していると、自分の持っている銘柄がTOBの対象になることもあります。その場合は、必ずTOBの内容を確認しましょう。TOBには不成立のリスクや買い取ってもらえないおそれがあるため、市場での売却が一番無難な選択肢といえます。ただし、売却価格やTOB価格が買付け価格を大きく下回る可能性もあります。TOBが発表されたら、慌てずにとるべき行動を考えましょう。
群馬FP事務所代表、CFP®、証券外務員二種、DCアドバイザー
国内生保に法人コンサルティング営業を経て2007年に独立系FPとして開業。企業型確定拠出年金の講師、個人向け相談全般に従事。現在は法人向けには確定拠出年金の導入コンサル、個人向けにはiDeCoやNISAでの資産運用や確定拠出年金を有効活用したライフプランニング、リタイアメントプランニングを行っている。
このライターの記事を読む >