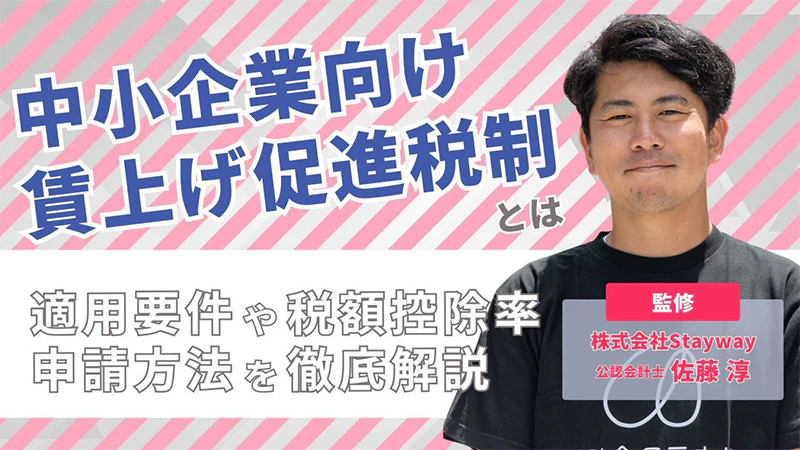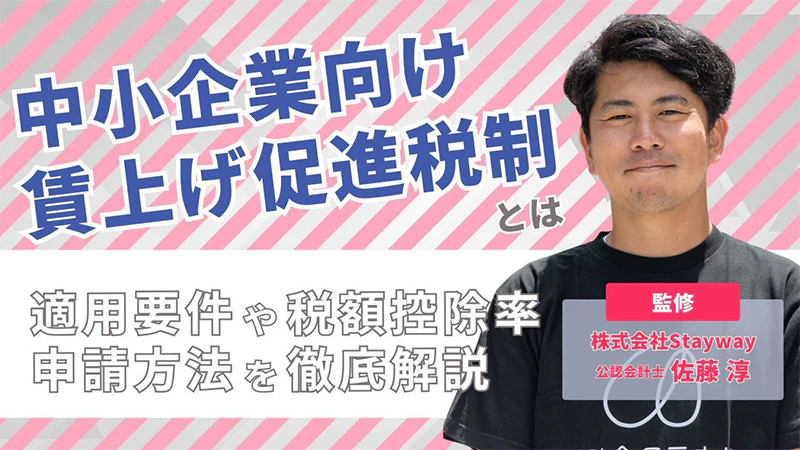
令和7年度の地域別最低賃金額が改定され、多くの都道府県で過去最高水準の引き上げとなりました。
中小企業や小規模事業者等にとって賃上げ対応は、従業員の確保や定着のため不可欠である一方、大きな負担となります。
こうした企業の負担を軽減し、賃上げを後押しする制度のひとつに「賃上げ促進税制」があります。
そこでこの記事では、賃上げ促進税制の3つの制度のうち、「中小企業向け賃上げ促進税制」の概要や適用要件、税額控除率、申請方法などを解説します。
※記事内容は、令和7年10月6日時点の情報です。最新の情報は、必ず公式HPをご確認ください。
中小企業向け賃上げ促進税制とは?
参照:中小企業庁 中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック
掲載ページ:中小企業庁 中小企業向け「賃上げ促進税制」
賃上げ促進税制とは、企業が賃上げを実施した場合に、その賃上げ額の一部を法人税などから税額控除できる制度です。
税額控除が認められると、全雇用者の給与等支給額の増加分のうち、最大45%を控除できます。
この制度の目的は、「成長と分配の好循環」の実現に向け、企業が得た収益を従業員に還元することです。
また、賃上げ促進税制には次の3つの制度があり、従業員数や資本金の規模によって利用できる制度が異なります。
制度名 | 適用対象 |
|---|
①全企業向け賃上げ促進税制 | 青色申告書を提出する全法人または個人事業主が対象 |
②中堅企業向け賃上げ促進税制 | 青色申告書を提出する従業員数2,000人以下の法人または個人事業主が対象 |
③中小企業向け賃上げ促進税制 | 青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業組合等)または従業員数1,000人以下の個人事業主が対象 |
各制度の対象者を図に表すと、次のとおりです。中小企業や小規模事業者の場合、すべての制度を活用可能です。

出典:経済産業省 賃上げ促進税制
この記事では①から③の制度のうち、「中小企業向け賃上げ促進税制」に焦点を当てて解説します。
参照:中小企業庁 ミラサポPlus 担当者に聞く「賃上げ促進税制」
参照:経済産業省 賃上げ促進税制
適用期間
「中小企業向け賃上げ促進税制」は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象です。
個人事業主については、令和7年から令和9年の各年が対象となります。
適用要件・税額控除率

出典:中小企業庁 中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック
掲載ページ:中小企業庁 中小企業向け「賃上げ促進税制」
適用要件は、「必須要件」「上乗せ要件①」「上乗せ要件②」に分けられ、すべて満たす場合、最大45%の税額控除が受けられます。
ここでは、各要件の内容と税額控除率について解説します。
(必須要件)賃上げ要件
必須要件として、雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加している必要があります。
雇用者給与等支給額とは、国内雇用者に対して支給した課税対象の給与・賞与・手当などの合計額を指します。要件を満たすかどうかは、以下の式で確認します。

出典:中小企業庁 中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック
掲載ページ:中小企業庁 中小企業向け「賃上げ促進税制」
この計算結果が1.5%以上であれば、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%の税額控除を受けられます。
同様に、この計算結果が2.5%以上となる場合は、控除対象雇用者給与等支給増加額の30%の税額控除を受けることができます。
(上乗せ要件①)教育訓練費増加要件
上乗せ要件のひとつめに、「教育訓練費増加要件」があります。
具体的には、次の2つの要件を満たす場合、税額控除率を10%上乗せします。
①教育訓練費の額が前事業年度と比べて5%以上増加していること
②教育訓練費の額が適用事業年度の雇用者給与等支給額の0.05%以上であること
教育訓練費とは、主に次の項にすべて該当する費用を指します。
● 適用事業年度において、損金として算入できる費用であること
● すべての国内雇用者を対象とするもの
● 法人または個人事業主が、その雇用者に対し、職務に必要な技術や知識を習得・向上させるために支出した費用であること
前事業年度の教育訓練費が「0円」の場合でも、上乗せ要件の適用を受けることは可能です。
ただしこの場合、適用事業年度の教育訓練費の額が適用事業年度の雇用者給与等支給額の0.05%以上であることが要件となります。
この他、対象となる教育訓練費の範囲が定められていますので、申請検討の際は必ず事前に詳細情報をご確認ください。
(上乗せ要件②)子育てとの両立支援・女性活躍支援要件
もうひとつの上乗せ要件に「子育てとの両立支援・女性活躍支援要件」があります。
具体的には、次のいずれかを満たしている必要があります。
● 適用事業年度中に「くるみん認定」「くるみんプラス認定」、または「えるぼし認定(2段階目以上)」を取得していること
● 適用事業年度の終了時点で「プラチナくるみん認定」「プラチナくるみんプラス認定」、または「プラチナえるぼし認定」を取得していること
上記いずれかを満たした場合、税額控除率を5%上乗せします。ただし、適用事業年度終了時点までに当該認定が取り消された場合は、対象外となるのでご注意ください。
また、くるみん認定、くるみんプラス認定およびえるぼし認定(2段階目以上)は税制を適用する事業年度に認定を受けることが要件となっています。
そのため、過去に取得した認定をもって上乗せ要件の適用を受けることはできません。
適用申請方法
「中小企業向け賃上げ促進税制」を利用するにあたり、税務申告の前に特別な手続きは不要です。ただし、適用を受けるには確定申告の際に、次の書類を添付する必要があります。
● 税額控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額
● 控除を受ける金額
● その計算に関する明細書
● 適用額明細書(法人のみ)
控除しきれない金額(未控除額)を翌年度以降に繰り越す場合は、上記に加えて「繰越税額控除限度超過額の明細書」が必要となります。
赤字である等の理由により控除を受ける金額が0円で、全額を未控除額として翌年度以降に繰り越す場合も同様です。
また、教育訓練費要件の上乗せ措置を利用する場合は、次の項目を記載した書類を作成・保存しておく必要があります。提出は不要です。
● 教育訓練等の実施時期
● 教育訓練等の内容・期間
● 受講者
● 教育訓練費の支払証明
さらに、後述する「繰越控除措置」を利用する場合には、以下の点にご注意ください。
● 未控除額が発生した事業年度以後の各事業年度の確定申告書に、繰越税額控除限度超過額の明細書を添付すること
● 繰越控除を受けたい事業年度の確定申告書に、繰越控除額を記載し、その計算明細書を添付すること
繰越控除措置について

出典:中小企業庁 中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック
掲載ページ:中小企業庁 中小企業向け「賃上げ促進税制」
「繰越控除措置」とは、要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額について、翌年度以降5年間にわたり繰越を可能とする制度です。
繰越税額控除を受けようとする事業年度においては、青色申告書を提出する必要があります。
中小企業者等または青色申告書を提出する常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主に該当しない場合でも適用可能です。
まとめ
この記事では、「中小企業向け賃上げ促進税制」の概要や適用要件、税額控除率、申請方法などを解説しました。
本制度の活用により、賃上げによる税負担の軽減が可能となりますので、ぜひ、活用をご検討ください。
株式会社Stayway 代表取締役CEO 公認会計士
東京大学経済学部卒業 / 公認会計士及び経営革新等支援機関デロイト トウシュ トーマツ出身。東京及びシアトルにおいて、IPO支援に従事したのち、香港本社のPEファンド・経営コンサルティングファームに勤務。「中小企業や地域のポテンシャルを開放」するため、2017年株式会社Staywayを創業。
※本記事の監修者です。
このライターの記事を読む >