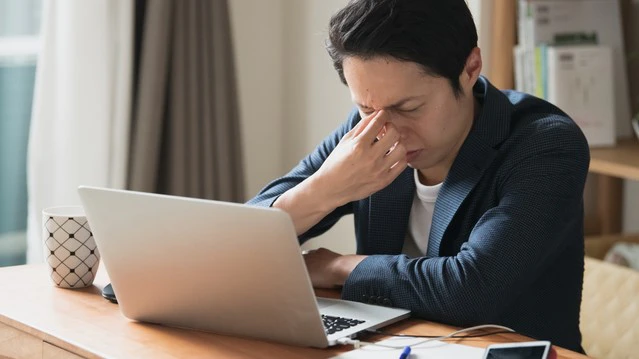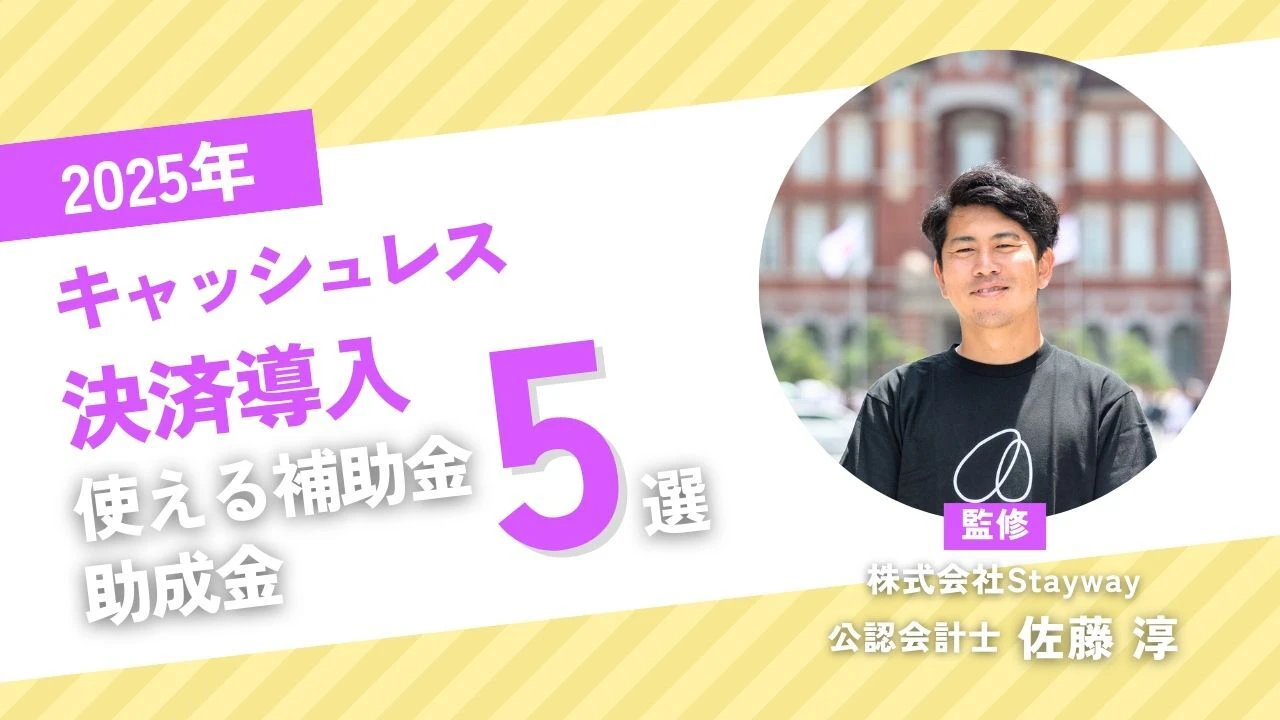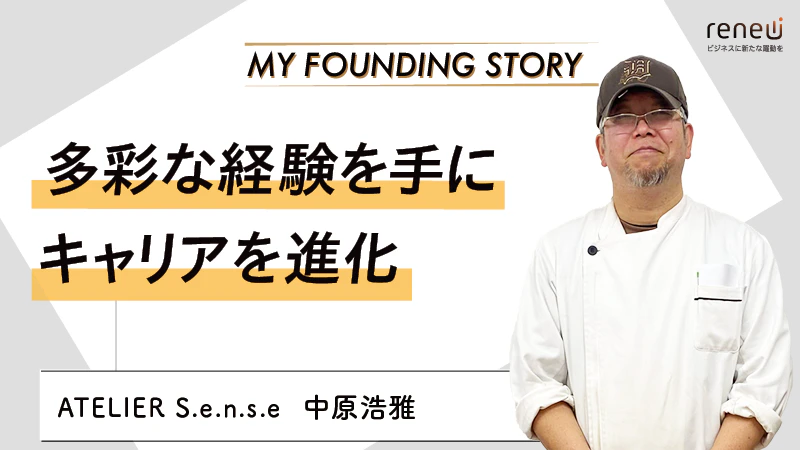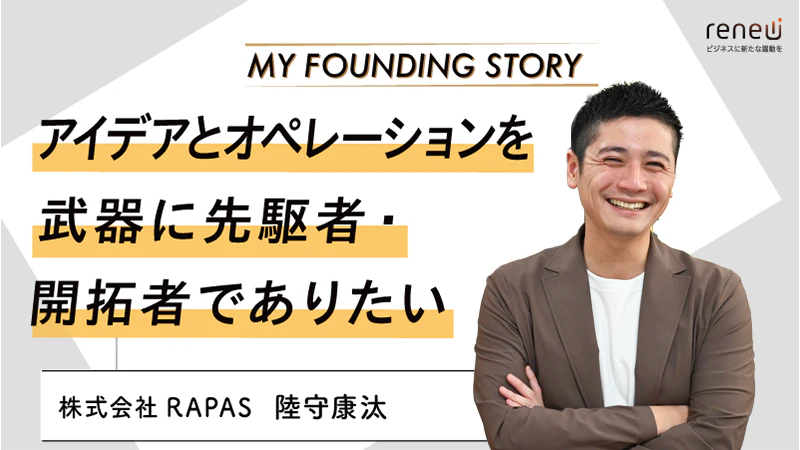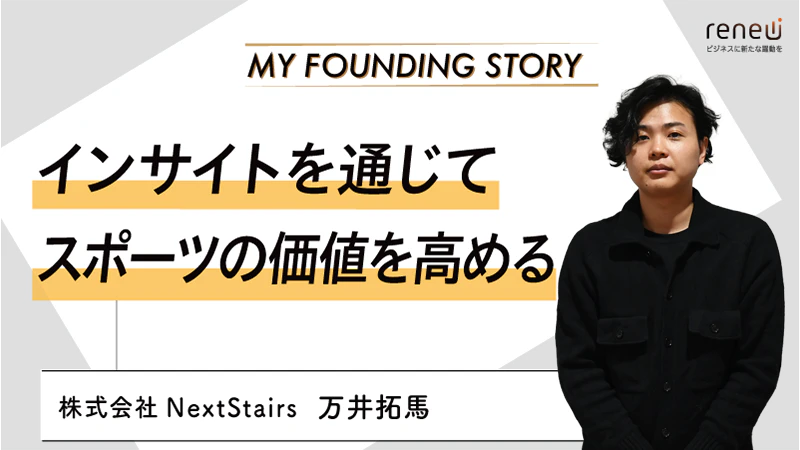Web3.0という単語がよく話題になっていますが、これまでのWebとの違いが分からない人は多いのではないでしょうか。今回はWeb3.0の概要を理解することを目的に、概念や具体的な解決事例などを詳しく解説します。
Web3.0とは?必要性、注目される理由とは
まずはWeb3.0とは何か、必要性や注目される理由を従来のWeb1.0、Web2.0がもつ歴史と比較して紹介します。
Web1.0(ホームページ時代)
Web1.0はインターネットの黎明期で、「発信者から閲覧者に一方通行で発信が行われていた時代」のことです。WWW(World Wide Web)が生まれた1990年(平成2年)から2005年(平成17年)ころまでが、Web1.0の時代といわれています。
ウェブの情報は基本的に閲覧するのみで、一部のコメントなどを除き双方向のやり取りはできませんでした。そのため、個別のやり取りにはメールやチャットが用いられていました。また、通信速度も非常に低速だったので、ウェブサイトはhtmlによるテキスト形式のコンテンツが多く、画像もほとんど使われていません。
Web2.0(SNS時代)
2005年(平成17年)以降、Web1.0からの変化として、Web上での双方向のやり取りが行えるようになった時代をWeb2.0といいます。FacebookやYouTube、TwitterなどのSNSが代表例です。さまざまなコンテンツで発信者と閲覧者が相互にコミュニケーションを行えるようになり、また誰でも発信できるようになりました。
Web2.0では技術の発展に伴い、Webの自由度や利便性が大幅に向上しました。しかしWeb上の情報がプラットフォーマーに独占され、中央集権的な構造となる問題も生じたのです。
プラットフォーマーによる搾取が問題となっている
例えばGoogleのサービスは非常に便利ですが、Webの閲覧履歴や個人情報は対価としてGoogleに収集されています。この状況は、プライバシーが企業に管理されるだけでなく、Googleの利益追求のために恣意的に運用されていることを指しています。
ほかにも、ユーザーの作ったコンテンツがプラットフォーマーによって削除されるなど、あらゆるデータの所有権がユーザーにないことも問題点です。ユーザーが生み出した価値がプラットフォーマー側に搾取されている状態を改善したいという声が、高まりつつあります。
Web3.0(ブロックチェーン時代)
そんな中、Web2.0の抱える問題点を解決できる存在として話題となっているのがWeb3.0です。Web3.0は、Ethereumの共同創設者であるギャビン・ウッド氏が提唱した概念になります。明確な定義は行われていませんが、最も大きな特徴は「権力分散型」のWebということです。
Web3.0では、あらゆるサービスは自律的に動き、プラットフォーマーが存在しません。個人データは細分化して保存されることから、保有者以外が見ることはできず、個人情報は守られます。また、全てのクリエイターがサービスに貢献でき、貢献した分の報酬を得られるため、透明性が高く公平な取引が行えるというメリットもあります。
Web3.0が成り立つ仕組みや技術とは

続いては、Web3.0において権力を個人に分散させるために、どのような仕組みや技術を用いているのかを解説します。
ブロックチェーン技術が根幹
Web3.0の根幹となっているのは、「ブロックチェーン」技術です。「多くのユーザーが同じデータを保存し、データ間のつながりを持たせることで改ざんや消失をなくせる技術」のことです。ユーザーが持つデータの「ブロック」がほかと繋がりあって鎖に見えることから、ブロックチェーンという名前がつけられています。
管理者がおらず公平で透明な取引が可能
ブロックチェーンには特定の管理者が存在しておらず、データを保有するユーザー同士をつなぐチェーンしかないのが特徴です。チェーンを介して、多数のユーザー同士が情報の正しさを管理しています。管理者がいなくとも正しくチェックできるため、セキュリティは非常に高いといえるでしょう。また、全てのユーザーが分割してデータを保持するので、公平で透明な取引が可能です。
Web3.0で解決できる問題

ブロックチェーン技術を用いたWeb3.0は、Web2.0が持っていた本質的な課題を解決することが可能です。解決できる課題について、具体的に記していきます。
セキュリティが向上しプライバシーが守られる
Web3.0ではブロックチェーンにより情報が分散して保存されているため、データが流出する心配はありません。また、企業によって個人データが恣意的に使われることもなくなります。ブロックチェーンへのハッキングは、同時に複数の端末に行わなければ情報を得られないことから非常に難しいです。そのため、セキュリティの向上にもつながります。
国境や企業による発信制限がなくなる
Web2.0は、例えば中国でYouTube、Twitterなどの利用が禁じられているように、国家や企業によってアクセスを制限される場合があります。しかし、ブロックチェーンは理論上、どんな国家や社会に対しても規制を受けずにアクセス可能です。国家によっては、仮想通貨などのブロックチェーン技術によって発生したサービスを規制する動きも出ています。しかし、将来的には全世界に広がっていくことが予想されています。
クリエイター中心の経済圏が生まれる
WEB2.0では、企業が用意したプラットフォームにおいてクリエイターがさまざまなコンテンツを提供し、収益を得ています。プラットフォーマーが決めたアルゴリズムに則って収益が決まるため、クリエイターの報酬は貢献度に左右されません。
Web3.0であれば、中央集権的なプラットフォーマーがいません。個々のクリエイターや企業同士が直接やり取りを行うため、クリエイターを中心とした経済圏が生まれます。これにより、プラットフォーマーによる搾取を受けることなく、貢献度に比例した収益が得られるでしょう。
個人情報や行動履歴データを自分で管理できる
これまでは、Webを利用したユーザーの個人情報や行動履歴はサービスを提供する企業に収集・管理されていました。そのため、ユーザー自身がこれらのデータを管理できないといった問題がありました。その影響は、Googleが個人の興味に合わせた広告を表示させることとつながります。Facebookが年齢・性別・地域ごとのユーザー行動を把握して、広告掲載に役立てているのも同様です。さまざまな所で企業の収益につながっており、これらの企業が大きな力を持つ原因にもなっています。しかし、Web3.0であれば個人情報は個人が管理できるようになります。意図しない広告の表示などもなくなり、広告を表示させる代わりに自分が報酬を得ることも可能です。
P2P取引により仲介組織を排除できる
Web2.0ではプラットフォーマーだけでなく、さまざまな企業が仲介してサービスが成り立っています。しかし、仲介組織によって手数料が引かれるのは、クリエイターにとって大きな問題です。Web3.0ではP2P取引が基本なので仲介による手数料はほとんどなくなり、クリエイターの利益最大化が期待できます。
インターネットのシステム障害に強くなる
Web3.0は分散型のネットワークで多くのユーザーに情報が蓄積されているため、システム障害でほとんど影響を受けません。アクセス過多による通信制限やシステムダウンの可能性がなくなり、より安定したサービスを利用できるようになります。
具体的な活用事例

Web3.0はまだ新しい概念ですが、仮想通貨を始めさまざまなサービスに適応され始めています。ここからは、Web3.0の具体的な活用事例を紹介します。
Ethereum
分散型のアプリケーションを動かすための、プラットフォームです。主要な機能として、さまざまな契約を自動的に締結できる「スマートコントラクト」があります。認証機関を必要とせず当事者間での契約が行えるもので、この機能を用いて多くの分散型アプリケーションが作られているのです。信頼性の高い仮想通貨というイメージが強いですが、仮想通貨はあくまでプラットフォーム内の通貨として開発されています。主体はプラットフォームです。
Brave
Web3.0により生まれた、新しい検索プラットフォームです。特定の企業によって運営されていないため広告は掲載しておらず、ユーザーは快適に検索が行えます。セキュリティの高さや広告を表示しないことによるWeb検索の高速化が支持され、多くのユーザーが採用し始めています。広告を意図的に表示させる代わりにユーザー自身が仮想通貨の収益を得る機能も、ほかにはない特徴です。
IPFS
「Inter Planetary File System」の略になります。ユーザー同士のP2P通信を確立する、Web3.0のサービスに欠かせない分散型のネットワークプロトコルです。Web2.0で主流のHTTPでは、サーバーに情報を蓄積してユーザーが読み込む形式です。一方、IPFSではそれぞれのネットワーク参加者が情報を保有し、ユーザーは直接データを読み込む形となります。
IPFSはあくまでP2Pでデータのやり取りを行う技術であり、単体ではWeb3.0のサービスはできません。しかし、ブロックチェーン技術などと合わせて、さまざまなサービスを開発できます。
My Crypto Heroes
2018年(平成30年)に日本で開発された、キャラクターや武器を集めて育てるゲームアプリの1つです。ブロックチェーン技術を使っており、ゲーム内のキャラクターや武器がNFT(非代替性トークン)で作られているのが特徴です。
ゲーム内で育てたキャラクターや武器がそのまま資産となり、売買によって収入を得られるようになっています。NFTは改ざんや複製が不可能で特定のサーバーを介さないため、データとしての価値が保証されるのが特徴です。
Web3.0の注意点
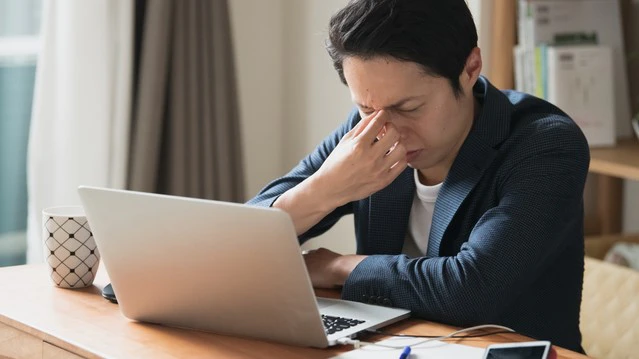
プラットフォーマーの存在による課題が解消され、さまざまなメリットのあるWeb3.0ですがデメリットも生まれています。ここからは、Web3.0を利用する際の注意点について紹介します。
ハッキング被害にあう可能性がある
Web3.0ではデータが分散されているため、データ全体のハッキングに対する堅牢性は非常に高いです。しかし、個々人で見た場合はセキュリティ上の問題が残っています。特に、個人の認証情報が1つしかないのが問題です。認証情報をハッキングされると自身に関する情報が全て漏洩してしまうことが、大きな問題として指摘されています。認証情報が堅牢であったとしても、何らかのきっかけで突破された際の影響が大きくなるのはデメリットです。
問題が発生したときの解決が難しい
Web3.0では特定の管理者が存在していませんが、それがデメリットとなる場合もあります。認証情報を紛失してしまった場合、管理者がいないと二度と自身の情報にログインできなくなります。また、認証情報をハッキングされてしまった場合も対応方法が存在しません。何か問題が生じた場合は自己責任で対応するしかなく、解決が非常に難しいです。
まとめ
Web3.0はブロックチェーン技術を用い、特定の企業が独占していたプラットフォームを分散化させます。数多くの国家や企業がWeb3.0に注目しており、投資も加速している状況です。社会に大きな影響を与えるのは間違いないので、技術の発展を注視してみてはいかがでしょうか。