青色申告と白色申告の違いって何?簡単にわかる基礎知識&メリット・デメリット
By 河野 雅人
|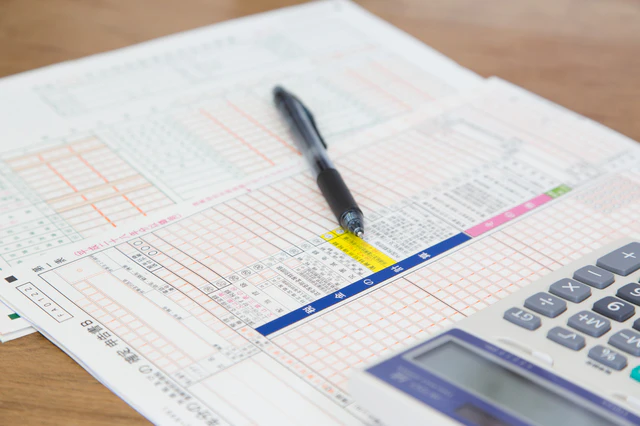
所得税の確定申告には青色申告と白色申告の2種類がありますが、どっちがいいのか迷う人もいるのではないでしょうか。青色申告にすれば税金面でメリットがある一方、手続きや申告が面倒というイメージがあるかもしれません。
そこで今回は、青色申告と白色申告のそれぞれの意味と、メリット・デメリットについて解説します。
確定申告における青色申告と白色申告の違いとは?
青色申告とは
青色申告とは、日々の取引を一定のルールに基づいて帳簿に記帳することにより確定申告する方法です。
白色申告に比べて税金面でさまざまなメリットがあるので、確定申告で青色申告にするか白色申告にするか悩んでいる人には、ぜひおすすめしたい申告方法です。
なお、青色申告は誰もが適用できるわけではありません。
税法では「所得」は10種類に分けられており、このうち「不動産所得」「事業所得」「山林所得」のいずれかを得ている個人事業主が、青色申告事業者となることができます。
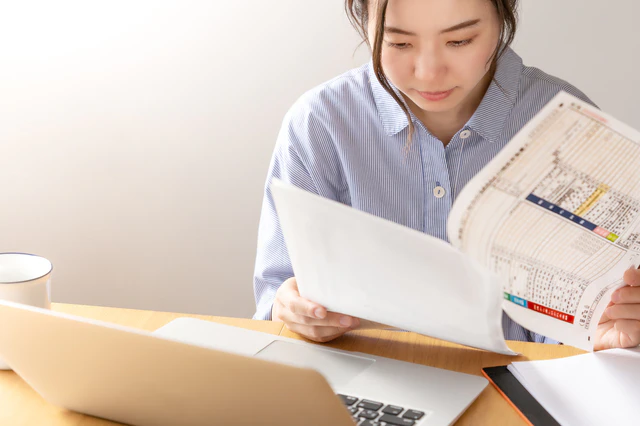
条件を満たせば、個人事業主や自営業以外の人も利用できる
一般的には、個人事業主や自営業の人は「事業所得」を得ている場合が多いでしょう。一方、サラリーマンの人は給与所得者に該当しますので、青色申告事業者となることはできません。
しかし、たとえばインターネットビジネスや不動産投資を行っている人など、サラリーマンでも副業等でなんらかの事業を行い、継続的に収益を得ている場合は、青色申告事業者となることができます。
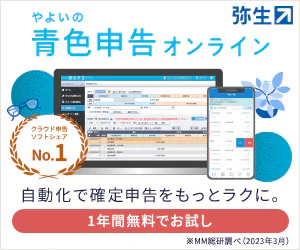
白色申告とは
後述しますが、青色申告では事前に「青色申告承認申請書」を提出し、承認される必要があります。
一方で白色申告は、青色申告のような書類の提出は必要とされていません。新たに開業し、青色申告の申請をしなければ、白色申告として扱われるためです。
白色申告は青色申告ほどきっちりとした記帳は要求されないので、青色申告よりも簡単に申告できるのが特徴です。事業で継続して利益が出ている場合には、青色申告にした方が節税のメリットを受けられますが、そうでなければ白色申告を選んだ方が手間はかからないといえます。
青色申告のメリット

上で述べたとおり、青色申告には税金面で多くのメリットがあります。具体的には、下記のようなメリットが挙げられます。
最大55万円(電子申告の場合は65万円)の特別控除額
青色申告では、最大で55万円(65万円)の特別控除を受けることができます。つまり、事業で得られた利益から最大で55万円(65万円)を差し引くことができるため、節税につながります。この「青色申告特別控除」は白色申告では受けることができません。
ただし、翌年の3月15日という所得税の確定申告書の提出期限を過ぎてしまった場合、特別控除は10万円になってしまいますので注意しましょう。
家族に対する給料を経費として計上できる
家族に対する給料は、原則として経費に算入することはできません。しかし青色申告では、税務署に「青色事業者専従者給与に関する届出書」を提出することによって、配偶者や親族などの家族に対する給料を必要経費として計上することができます。
ただし、しっかりと業務を行い、それに見合った給料であることや、「もっぱらその業務についていること」などの条件がありますので、子どもが学生の場合などは給料を支払っても経費にはできません。
白色申告の「専従者控除」よりメリットが大きい
家族への給料の経費算入として、白色申告にも「専従者控除」という制度があります。これは「青色専従者給与」とは異なり、最大86万円の控除であるなどの条件があるため、節税面においては青色申告の方がメリットが大きいといえるでしょう。
純損失を3年間繰越できる
青色申告では、事業から出た損失を3年間繰り越すことができます。つまり、損失が出ても、その損失分を翌年以降の3年間に発生した利益と相殺することができます。
特に事業を始めたばかりの時期はコストばかりが先行してしまい、事業初年度は損失が出やすい傾向にあります。この損失を軌道に乗った翌年以降の利益と相殺できることは、青色申告の大きなメリットのひとつといえるでしょう。
当期の損失を前年の利益と相殺できる(繰戻し還付)
当期に損失となってしまった場合、前年の利益と相殺することで、前年に支払った税金の一部の還付を受けることができます。これを「繰戻し還付」といいます。損失となった場合でも還付を受けられるので、損失の穴埋めをすることができます。
経費として認められる範囲が広い
個人事業主の中には、自宅を事務所として働いているというケースもあるでしょう。このとき、家賃や水道光熱費など「家事関連費」と呼ばれる費用は、原則として経費には認められません。
しかし青色申告なら、事業で使ったことを証明できれば、事業用の部分(割合)を何らかの基準で合理的に見積もり、その分を経費にすることができます。
使用割合に応じて経費に計上できる
たとえば家賃の場合、仕事で使っている部屋の面積が全体の20%ならば、家賃の20%を必要経費にできます。電気代や電話代についても同様に、使用割合に応じて経費に計上することができます。これら事業部分の経費処理は、大きな節税効果が期待できます。
白色申告でも経費計上は認められますが、認められる範囲は青色申告に比べて限定されます。したがって、自宅兼事務所としている個人事業主にとって、青色申告を選ぶメリットは大きいといえるでしょう。
30万円未満の事業用の固定資産を一括で経費に計上できる
少額減価償却資産の特例
会計上、固定資産は「減価償却」するのが原則となっています。これは、その取得価額を資産に計上し、毎期一定の方法で数年にわたって費用に落としていくというものです。
この減価償却において、青色申告の場合は30万円未満の事業用固定資産に限り、その取得価額を一括で経費に計上することができます。これを「少額減価償却資産の特例」といいます。取得価額の合計額は300万円が限度となっているため、その点には注意しましょう。
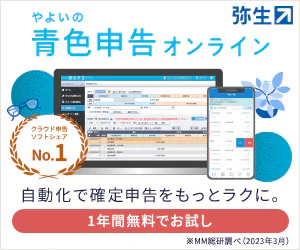
青色申告のデメリット

多くのメリットがある一方、青色申告には下記のようなデメリットがあります。
複式簿記の知識が必要
複式簿記とは
簿記とは、日々の取引を帳簿に記帳する際の一定のルールのことをいいます。単式簿記と複式簿記の2種類があり、単式簿記は家計簿など現金の出入りを単純に記帳するものです。一方、複式簿記はすべての取引を「借方」と「貸方」に整理して記帳しなければなりません。
青色申告では、複式簿記によって帳簿の記帳を行うことが原則とされています。慣れればそれほど大変な作業ではありませんが、簿記の知識と記帳する手間を要することはデメリットといえるでしょう。
求められる帳簿や書類が多い
主要簿と補助簿
青色申告のメリットを受けるためには、複式簿記によるいくつかの帳簿の作成が義務づけられています。一般的には「主要簿」と呼ばれる「総勘定元帳」や「仕訳日記帳」、さらに取引を管理するための「補助簿」と呼ばれる帳簿があります。
主要簿 | |
|---|---|
総勘定元帳 | 勘定科目ごとの増減をまとめたもの |
仕訳日記帳 | すべての取引を簿記の仕訳の形で日付順に並べたもの |
補助簿 | |
現金出納帳 | 現金の入出金をまとめたもの |
預金出納帳 | 預金口座の入出金をまとめたもの |
得意先台帳(売掛帳) | 得意先ごとに売上高・回収状況をまとめたもの |
仕入先台帳(買掛帳) | 仕入先ごとに仕入高・支払い状況をまとめたもの |
経費帳 | 経費の支払いをまとめたもの |
固定資産台帳 | 固定資産の管理・減価償却計算のためにまとめたもの |
青色申告承認申請書
青色申告を行うには、青色申告を始めたい年の3月15日までに、管轄の税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。提出した月の翌月までに却下などの通知がなければ、承認されたものと考えてよいでしょう。一度承認されれば、翌年以降は提出する必要はありません。
開業したばかりの個人事業主で、開業した当初から青色申告を行いたい場合は、開業してから2か月以内に「青色申告承認申請書」を提出します。「開業届」と同時に提出することが一般的です。
青色事業専従者給与に関する届出書
青色事業専従者給与を必要経費として参入するためには、「青色申告承認申請書」に加え、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要となります。
確定申告時の提出書類
確定申告の際には、「確定申告書B」と「青色申告決算書」を税務署に提出することになります。帳簿や領収書の提出は必要ありませんが、原則として7年間の保存が義務づけられています。
青色申告ソフトを使えば簡単に帳簿の記帳ができる
簿記の知識がほとんどなく難しいと感じる場合や、記帳する時間があまり取れないという人は、市販の青色申告ソフトを使うとよいでしょう。昨今の会計ソフトを利用すれば、簿記や税金の知識がなくても、帳簿の記帳から申告書の作成まで簡単に行うことができます。
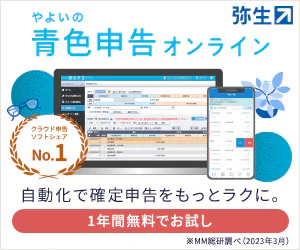
白色申告のメリット

青色申告よりも手続きが簡単
白色申告は税務署に届出をして承認を得る必要がないため、青色申告よりも手続きが簡単といえます。
また、青色申告で求められる複式簿記と比べると、一部の取引を月ごとにまとめて記帳するなど簡易な方法による記帳が認められているため、記帳の手間を省くことができるでしょう。
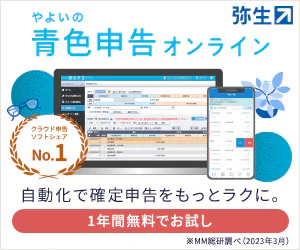
白色申告のデメリット
税金面のメリットが受けられない
白色申告のデメリットを一言でいうと、税金面でのメリットが受けられないことです。たとえば、青色申告特別控除や損失の繰越など、青色申告で認められている節税メリットについて、白色申告では受けることができません。
申告する必要がないわけではない
手間がかからないとはいえ、白色申告は申告の必要がないわけではありません。「申告しなくてもよい」と思い込んで申告漏れとなれば、思いもよらない多額の税金を請求される場合もあります。確定申告が必要かどうかをきちんと確認するようにしましょう。
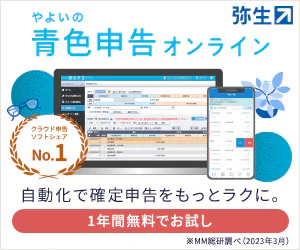
青色申告と白色申告のメリット・デメリットを比較

これまで述べてきたように、青色申告には税金面において多くのメリットがあり、そういったメリットを受けられないことが白色申告のデメリットといえます。
反対に、青色申告は書類や手続き面においてデメリットがありますが、そういった複雑さがない点は白色申告のメリットといえるでしょう。
両者をわかりやすく比較できるよう、青色申告と白色申告のメリット・デメリットを一覧にしてまとめます。
青色申告 | 白色申告 | |
|---|---|---|
メリット | ・最大で55万円(電子申告の場合は65万円)の青色申告特別控除を受けることができる ・青色事業専従者給与を必要経費として算入できる ・純損失の繰越、繰戻しができる ・認められる経費の範囲が広い ・30万円未満の事業用資産を一括で経費に計上できる | ・青色申告よりも簡素な帳簿づけでも問題はない |
デメリット | ・簿記の知識が必要となる ・事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要 ・記帳の手間がかかる | 青色申告特別控除など、青色申告で認められる節税メリットを受けることができない |
まとめ
青色申告と白色申告には、それぞれメリット・デメリットがあります。簡単にいえば、青色申告のメリットは税金面での大きな優遇を受けられること、そして白色申告のメリットはその手軽さといえます。
それぞれのメリット・デメリットを比較し、事業に合わせて適切な申告方法を選択するようにしましょう。
- 青色申請
- 白色申請
Writer

河野 雅人
公認会計士、税理士、CFP
大手監査法人に勤務した後、会計コンサルティング会社を経て、税理士として独立。中小企業、個人事業主を会計、税務の面から支援している。独立後8年間の実績は、法人税申告実績約300件、個人所得税申告実績約600件、相続税申告実績約50件。
このライターの記事を読む >おすすめの記事

お役立ち
2025.10.23
対談記事【ビジネスのヒント】|接骨院から建設業へ。驚きの経歴と経緯
経営に関する悩みや課題を抱える事業経営者の皆さまにとって、銀行の営業担当者は心強いサポーターの一人です。そこで、リニュー編集部では、事業経営者と西日本シティ銀行の営業担当者にスポットをあててインタビュー。サポートのきっかけや、事業の成功までの道のりなどをざっくばらんにお話しいただきます。

ニュース
2025.09.30
【今月のZero-Ten Park】株式会社ストリ|心と体に美しさと健やかさを
福岡を中心に世界5カ国15拠点を展開するシェアオフィス&コワーキングスペース「Zero-Ten Park」。そこに入居している、今注目したい企業をピックアップ。今回は「株式会社ストリ」をご紹介します。

お役立ち
2023.11.21
働き方改革に注力している企業ってどんなところ?|次世代ワークスタイル応援私募債「ミライへの路」
これから就職先を探している学生のみなさんにとって、どんな企業が自分にとって働きやすいのか、気になりますよね。そこで今回は、西日本シティ銀行が取り扱う次世代ワークスタイル応援私募債『ミライへの路*』を発行している企業のみなさんにご協力をいただき、その企業で実際に働いている若手の社員に直撃インタビュー。なぜ入社を決めたのか、実際に働いてみてどんな感じなのか、などをヒアリングしました。また、併せて、各企業の経営者にも、求める人材像や今後の展望などをお話しいただきました。取材に協力いただいた企業は、地元・福岡で働き方改革に注力している、優良企業ばかりです。ぜひ、就職希望先の候補の一つとして、働く先輩たちのリアルな声をご一読ください。

お役立ち
2025.07.18
【ミライへの路に挑む企業】地球を守り働く人の成長を支える環境調査会社|株式会社ENJEC
多様な生き方や働き方が広がりつつある現代。企業にはこれからますます、さまざまな人が働きやすい環境を整えることが求められます。社員の働きやすさを叶える企業の取り組みとは?この連載では、実際に働き方改革を積極的に取り組む企業で働く人や経営者にインタビュー。今回は、九州を中心に、水質、大気、土壌といった環境にまつわる調査・分析の事業を手がける、福岡市の株式会社ENJEC(エンジェック)に取材しました。

インタビュー
2025.06.11
質の高い人材紹介サービスで、企業も求職者も従業員も幸せに |株式会社GR8キャリア 小畑和貴さん
医療・福祉業界の人材紹介サービスをメインに事業展開する株式会社GR8(グレイト)キャリア。代表の小畑和貴さんは宮城県出身で福岡に移住し、住宅メーカーから人材紹介業界に転職したという異色のキャリアの持ち主です。創業から1年足らずでメンバーは20人ほどに増え、順調な滑り出しといえます。しかし、組織や利益の拡大は求めず、あくまでも「質の高いサービス提供」と「社員とその家族が笑顔で過ごせること」にこだわり続けたいという小畑さんに、その思いの根源や起業のストーリーを聞きました。

インタビュー
2025.06.02
番組・動画制作から拠点の運営まで、幅広い事業を展開|株式会社move on.e 岩谷直生さん
20歳から放送局の番組制作に関わり、個人事業主を経て、41歳で番組と動画制作を主軸にした株式会社move on.eを設立した岩谷直生さん。長年のディレクター経験を生かして、マスメディアの番組やイベントを手掛ける一方で、子どもに向けた全く新しい事業にも意欲的にチャレンジしています。

お役立ち
2025.11.25
【事業継続力強化計画認定制度】概要や認定のメリット、申請支援事業も紹介
近年、地震や台風などの自然災害、感染症の流行など、企業経営を取り巻くリスクが多様化しています。 こうした中で注目されているのが、災害や緊急事態に備えて事業を継続できる体制を整える「事業継続力強化計画(BCP)」です。 この計画の認定を受けることで、補助金申請時の加点や税制優遇など、さまざまなメリットがあります。 そこでこの記事では、事業継続力強化計画認定制度の概要や認定メリットに加えて、計画策定・申請を支援する取り組みについても解説します。

お役立ち
2025.11.25
【中小企業必見】最低賃金引上げに伴う負担軽減策とは?福岡県の支援策も紹介
令和7年度の最低賃金引上げにより、全国的に人件費の負担が増加しています。特に中小企業や小規模事業者にとっては、賃上げへの対応が経営上の大きな課題となっています。 こうした状況を受け、国や自治体では、最低賃金の引上げに伴う事業者の負担を軽減するため、各種支援策を打ち出しています。 この記事では、最低賃金引上げに対応するための国の主な支援策に加え、福岡県独自の支援制度について解説します。


