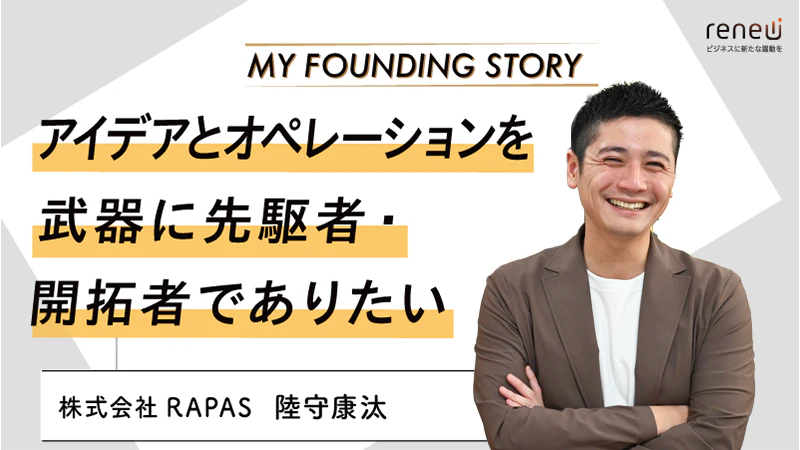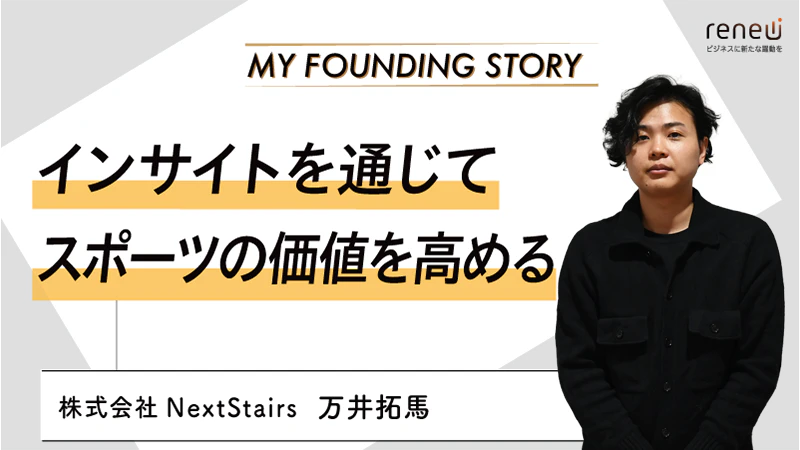DX(デジタルトランスフォーメーション)の成功事例9選!共通する特徴や必要性とは
By 森本 由紀
|デジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組む企業が増えています。DX対応の遅れは、企業にとって損失になる可能性があります。DXの必要性を理解した上で、失敗のないように進めましょう。本記事ではDXの成功事例から、成功のポイントについて説明します。
あわせて読みたい
DX(デジタルトランスフォーメーション)って?定義や考え方を分かりやすく説明
Amazonの電子書籍が読み放題!Kindle Unlimited
デジタルトランスフォーメーションの成功の定義とは

「デジタルトランスフォーメーション」という言葉は、近年になって頻繁に使われるようになりました。まずはデジタルトランスフォーメーションの意味や、成功の定義について説明します。
デジタルトランスフォーメーション(DX)の意味
デジタルトランスメーションは、DXという略称で呼ばれています。DXは欧米発の概念ですが、2010年(平成22年)代後半から日本においてもその重要性が叫ばれるようになりました。
デジタル技術を用いた変革
英語の「Transformation」には、変容や変革という意味があります。デジタルトランスフォーメーションは、デジタル技術を用いた変革のことです。IT化やデジタル化にとどまらない、抜本的な変革を表しています。
デジタル技術とは?
DXのために活用できるデジタル技術には、AI、5G、クラウド、IoT、VR/AR、3Dプリンタなどがあります。現代においては、あらゆるモノやコトをデジタル情報に置き換えて表現・伝達できるといっても過言ではありません。デジタル技術を使ってできることは無限大といえるのです。
日本は企業のDX対応を推進
DXは、一部の先進的な企業のみに関係があることではありません。すべての企業でDXが必要な時代になっています。
国はDXを推し進めている
日本政府は、企業のDX対応を推進しています。2018年(平成30年)9月には、経済産業省より「DXレポート~ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開~」(DXレポート)が出され、日本企業のDX対応の遅れが報告されました。同年12月には、「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」(DX推進ガイドライン)が発表され、各企業におけるDX対応の指針が示されました。
経済産業省のDXの定義
経済産業省はDXレポートの中で、「将来の成長、競争力強化のために、新たなデジタル技術を活用して新たなビジネス・モデルを創出・柔軟に改変するDXの必要性」に言及しています。つまり、日本では「新たなデジタル技術を活用して、新たなビジネスモデルを創出または既存のモデルを改変すること」がDXの意味と捉えられています。
DXはどんな場合に成功したといえる?
デジタルトランスフォーメーションは、単なるデジタル技術の導入ではなく、活用による変革です。では、どんな場合に変革を起こしたと言えるのでしょうか?DX成功の定義について考えてみましょう。
デジタル技術を応用したビジネスモデルの構築
デジタル技術を活用すれば、これまでとは全く違った新しい形のビジネスモデルの構築が可能になります。デジタル技術を使って、顧客に新しい価値を提供できるビジネスモデルが生まれたなら、DXは成功したといえるでしょう。
デジタル化による業務改革や組織改革
デジタル技術を使えば、これまで行っていた業務の一部を不要にしたり、組織や人事の体制を全く異なる形に変えたりすることも可能です。このような場合にも、DXの成果が出ていることになります。
既存のシステムからの脱却
多くの企業では、業務の一部や全部を古いシステムに依存しています。老朽化したシステムは、システムトラブルなどの問題が発生しがちです。デジタル技術の導入や新たなビジネスモデルの創出によって既存システムの問題を解消できたときに、DXは成功したといえます。
Amazonの電子書籍が読み放題!Kindle Unlimited
日本企業におけるデジタルトランスフォーメーションの課題と必要性

日本企業のDX対応の遅れに対し、経済産業省はDXレポートやDXガイドラインを出して警鐘を鳴らすほど危機感をあらわにしています。日本企業でDX推進が求められる理由についても確認しておきましょう。
既存システムが抱える問題は大きい
上でも少し触れましたが、日本企業の多くは老朽化したシステムを抱えています。このような老朽化したシステムは「レガシーシステム」と呼ばれます。レガシーシステムは複雑化・ブラックボックス化しているため、扱いにくいだけでなく、うまく機能しないこともあるのです。レガシーシステムを保有しているリスクには、次のような点が挙げられます。
データ活用ができない
レガシーシステムは、データの爆発的な増加に対応できません。企業においては、せっかく保有しているデータの活用ができないことになります。
業務基盤が維持・継承できない
古くなったシステムは、ITシステムの運用・保守の担い手が不在となり、多くの技術的負債を抱えるようになります。これにより、業務基盤そのものの維持・継承が困難になってしまうこともあります。
データ滅失・流出等のリスク
レガシーシステムは、サイバー攻撃や災害の際に、十分なセキュリティを発揮できません。データの滅失や流出のリスクも高くなってしまいます。
レガシーシステムを放置した場合の経済損失
レガシーシステムを保有していると、業務がスムーズに進まないだけでなく、メンテナンスやトラブル対応にリソースを割かれてしまいます。多くの企業がこのような既存システムを抱えているため、国家レベルで見ると巨額の経済損失になってしまうのです。
「2025年の崖」とは?
経済産業省のDXレポートでは、日本企業のDX遅れの現状を「2025年の崖」として危機感をあおっています。複雑化・老朽化・ブラックボックス化した既存システムが残存した場合、2025年(令和7年)までにIT人材の引退やサポート終了などによるリスクが予想され、それに伴う2025年(令和7年)以降の経済損失は最大12兆円/年と算出されています。
既に多額の経済損失が発生
レガシーシステムに起因するシステムトラブルがもたらした経済損失は、2014年(平成26年)時点でも約4兆円と算出されています。既に大きな損失が発生しており、2025年(令和7年)には約3倍の経済損失になると予測されています。
既存のシステムの脱却・更新が課題
経済産業省のDXレポートでは、DX実現シナリオとして「2025年までの間に、複雑化・ブラックボックス化した既存システムについて、廃棄や塩漬けにするもの等を仕分けしながら、必要なものについて刷新しつつ、DXを実現することにより、2030年実質GDP130兆円超の押上げを実現」するとしています。
企業がとるべき対策とは?
各企業においては、経済産業省のDXガイドラインにもとづきDXを推進していくことが必要になります。しかし、具体的に何をどうすればよいのかはわかりにくいでしょう。
以下、DXに成功した企業の事例を紹介します。DXのイメージを掴むうえで参考にしてください。
Amazonの電子書籍が読み放題!Kindle Unlimited
業界別・DXの成功事例9選

DXは、一部の業界でのみ有効な方法ではありません。あらゆる業界で、デジタル技術を用いたビジネスモデルの構築が可能です。業界別に成功事例を見てみましょう。
食品・飲食業界
株式会社グリーンハウス
「とんかつ新宿さぼてん」を運営する株式会社グリーンハウスでは、国内の一部店舗にAIカメラを導入し、画像解析により来店客やスタッフの「喜び」を数値化する取り組みを行っています。デジタルの力を借りて「喜びの見える化」を行うことにより、顧客の満足度や、スタッフのモチベーション向上に成功しました。
江崎グリコ株式会社
江崎グリコの法人ノベルティ部門では、商談化率向上のために、マーケティングオートメーションツールを導入しました。顧客に対する理解が深まり、購買タイミングに合わせた営業が可能になったことから大きな成果につながりました。
製造業界
ゼブラ株式会社
ゼブラでは、3Dプリンタを利用した試作品作りを行っています。試作品を外部委託する場合に比べて、費用を抑えながら納期を短縮できるようになり、コストの問題を解決できました。
大塚製薬株式会社
大塚製薬の医療関連事業分野では、脳梗塞再発抑制薬の服薬忘れを防止するための「プレタールアシストシステム」をNECと共同開発しました。服薬のタイミングで専用ケースのLEDが点滅する仕組みです。服薬状況は本人がスマホで確認できる以外に、家族や医師・薬剤師も確認できるようになっています。
建設業界
小松製作所
コマツでは、「KOMTRAX(コムトラックス)」という機械稼働管理システムを導入しています。最先端のICTを駆使したIoTで、顧客や代理店の現場、協力企業など生産現場の全体をつなぐことにより、全ての現場の安全と生産性の向上を図っています。
運輸業界
ANAホールディングス株式会社
ANAでは航空機利用者向けに、搭乗後も疲れを感じずに最大のパフォーマンスを発揮してもらうための「乗ると元気になるヒコーキ」プロジェクトを行っています。第一弾としてリリースされた時差ボケ調整アプリは、フライト情報や現地での予定を入力することにより、適切なタイミングで時差ボケ調整のアドバイスが受けられます。
日本交通株式会社
日本交通ではAI配車を導入し、過去の乗車履歴や現在開催中のイベント情報、気象情報、鉄道情報などを組み合わせ、乗車需要が多い場所を予測しています。これにより、タクシー車両の稼働率を上げることが可能になりました。
教育・サービス業界
株式会社トライグループ
家庭教師のトライでは、映像授業をオンライン上で無料配信し、質問箇所もオンラインで家庭教師が答えるサービスを業界で初めて行いました。生徒のライフスタイルに合わせ、いつでもどこでも受講可能なシステムとして注目を浴びました。
株式会社メルカリ
従来のネットオークションとは異なり、スマホ1つで完結する個人間取引を可能にし、多くの利用者を獲得したのがメルカリです。誰でも簡単に出品できる仕組みや匿名配送など、ユーザーの利便性を考えたサービスを展開しています。
成功するための4つのポイント

DXの成功について、事例からイメージしていただけたでしょうか?最後に、DXを成功に導くためのポイントを4つ挙げます。
1. 社内全体に理解を促す
DX推進のためには、社内全体の意識改革が必要です。経営トップがDXの必要性を認識していても、現場の責任者の理解が得られなければ思うように進みません。DXにより何ができるのか、どのような取り組みを行うのかを具体的に説明し、社内全体の意識を高めることが大切です。
トップは明確なビジョンを示す
DXを進めるときには、経営トップがリーダーシップを発揮して従業員に号令をかけなければなりません。DXによりどこを目指そうとしているのかを経営トップ自らが発信し、従業員のモチベーションを高めることが必要です。
2. 経営陣と現場との情報共有
DXについての戦略を考える経営陣と、現場でシステム面の実行をする従業員とが、スムーズに情報を共有できるようにしましょう。経営陣の理想と現場の状況が一致するとも限りません。意思疎通を密に行い、経営陣と現場とで意見のすり合わせを行うことが必要です。
DX推進部門の設置
DXを進めると決めたら体制整備が必要です。DX推進のための部門を設置し、経営陣と現場間の意見調整も行うようにしましょう。
3. 最適なIT人材の確保
DXを進めるためには、IT人材を確保する必要があります。自社の人材やノウハウだけでは、DXの成功には不十分なことがあるため、外部のサポートを受けることも検討しましょう。
DXのコンサルティングを受ける
DXに関するプロのコンサルティングを受けることには、さまざまなメリットがあります。外部のサポートを受ければ、他社の事例も知ることができるでしょう。最新のデジタル技術について情報を入手しながら、自社に合った方法の提案を受けられます。
4. 顧客中心主義で考える
従来のIT化は、業務の効率化やコスト削減といった企業側の利益を重視したものでした。DXを考える場合には、企業側の都合ではなく、顧客のニーズを第一に考えることが必要です。DXに成功している企業は、「顧客中心主義」という共通点があります。
顧客ニーズをみたすために何が最適か
デジタル技術の導入は、もはや当たり前になってきています。単なるデジタル化では、競争に勝ち残ることができません。企業においてDXを成功に導きたいなら、顧客の満足度を高めるためにデジタル技術を活用できないかという視点から考えてみましょう。
まとめ
DXを成功に導くには、社内の体制整備や適切な人材確保が必要になります。デジタルの力を利用し、今後の生き残りのために変革を起こしましょう。
西日本シティ銀行のデジタル支援チームでは、企業のDX推進サポートを行っています。DX対応でお悩みならば、ぜひご相談ください。
デジタル化するもの、しないもの。西日本シティ銀行のデジタル化支援の取組み
DX(デジタルトランスフォーメーション)って?定義や考え方を分かりやすく説明
- DX
Writer

森本 由紀
AFP(日本FP協会認定)、行政書士、夫婦カウンセラー
大学卒業後、複数の法律事務所に勤務。30代で結婚、出産した後、5年間の専業主婦経験を経て仕事復帰。現在はAFP、行政書士、夫婦カウンセラーとして活動中。夫婦問題に悩む幅広い世代の男女にカウンセリングを行っており、離婚を考える人には手続きのサポート、生活設計や子育てについてのアドバイス、自分らしい生き方を見つけるコーチングを行っている。
おすすめの記事

お役立ち
2025.02.06
対談記事【ビジネスのヒント】|斬新な新サービスを支えた企業と銀行の絆
経営に関する悩みや課題を抱える事業経営者の皆さまにとって、銀行の営業担当者は心強いサポーターの一人です。そこで、らいふくのーと編集部では、事業経営者と西日本シティ銀行の営業担当者にスポットをあててインタビュー。二人の出会いや、事業の成功までの道のりなどをざっくばらんにお話しいただきます。
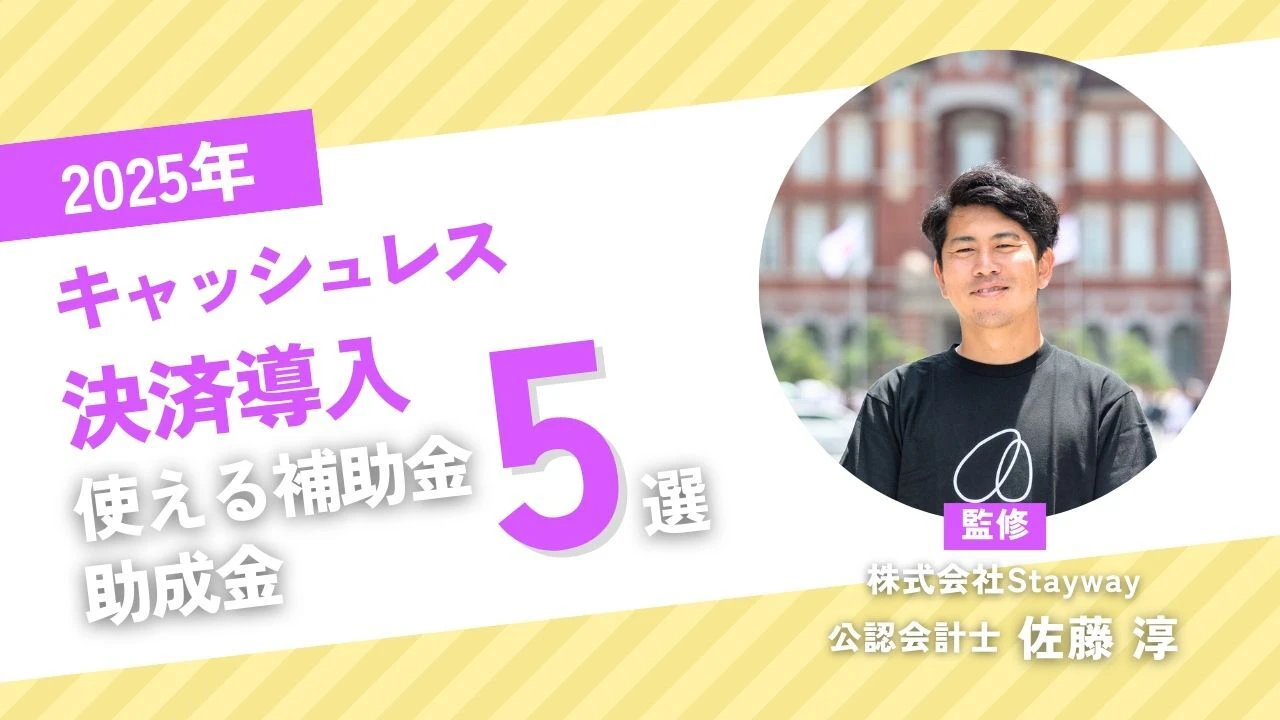
お役立ち
2025.03.05
【2025年】キャッシュレス決済導入に使える補助金・助成金5選
感染症対策やインバウンド対策等の一環としてキャッシュレス決済への需要が高まるなか、キャッシュレス決済の導入を検討しているものの、コストが気になるという事業者様は少なくないでしょう。 そこでこの記事では、キャッシュレス決済端末を導入する際に活用できる主な補助金や助成金を紹介します。 ※記事内容は、2025年3月3日時点の情報です。最新の情報は、必ず省庁や自治体の公式HPをご確認ください。

お役立ち
2025.03.04
IT導入補助金2025の変更点とは?拡充ポイントや制度概要を解説
事業者の業務効率化を支援する国の施策のひとつに「IT導入補助金」があります。 ITツールの導入を支援する制度で、これまで複数年にわたり公募を実施してきました。 さらに、令和6年(2024年)12月の令和6年度(2024年度)補正予算成立に伴い、今後の継続も決まっています。 そこでこの記事では、IT導入補助金2025で実施予定の拡充ポイントを交えて制度概要を解説します。 ※記事内容は、2025年2月3日時点の情報です。最新の情報は、必ず省庁や自治体の公式HPをご確認ください。

お役立ち
2023.11.21
働き方改革に注力している企業ってどんなところ?|次世代ワークスタイル応援私募債「ミライへの路」
これから就職先を探している学生のみなさんにとって、どんな企業が自分にとって働きやすいのか、気になりますよね。そこで今回は、西日本シティ銀行が取り扱う次世代ワークスタイル応援私募債『ミライへの路*』を発行している企業のみなさんにご協力をいただき、その企業で実際に働いている若手の社員に直撃インタビュー。なぜ入社を決めたのか、実際に働いてみてどんな感じなのか、などをヒアリングしました。また、併せて、各企業の経営者にも、求める人材像や今後の展望などをお話しいただきました。取材に協力いただいた企業は、地元・福岡で働き方改革に注力している、優良企業ばかりです。ぜひ、就職希望先の候補の一つとして、働く先輩たちのリアルな声をご一読ください。
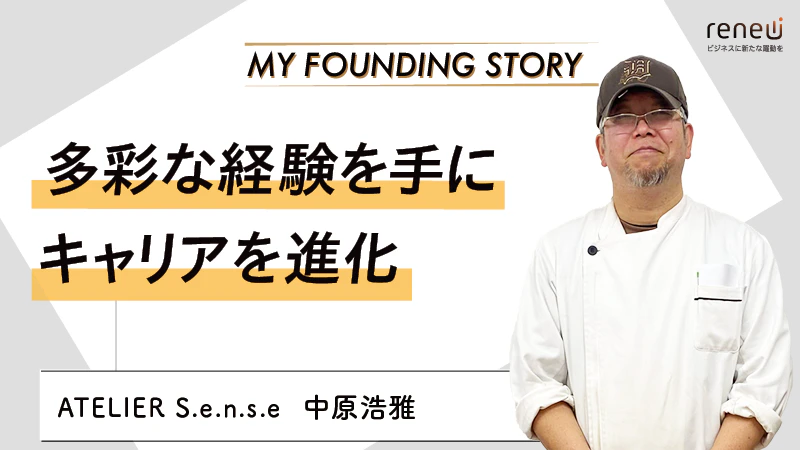
インタビュー
2025.03.07
お菓子製造のOEMで福岡の製菓業界に新境地を開く。ATELIER S.e.n.s.e 中原浩雅さん
他社ブランドの商品を生産する"OEM"。受託企業は商品の製造に、委託企業は商品開発やPRに集中できるというメリットがあり、アパレルや自動車などのさまざまな業種で活用されていますが、食品業界でもOEMの商品は多く見られます。今回はそんな食品の中でもお菓子(焼き菓子)のOEM製造を手がける、「ATELIER S.e.n.s.e(アトリエ・センス)」代表の中原浩雅さんにインタビュー。福岡ではまだ希少なお菓子のOEMという業種で起業した背景には、中原さんの多彩な経験が深く関わっていました。

お役立ち
2025.02.06
【ミライへの路に挑む企業】循環型の総合不動産企業として、社員もお客さまもハッピーに!|株式会社みらいコンシェルジュ
多様な生き方や働き方が広がりつつある現代。企業にはこれからますます、さまざまな人が働きやすい環境を整えることが求められます。社員の働きやすさを叶える企業の取り組みとは? この連載では、実際に働き方改革を積極的に取り組む企業で働く人や経営者にインタビュー。今回は熊本を基盤に不動産売買やファイナンシャルプランニング、保険の見直しなどの幅広い事業を展開する「CRAS(クラス)」を運営する「株式会社みらいコンシェルジュ」にお話を伺いました。