起業資金っていくら必要?気になる資金調達方法から費用の目安について

起業にはお金が必要であり、自己資金だけでまかなえない場合は、何らかの方法で調達しなければなりません。そもそも、いくらかかるのかも気になるところでしょう。今回は、起業にかかる費用の目安とその調達方法について解説します。
起業(開業)資金はいくら必要?
起業(開業)にかかる資金は個人事業なのか会社(法人)を設立するのかだけでなく、業種・業態によっても大きく変わってきます。
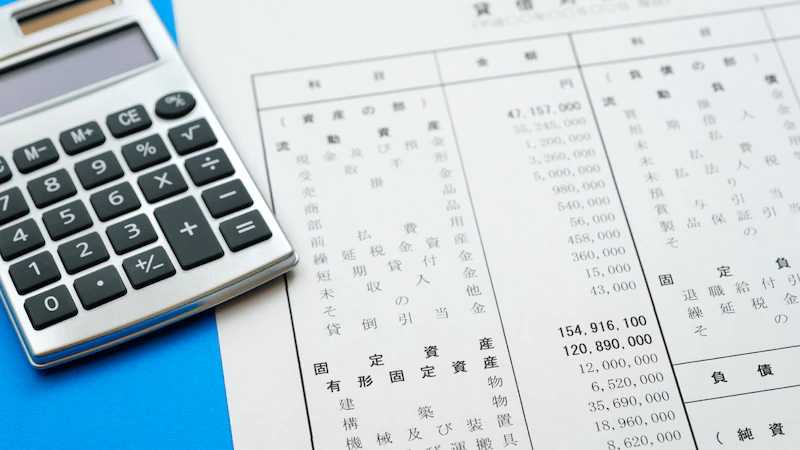
個人事業を始める際の手続きにかかるお金
自営業やフリーランスとして行う個人事業であれば、開業に必要な手続きは「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」の提出だけです。開業届は用紙1枚の簡単なもので、自身で作成すれば費用はかかりません。
会社(法人)の設立手続きにかかるお金
会社(法人)を設立するには、定款の作成・認証と登記が必要です。最低限必要な法定費用として、株式会社を設立する場合で約20〜25万円、合同会社では約6〜10万円かかります。これに加え、会社代表者印の作成費用などに1万円程度、司法書士などに手続きを依頼すれば10万円程度の報酬が必要になります。
株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
定款認証手数料 | 3〜5万円*(1) | 不要 |
謄本手数料 | 2,000円程度 | 不要 |
定款印紙代 | 4万円 (電子定款の場合は不要) | 4万円 (電子定款の場合は不要) |
登録免許税(設立登記) | 15万円〜*(2) | 6万円〜*(3) |
代表者印作成費用等 | 1万円程度 | 1万円程度 |
司法書士等報酬 | 7〜15万円程度 | 6〜12万円程度 |
*(1)資本金額により変動
*(2)15万円または資本金の額の0.7%のいずれか高い額
*(3)6万円または資本金の額の0.7%のいずれか高い額
資本金は返済不要の資金で準備しなければならない
会社を設立する場合は「資本金」も必要です。資本金には、自己資金や第三者からの出資など、返済義務のない資金を充てるのが原則です。金融機関からの借り入れなどを資本金とすることは、基本的に認められません。
2006年(平成18年)の会社法改正により、資本金1円以上で会社を設立できるようになったため、実際には資本金がなくても会社の設立自体は可能です(最低資本金の規定がある業種を除く)。
とはいえ、資本金は会社が事業を営んでいくための元手となるお金です。あまりに少ないと会社の信用にもかかわり、融資を受けにくくなったり取引先が限られてしまったりするおそれがあります。長期的に事業を継続・拡大していくのであれば、ある程度の資本金は準備すべきでしょう。
適正な資本金の額はビジネスモデルにもよりますが、初期費用に3〜6カ月程度の運転資金を加えた金額がひとつの目安です。
初期投資にかかるお金(初期費用)
開業にあたっては事業に必要な物品の購入費用や設備投資費用、店舗やオフィスを構える場合は内外装費や保証金(敷金)、前払賃料などの初期費用がかかります。
自宅開業などでほとんどかからないケースから、数千万円〜1億円以上かかるケースまで、初期費用は大きな差がつく部分です。
運転資金として準備するお金
黒字が見込めるまでの赤字を補てんできる程度の運転資金は、準備しておきましょう。事業を行うには、家賃や水道光熱費、商品の仕入れ代金、従業員の人件費などの経費がかかります。売上が経費を上回れば利益が出ますが、開業当初は赤字となるケースも少なくありません。事業が軌道に乗る前に資金が足りなくなれば、せっかく立ち上げても継続できなくなってしまいます。
自身の当面の生活に必要なお金
収入がなくても半年から1年程度は生活できるお金を、事業資金とは別に確保しておきましょう。起業後の収入は事業の利益によって大きく左右され、不安定になりがちです。手元資金をすべて起業に充ててしまうと、赤字になったときに生活できなくなるおそれがあります。
事業の内容にもよりますが、安定した収入を得られる仕事を続けながら、副業(複業)として開業するのもひとつの方法です。
【事業業種別】起業する際に必要な費用の目安

起業に必要な費用は、その業種によっても大きく違います。
下表は業種ごとに起業に必要な費用の目安を示したものです。実際にかかる費用は具体的な事業内容や規模によって変わりますが、金額のイメージを掴むための参考にしてください。
業種 | 起業に必要な費用の目安 | 業種 |
|---|---|---|
歯科医院 | 2,000万円〜1億8,000万円 | 歯科医院 |
医院・クリニック | 1,000万円〜1億5,000万円 | 医院・クリニック |
美容室 | 500万円〜3,000万円 | 美容室 |
居酒屋 | 600万円〜2,500万円 | 居酒屋 |
カフェ | 100万円〜1,500万円 | カフェ |
学習塾 | 100万円〜1,000万円 | 学習塾 |
小売店 | 50万円〜500万円 | 小売店 |
士業事務所 | 50万円〜500万円 | 士業事務所 |
飲食店や美容院、クリニックなどは内外装費や設備投資などにお金がかかり、起業に必要な費用もかさみがちです。退去したテナントの内装や設備機器などをそのまま利用できる「居抜き物件」を借りたり、中古やリースなどを利用したりといった工夫で、費用は大きく変わります。
士業事務所やネット販売事業、プログラマー・デザイナー・ライターなど、自宅でも開業できる業種・業態なら、ほとんどお金をかけずに起業することも可能です。
500万円未満での起業(開業)が最も多い
日本政策金融公庫が実施した「2020年度新規開業実態調査」によると、500万円未満で開業する人が43.7%と最も多くなっています。次に多いのが500万円以上1,000万円未満の27.3%で、約7割の人が起業資金1,000万円未満で開業しています。
起業資金(開業費用)の平均値は989万円、中央値は560万円です。いずれも1991年(平成3年)の調査開始以来最低となっており、年々減少しています。要因としては、初期投資や運転資金があまりかからないインターネットを利用した起業の増加などが考えられます。
知っておきたい6つの資金調達方法

起業に必要な資金の調達方法は、主に次の6つです。
それぞれの資金調達方法について、より詳しくみていきましょう。
(1)自己資金
起業資金のベースとなるのは「自己資金」です。手元にある資金だけで起業できれば、資金調達の必要はありません。資金を借り入れた場合の金利負担や返済義務、出資を募った場合の利益分配や経営への介入といった心配も不要です。
しかし、自己資金だけですべての起業資金をまかなえる人は多くありません。日本政策金融公庫が実施した「2020年度新規開業実態調査」によると、開業時の資金調達額の平均は1,194万円です。そのうち自己資金の平均は266万円で、平均調達額の占める割合は22.2%となっています。
では、自己資金はいくら準備すればいいのでしょうか。個別の状況によるため一概にはいえませんが、起業資金全体の2〜3割程度がひとつの目安になります。金融機関等から融資を受けるにしても、自己資金は多いほうが有利です。
(2)国や自治体からの補助金・助成金
国や自治体ではさまざまな起業(創業)支援事業を行なっており、条件を満たせば補助金や助成金をもらえる可能性があります。
補助金や助成金は「もらえるお金」であり、利用しない手はありません。ただし、申請には手間がかかり、審査に通らなければなりません。また、支払った費用の一部が後払いで支給される仕組みなので、まずは自分でお金を準備しなければなりません。
最初から補助金・助成金を当てにするのではなく、他の資金調達方法と並行して申請をしておき、もらえればラッキーというくらいの気持ちで臨みましょう。国や自治体が実施している補助金や助成金の情報は、下記サイトから検索できます。
補助金・助成金・融資の検索(中小企業基盤整備機構・J-Net21)
(3)親族・知人等からの借り入れ
金融機関からの借り入れのような審査はなく、条件も自由に決められるため、利用しやすい点がメリットです。
一方で、お金が絡めば親族や知人でもトラブルに発展するリスクがあります。事業が失敗して返済できなくなれば、親族や知人との関係まで悪化しかねません。選択肢のひとつではありますが安易に頼らず、慎重な判断が必要です。
(4)投資家等からの出資
資金を提供してもらい、代わりに利益の配当を受けたり経営に参加する権利を与えたりする方法です。借り入れとは異なり、提供された資金を返済する必要はありません。
将来性や成長性のある事業であれば、投資家やベンチャーキャピタルなどから多額の出資を得て、事業を一気に拡大することも可能です。
ただし、出資者は会社の経営に対して影響力を持つようになるため、意見が対立してトラブルに発展するリスクには注意が必要です。
(5)民間金融機関からの融資
資金調達で最も一般的に利用される方法です。親族・知人からの借り入れのように人間関係でトラブルが生じたり、出資者から経営に介入を受けたりする心配がありません。ただし融資には審査があります。開業当初からある程度の売上・利益が見込める事業であれば、信用保証協会の保証などを利用して融資を受けられる可能性があります。
ベンチャーやスタートアップのように、開発先行型で創業から当面の間は赤字が続くビジネスモデルでは、金融機関から融資を受けるのは難しいケースもあります。将来性があり、成長期待の高いビジネスモデルであれば、ベンチャーキャピタルなどからの融資・出資がおすすめです。国や自治体が実施しているこのほかの創業融資制度の情報は、下記サイトから検索できます。
補助金・助成金・融資の検索(中小企業基盤整備機構・J-Net21)
(6)国からの創業融資
国が行う創業融資は起業支援が目的であり、これから起業しようという人も融資を受けやすいのが特徴です。
代表的な創業融資制度としては、政府系金融機関である日本政策金融公庫が取り扱う「新規開業資金」や「女性、若者/シニア起業家支援資金」、「新創業融資制度」などがあります。
日本政策金融公庫では、技術やノウハウなどに新規性があり、地域経済の活性化につながる事業を支援する「挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)」など、上記以外にもさまざまな創業融資を実施しています。これから起業しようとする人にとって強い味方といえるでしょう。
よろず支援拠点などを活用するのも一手です。地域の他の支援機関等とも連携しながら、中小企業・小規模事業者が抱える売上拡大や経営改善等に関する様々な経営相談に対応するワンストップで相談に乗ってくれます。
※よろず支援拠点は、多様な分野に精通した専門家が経営上の悩みに親身に耳を傾け、抱えている悩みの本質的な課題を明確化するとともに、適切な解決策をご提案してくれる拠点です。福岡県よろず支援拠点、東京都よろず支援拠点、大阪府よろず支援拠点など全国各地に存在します。
※西日本シティ銀行でも、創業時に必要なご資金から、創業後の運転資金にご対応する融資商品やリース商品を取り揃えています。「創業関連制度融資のご案内」では創業期のお客さまが利用可能な融資制度についての情報を展開しています。また、「NCB操業応援サロン」ではリアル拠点で創業周りのご相談に応じています。
自分に合った資金調達をしよう

起業を成功させるには、自分に合った資金調達方法の選択が欠かせません。それぞれの方法のメリット・デメリットをまとめましたので、比較検討に活用ください。
資金調達方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
自己資金 | ・自由に使える ・金利負担や返済義務がない | ・資金力に限界がある ・準備に時間がかかる |
国や自治体からの補助金・助成金 | ・返済義務がない | ・申請手続きに手間がかかる ・要件が厳しい ・後払いのため自己資金の準備が必要 ・すぐに受け取れない |
親族・知人等からの借り入れ | ・審査が不要 ・借入条件を自由に決められる | ・金利負担や返済義務がある ・人間関係が悪化するリスクがある |
投資家等からの出資 | ・返済義務がない ・多額の資金調達も可能 | ・利益を分配しなければならない ・経営に介入されるおそれがある |
民間金融機関からの融資 | ・人間関係のトラブルや経営への介入などの心配がない | ・金利負担や返済義務がある ・担保や保証人が必要 |
国や自治体からの創業融資 | ・融資までの機関が短い | ・金利負担や返済義務がある |
まとめ
起業にかかる費用は業種や業態、事業内容、規模によって大きく異なります。自己資金だけでは資金が不足する場合には、自分に合った方法を選んで調達しなければなりません。
西日本シティ銀行の「NCB創業応援サロン」では、資金調達に欠かせない創業計画書の作成から融資の組み立てまで、起業(創業)資金の調達に関するさまざまな相談を承っています。これから起業を考えている方は、ぜひ一度相談ください。
▶︎創業応援サロン詳細は以下の画像をクリック↓↓
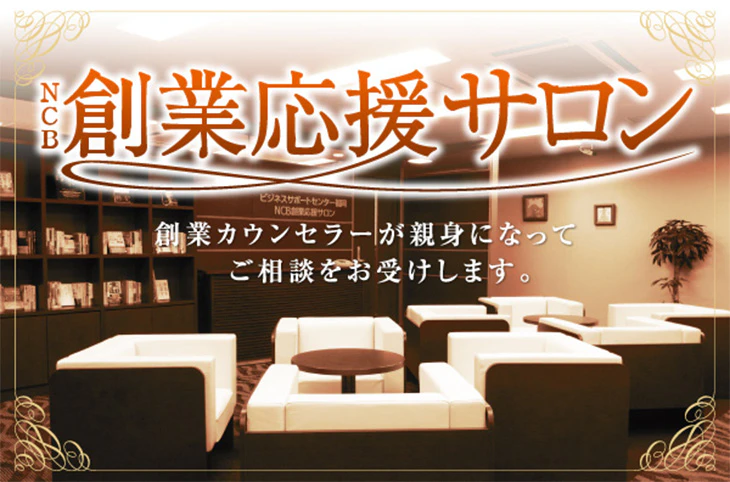
- 資金調達
Writer

RAPPORT Consulting Office代表、1級FP技能士、CFP(R)、証券外務員一種
証券会社・生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。お金に関するコンサルティング業務や執筆業務などを行う。ミニマリズムとマネープランニングを融合したシンプルで豊かな暮らしを提案している。
このライターの記事を読む >おすすめの記事

対談記事【ビジネスのヒント】|接骨院から建設業へ。驚きの経歴と経緯
経営に関する悩みや課題を抱える事業経営者の皆さまにとって、銀行の営業担当者は心強いサポーターの一人です。そこで、リニュー編集部では、事業経営者と西日本シティ銀行の営業担当者にスポットをあててインタビュー。サポートのきっかけや、事業の成功までの道のりなどをざっくばらんにお話しいただきます。

【今月のZero-Ten Park】株式会社ストリ|心と体に美しさと健やかさを
福岡を中心に世界5カ国15拠点を展開するシェアオフィス&コワーキングスペース「Zero-Ten Park」。そこに入居している、今注目したい企業をピックアップ。今回は「株式会社ストリ」をご紹介します。

働き方改革に注力している企業ってどんなところ?|次世代ワークスタイル応援私募債「ミライへの路」
これから就職先を探している学生のみなさんにとって、どんな企業が自分にとって働きやすいのか、気になりますよね。そこで今回は、西日本シティ銀行が取り扱う次世代ワークスタイル応援私募債『ミライへの路*』を発行している企業のみなさんにご協力をいただき、その企業で実際に働いている若手の社員に直撃インタビュー。なぜ入社を決めたのか、実際に働いてみてどんな感じなのか、などをヒアリングしました。また、併せて、各企業の経営者にも、求める人材像や今後の展望などをお話しいただきました。取材に協力いただいた企業は、地元・福岡で働き方改革に注力している、優良企業ばかりです。ぜひ、就職希望先の候補の一つとして、働く先輩たちのリアルな声をご一読ください。

【ミライへの路に挑む企業】地球を守り働く人の成長を支える環境調査会社|株式会社ENJEC
多様な生き方や働き方が広がりつつある現代。企業にはこれからますます、さまざまな人が働きやすい環境を整えることが求められます。社員の働きやすさを叶える企業の取り組みとは?この連載では、実際に働き方改革を積極的に取り組む企業で働く人や経営者にインタビュー。今回は、九州を中心に、水質、大気、土壌といった環境にまつわる調査・分析の事業を手がける、福岡市の株式会社ENJEC(エンジェック)に取材しました。

質の高い人材紹介サービスで、企業も求職者も従業員も幸せに |株式会社GR8キャリア 小畑和貴さん
医療・福祉業界の人材紹介サービスをメインに事業展開する株式会社GR8(グレイト)キャリア。代表の小畑和貴さんは宮城県出身で福岡に移住し、住宅メーカーから人材紹介業界に転職したという異色のキャリアの持ち主です。創業から1年足らずでメンバーは20人ほどに増え、順調な滑り出しといえます。しかし、組織や利益の拡大は求めず、あくまでも「質の高いサービス提供」と「社員とその家族が笑顔で過ごせること」にこだわり続けたいという小畑さんに、その思いの根源や起業のストーリーを聞きました。

番組・動画制作から拠点の運営まで、幅広い事業を展開|株式会社move on.e 岩谷直生さん
20歳から放送局の番組制作に関わり、個人事業主を経て、41歳で番組と動画制作を主軸にした株式会社move on.eを設立した岩谷直生さん。長年のディレクター経験を生かして、マスメディアの番組やイベントを手掛ける一方で、子どもに向けた全く新しい事業にも意欲的にチャレンジしています。

【事業継続力強化計画認定制度】概要や認定のメリット、申請支援事業も紹介
近年、地震や台風などの自然災害、感染症の流行など、企業経営を取り巻くリスクが多様化しています。 こうした中で注目されているのが、災害や緊急事態に備えて事業を継続できる体制を整える「事業継続力強化計画(BCP)」です。 この計画の認定を受けることで、補助金申請時の加点や税制優遇など、さまざまなメリットがあります。 そこでこの記事では、事業継続力強化計画認定制度の概要や認定メリットに加えて、計画策定・申請を支援する取り組みについても解説します。

【中小企業必見】最低賃金引上げに伴う負担軽減策とは?福岡県の支援策も紹介
令和7年度の最低賃金引上げにより、全国的に人件費の負担が増加しています。特に中小企業や小規模事業者にとっては、賃上げへの対応が経営上の大きな課題となっています。 こうした状況を受け、国や自治体では、最低賃金の引上げに伴う事業者の負担を軽減するため、各種支援策を打ち出しています。 この記事では、最低賃金引上げに対応するための国の主な支援策に加え、福岡県独自の支援制度について解説します。


