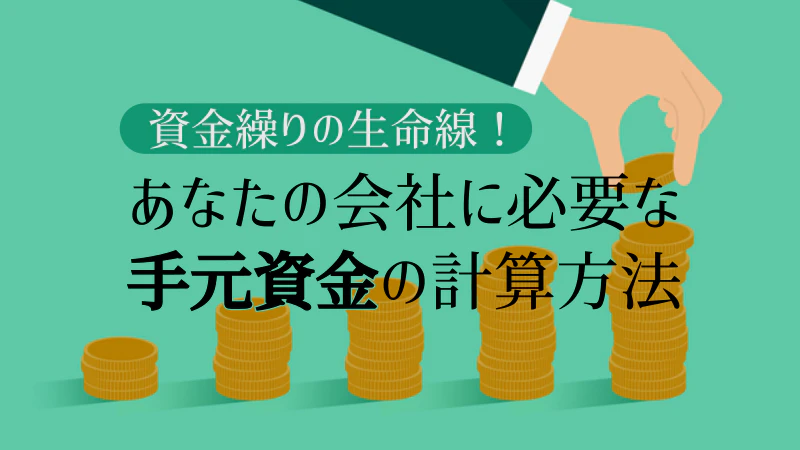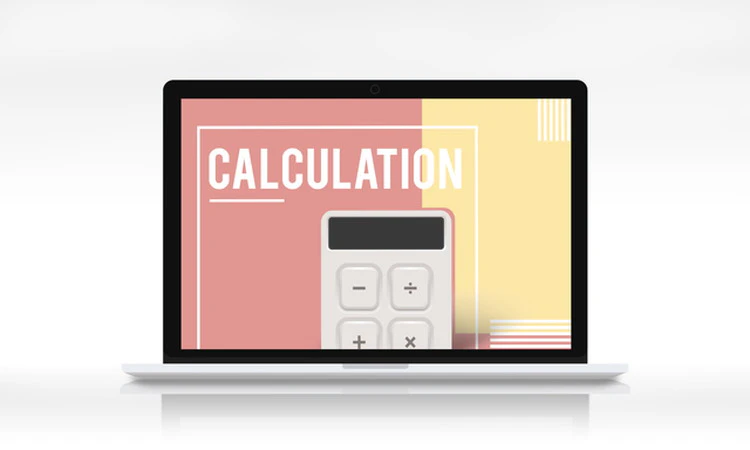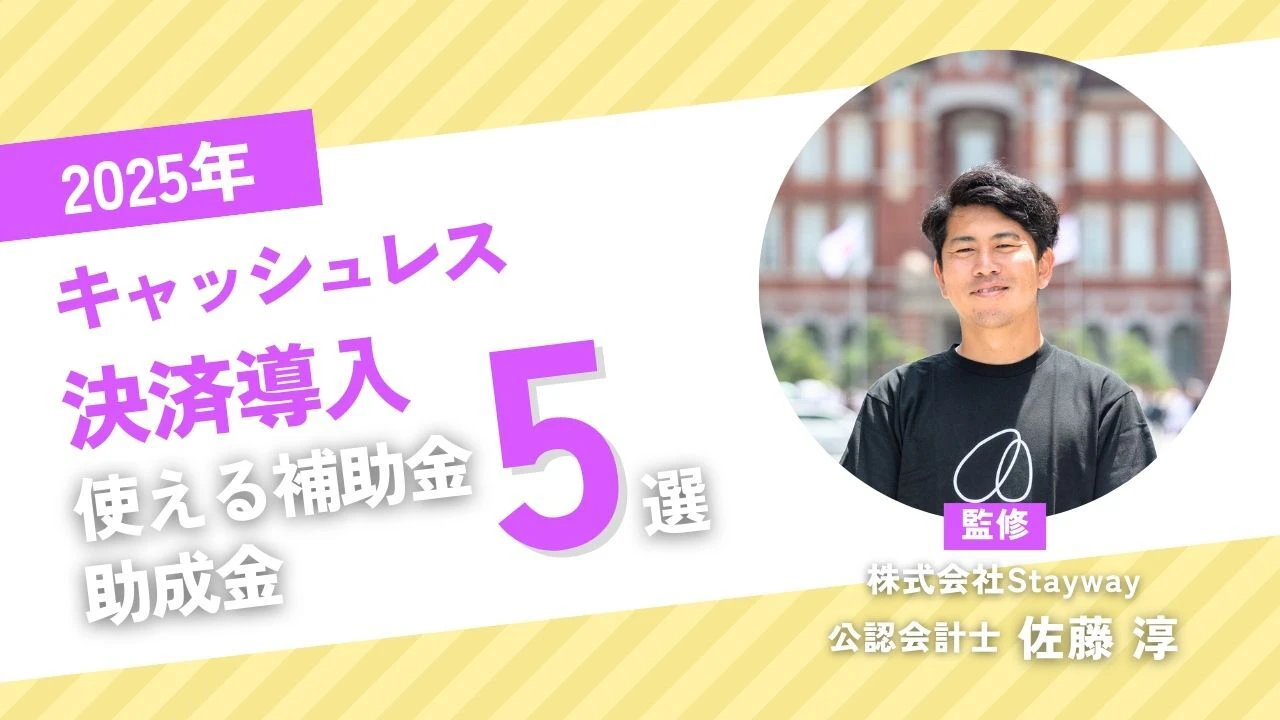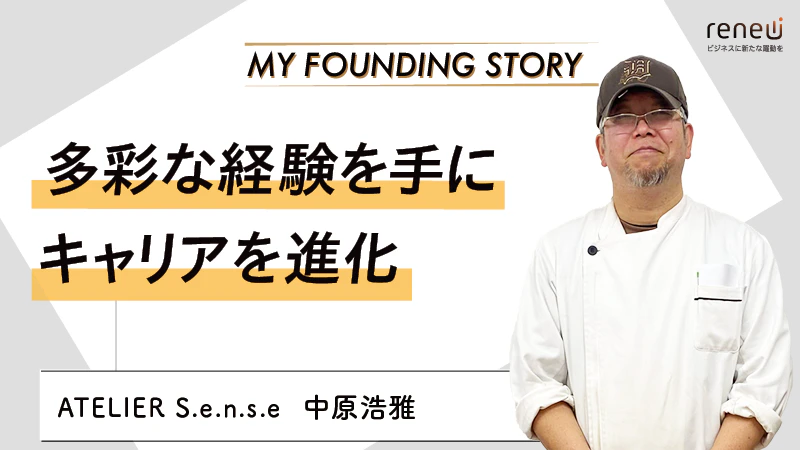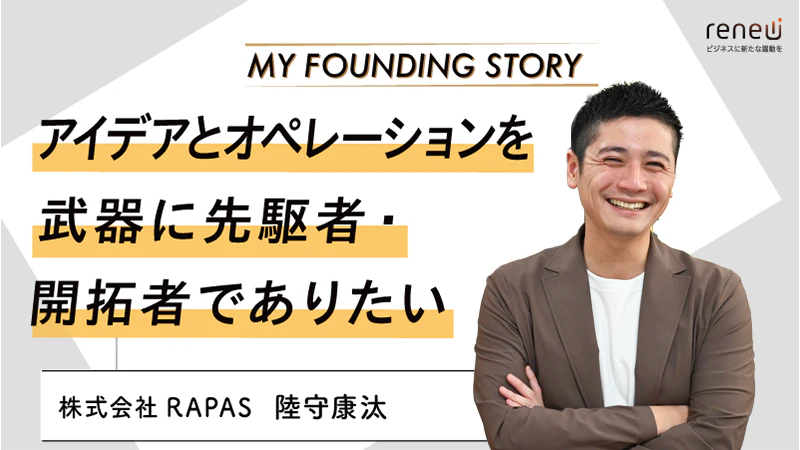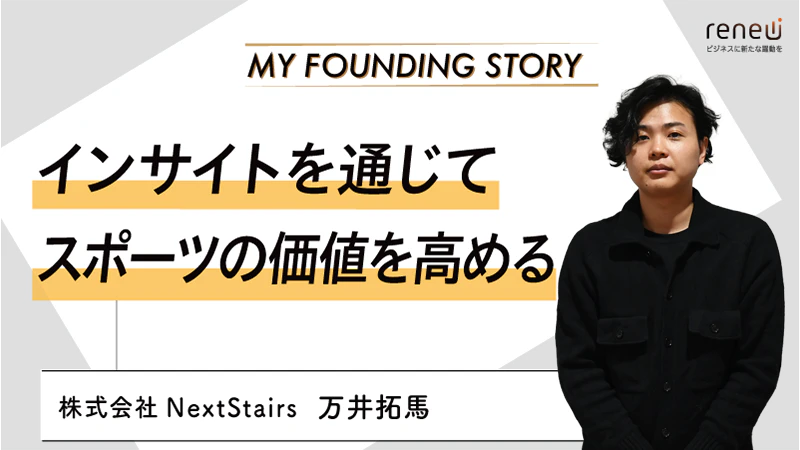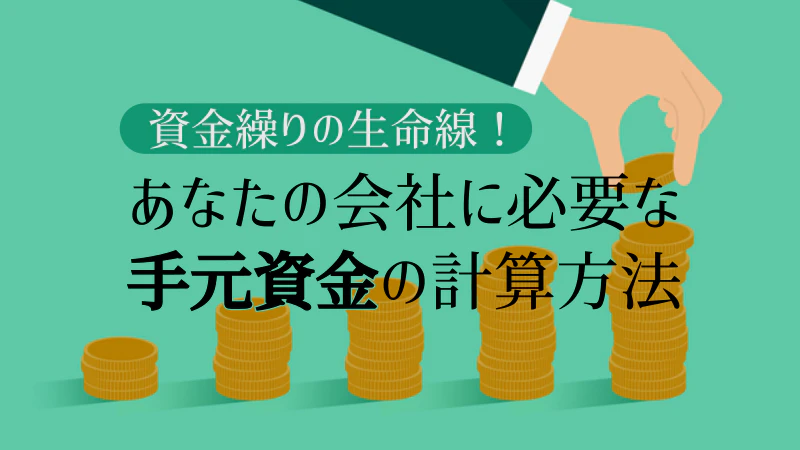
「会社の手元資金は、どれくらい用意しておけばいいのか」と悩んでいる経営者は多いのではないでしょうか。多すぎると無駄な支出につながりやすく、少ないといざというときの資金繰りが心配になるでしょう。今回は、会社経営の手元資金の目安について、その考え方を解説していきます。
手元資金とは?
手元資金とは、経費や税金などを支払った後、手元に残る現金や普通預金残高のことをいいます。突発的な支払いに備えて、いつでも使用できる流動性の高い資金のことです。
中小企業にとって手元資金は生命線
お金が無くなれば、会社は倒産してしまうでしょう。したがって、手元資金がいくらあるかということは、会社にとってまさに生命線といえます。
毎月の支払いに苦しんでいる会社であれば、資金繰りは重要な課題となります。また、今のところはそれほど資金繰りに困っていない会社でも、急激に景気が悪化することがあるため、手元資金を決して軽視はできません。
では、手元資金として最低どれくらい用意しておけばよいのでしょうか。
会社に必要な手元資金の計算方法と目安
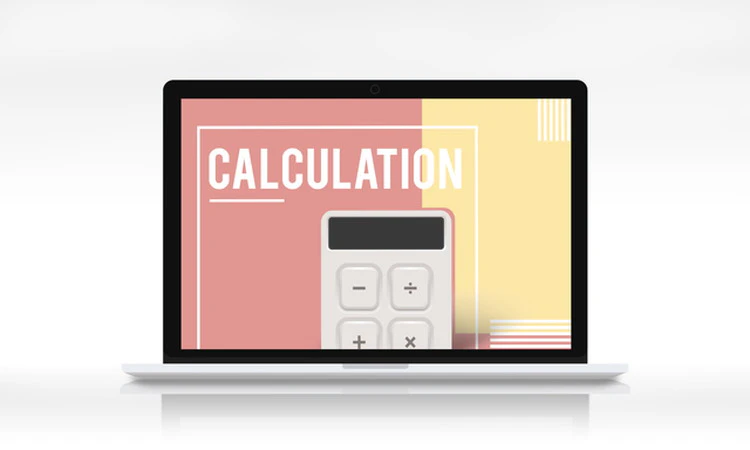
(1)売上高を基準として計算する方法
維持しておきたい手元資金の目安について、おおよそ「平均月間売上の何か月分」という言い方をする場合があります。しかし、さまざまな業種やビジネスモデルの違いがあるなか、単純に平均月売上(年間売上高÷12)を目安にするのは、適切な方法とはいえないでしょう。
売上高に基づく計算は目安とはならない
たとえば、利益が同じ程度であっても、卸売業と小売業では売上高の規模が違います。一般的に、卸売業は利益率が低いケースが多い一方、売上高は大きくなる傾向にあります。したがって、売上高をベースに手元資金を計算すると、多額に計算されてしまうのです。これでは、維持すべき手元資金の目安とはなりません。
(2)利益を基準として計算する方法
では、利益額を基準として計算する方法はどうでしょうか。「売上高」ではなく、「利益」を基準に手元資金の目安とすれば、業種の違いによる売上規模の大小に左右されず、自社にとって適正な手元資金の目安を測ることができます。
計算に用いるのは「限界利益」
ただし、ひとことで利益といっても、売上総利益や営業利益、経常利益など複数の考え方があります。ここで、手元資金の目安を計算する際に適正な利益額は、「限界利益」のことを指すと考えてください。月平均の限界利益の計算方法は以下のようになります。
限界利益 = 売上高 - 変動費
月平均限界利益 = 年間の限界利益 ÷ 12
限界利益・変動費の意味と定義

ここで、限界利益と変動費について解説します。
(1)限界利益の意味・定義
限界利益の計算式
限界利益の計算式は以下のとおり、売上高から変動費のみを差し引いたものをいいます。したがって、限界利益を計算するためには、売上にかかった費用を変動費と固定費に分けなければなりません。
限界利益 = 売上高 - 変動費
営業利益の計算式
それに対して、一般的に会計上でいわれる営業利益は、売上高から変動費だけでなく固定費も差し引いたものです。
営業利益 = 売上高 -(変動費 + 固定費)
限界利益と営業利益の違い
限界利益と営業利益との違いは、売上高から差し引くのが、変動費のみか、変動費と固定費を両方差し引くのかという点にあります。
営業利益は、外部に報告することを目的としていますが、限界利益は自社の経営判断を行う際に使用する管理会計上の指標だと考えるとよいでしょう。
(2)変動費・固定費の意味と内容
変動費と固定費の意味や具体的な項目は以下のとおりです。
変動費
変動費は売上を上げるためにかかった費用をいいます。具体的には原材料費や商品仕入高、販売手数料、外注加工費などがあります。変動費は、売上の増減にともない増減するという性質があります。
固定費
固定費は売上の増減にかかわらず、常に一定金額が発生する費用をいい、会社を維持するために必要な費用です。具体的には人件費や事務所家賃、水道光熱費、諸会費などがあります。
管理会計は会社が自社を分析するために行うものなので、特に基準が定められているわけではありません。したがって、変動費と固定費の分け方は、会社によっても異なるでしょう。
売り上げがなくても固定費はかかる
事業が軌道に乗り、順調に利益を上げていたとしても、たとえばリーマンショックのような世界規模の金融危機や、大規模な自然災害などの予期せぬ事態により、急激に経済がストップすることもあります。
このような場合、売上は上がらなくなると考えられるでしょう。売上がなければ変動費はかかりませんが、社員の給料や事務所の家賃など固定費の支払いはしなければなりません。したがって、売上がなくなる場合を想定し、固定費支払いのためにいくらか手元資金を用意しておく必要があるといえます。
最低限必要な手元資金の算出方法

金融機関からの融資には時間がかかる
では、実際にいくらの手元資金を用意しておけばいいのでしょうか。経済がストップし、事業の売上が上がらなくなった場合、銀行などの金融機関に融資を申し込むことが考えられます。
すぐにお金を借りられれば問題ありませんが、たくさんの会社が融資の申し込みをするため、お金を借りられるのは申し込みから1か月~2か月かかる可能性があります。
最低限必要な手元資金は平均限界利益の3か月分
だとすると、この期間は手元資金で会社を回さなければなりません。つまり、最低でも3か月は、売り上げがなくとも固定費の支払いができる程度の手元資金が必要といえるでしょう。これにより、最低限必要な手元資金は、「平均限界利益の3か月分」と考えることができます。
計算式
年間の限界利益 = 年間売上高 – 年間変動費
最低限必要な手元資金 = 年間の限界利益 × 3/12
上記算式で計算された金額は、仮に売上高がゼロであっても、3か月間は固定費の支払いが可能な手元資金を表しています。
これくらいの手元資金があれば、突然の危機が生じても、資金繰りに走り回る必要はないといえるでしょう。
手元資金を確保するためにやるべきこと
それでは、どのようにして手元資金を増やせばよいのでしょうか。手元資金を増やすためには以下のことが考えられます。
(1)利益を上げること
まずは事業で利益を上げることが挙げられます。より多くの利益を出すことができれば、手元資金を確保しやすくなるでしょう。
(2)お金が増えない原因を知ること
お金が増えない原因を分析し、それを解消しなければ、利益を上げたところで手元資金は残りません。手元資金が残らない原因は、以下のようなケースが考えられます。
①売掛金と買掛金の支払いサイトの問題
売掛金の回収より買掛金の支払いのほうが先ならば、売上が伸びていっても手元資金は減っていきます。売掛金と買掛金のサイトバランスを見直しましょう。
②在庫が多い
売上増加にともない在庫は増加する傾向にありますが、在庫が増加すれば保管するための費用がかかり、手元資金が減少していきます。適正在庫量を常に意識し、在庫縮小を検討しましょう。
③銀行借入金の返済額が多い
いくら利益を確保できたとしても、銀行借入金の返済額の方が大きければ、手元資金は減っていきます。返済計画の見直しや借換えなど、何らかの対応が必要な場合もあることを認識しましょう。
(3)銀行融資を受ける
手元資金が足りないと感じるなら、銀行から借り入れることも検討しましょう。目安は、最低でも「月平均限界利益の3か月分」です。
ここで借りたお金は手元資金を厚くするためのものですから、借金は増えますが手元資金も増えます。利息はかかりますが、返そうと思えばいつでも返せるお金といえます。
あるいは、事業拡大のための設備投資も可能となります。事業が順調なときこそ、銀行をうまく活用しましょう。
「資金繰り表」を作成するメリット

資金繰り表の役割
手元資金を考えるうえで重要なことは、資金繰りの管理を徹底することです。例えば、手元資金が減ってきた場合は、すぐに原因を特定し対処しなければなりません。そのために「資金繰り表」の作成は必須といえます。
手元資金をコントロールできる
資金繰り管理を徹底している会社は、銀行との融資交渉をいち早く行うことができ、手元資金をコントロールできます。多少の不況でも難なく乗り越えることができるといえるでしょう。さらに資金繰り管理を徹底していれば、設備投資をして事業拡大につなげることも可能です。「資金繰り表」を作成し、資金繰り管理を徹底しましょう。
まとめ
今回は、会社経営の手元資金はいくら必要かについて解説しました。手元資金は会社にとっての生命線であり、最低限必要な手元資金は平均限界利益の3か月分と考えられます。
手元資金がなければ倒産してしまう可能性がありますが、反対に手元資金をしっかりとコントロールできていれば、資金繰りに困らない強固な経営基盤を実現できるでしょう。
大手監査法人に勤務した後、会計コンサルティング会社を経て、税理士として独立。中小企業、個人事業主を会計、税務の面から支援している。独立後8年間の実績は、法人税申告実績約300件、個人所得税申告実績約600件、相続税申告実績約50件。