飲食店開業時のポイントとは?独立前に知っておきたい創業の基礎知識
飲食店に勤務している人の中には、「いつかは自分のお店を持って独立したい」と考えている人も多いのではないでしょうか。飲食店を創業したいと考えているようでしたら、計画的に準備を進めることが肝心です。
本記事では、飲食店開業の流れから、開業する前に知っておきたい基礎知識を5つのポイントに分けて説明します。創業に向けて何をすべきか理解するサポートとなれば幸いです。

目次
飲食店を開業する方法と経営に必要な許可等
飲食店を開業するまでにはいろいろな準備が必要です。開業までの大まかな流れと、飲食店経営に必要な許可や資格を知っておきましょう。
開業までの流れ
飲食店のオープンまでは、一般に、次のような流れになります。
コンセプトを考える
料理のジャンル、どういう雰囲気のお店にするのか、主な客層などのコンセプトを考えます。
物件探しをする
立地条件が良く、コンセプトに合った物件を探します。
創業計画を策定する
コンセプトが決まり、家賃などのコストの目途が立ったら、創業計画を策定します。
資金調達する
自己資金で足りなければ融資を受けて資金を調達します。
メニューを開発する
コンセプトにもとづき、メニュー作りをします。
内外装工事
店舗のレイアウトを決めて、必要な内外装工事を行います。
許可申請・届出等
法律にもとづき、保健所や消防署に許可申請や届出をします。
開店
関係者を招待するプレオープンを行った後、グランドオープンするのが一般的です。
飲食店開業に関する法律上の規制
飲食店は誰もが自由に開業できるわけではなく、法律上の規制があります。飲食店には特定の資格を持った人を置かなければならないほか、保健所の許可等も必要です。
飲食店起業に必要な資格
飲食店を始めるためには、次のような資格を取っておかなければなりません。なお、飲食店経営には調理師免許は不要です。
飲食店は、1つの店舗に1人は必ず食品衛生管理者を置かなければなりません。都道府県が開催している1日の講習を受けることで取得できます。 受験料は教材費込みで10,000円です。 | |
収容人数が30人以上の店舗では防火管理者を置く必要があります。また、延床面積よって必要な資格等級が異なります。 延床面積が300平米以上の場合は「甲種防火管理者」、300平米未満の場合は「乙種防火管理者もしくは甲種防火管理者」が必要です。消防署などが実施している講習を受けると1~2日で取得できます。 受験料は甲種が8,000円、乙種が7,000円です。 |
飲食店を始める前には許可・届出も必要
飲食店を開業するときには、事前に保健所に申請して営業許可を受けなければなりません。また、消防署に防火対象物使用開始届や火を使用する設備等の設置届をする必要もあります。
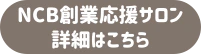
飲食店開業のポイント①創業計画策定
飲食店の創業では、しっかりとした創業計画を立てることが欠かせません。創業計画は、次のような手順で立てていきます。
販売計画と仕入計画を立てる
お店のコンセプトにもとづき、販売計画と仕入計画を立てます。販売計画、仕入計画では次のような点を意識しておきましょう。
販売計画 | 誰が | 従業員を必要とするのか、家族のみでよいのか |
誰に | どのような顧客層をターゲットにするのか | |
何を | どのようなサービスをするのか | |
どのように | どのような販売方法とするのか | |
どこで | 店舗はどこにするか | |
どんな条件で | カード決済の可否等 | |
いつ | 営業時間 | |
仕入計画 | 何を | 売れ筋商品や販売戦略に沿った材料の確保の可否 |
どこから | 安定供給してくれる仕入先の確保 | |
どんな条件で | 買掛の可否等 | |
どんな計画で | 過剰在庫にならないよう計画 |
資金計画を立てる
設備資金や運転資金を見積もり、どのようにして資金調達をするかを検討します。資金調達の方法としては、自己資金のほか、家族や友人等からの借入、銀行や日本政策金融公庫等から融資を受ける方法があります。
売上予測をする
先ほどは資金計画について述べましたが、楽観的な計画を立てられている人も多いのが実情です。具体的な根拠に基づいた売り上げ予測をおこない、売上計画を作成する必要があります。例えば、近隣店舗の客単価の相場、業界平均なども考慮する必要があるでしょう。
以下では、例を挙げながら開業後の売上高がどれくらいになるのかを予測します。売上予測は、「客単価×席数×回転数」で計算します。
【例】
客単価 | 昼800円、夜3,500円 |
席数 | 30席 |
回転数 | 昼2回転、夜0.6回転 |
上記の条件の場合、1日あたりの売上予測は次のようになります。
売上予測=(800円×30席×2回転)+(3,500円×30席×0.6回転)=11万1,000円
1か月に25日稼働する場合、1か月あたりの売上予測は次のようになります。
11万1,000円×25=277万5,000円
収支計画を立てる
収入は売上高、支出は売上原価と経費(人件費、家賃、支払利息等)で、収入から支出を差し引きしたものが利益になります。売上高は創業当初と軌道に乗った後で変わることが予想されるため、それぞれの利益がどれくらいになりそうかを計算します。
飲食店開業のポイント②創業準備と創業計画書の書き方
創業計画を策定したら、創業計画書を作成し、創業準備を行います。創業計画書は融資を申し込む際に金融機関に提出することになるため、書き方をしっかり押さえておきましょう。以下、日本政策金融公庫の創業計画書に沿って、創業準備のチェックポイントを説明します。
創業動機と事業経験
事業に対する考え方や熱意、将来的な事業展開を明確にします。創業動機としては、「独立をすすめられた」などの理由ではなく、自らが主体的に「創業したい」という意欲を持っていることが大切です。
飲食業界での勤務経験が豊富であれば、事業が成功する可能性も高いと判断され、融資の際にも有利になると考えられます。勤務時代に取り組んだことをまとめてみましょう。
商品・サービス
商品・サービスや接客面でのセールスポイントを明確にします。「アットホームな店」といったあいまいなものではなく、商品の特徴や内装へのこだわりなどを具体的に考えておく必要があります。
取引先・取引条件
飲食店の場合、販売先は一般個人になりますが、会社員・学生などの具体的なターゲットを決めましょう。仕入先としては信頼できる業者を選ぶ必要があります。
必要な資金
創業時には、設備資金として賃貸物件の保証金や内外装工事の費用、厨房機器・什器・備品等の購入費用が必要です。周辺相場と比べたり、複数の会社から見積もりを取ったりして、妥当な水準かどうかをチェックしましょう。
創業後は思ったように売上が上がらないこともあるので、資金不足に陥らないために、当面の運転資金も準備しておかなければなりません。運転資金は、開業後半年程度の赤字を補てんできるように用意しておくのがよいでしょう。
資金調達の方法
自己資金に余裕があれば、創業後の月々の返済がしやすくなります。開業までに自己資金をコツコツ貯めておきましょう。
なお、西日本シティ銀行では独自の創業融資商品をご用意しています。
融資商品の詳細は、NCB創業応援サロンにお問い合わせください。
事業の見通し
事業の見通しを立て、創業計画書に収支計画を記入します。予想売上高が過大になったり、予想経費が過少になったりしないように、根拠を明確にしながら見積もりしましょう。創業計画書を一人で作り上げるのは大変なうえ時間もかなりかかります。西日本シティ銀行の「NCB創業応援サロン」では創業計画書の作成支援も行っているので、作成される際は資金調達と合わせて是非ご相談ください。
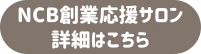
飲食店開業のポイント③適切なコスト配分を把握
飲食店で利益を出すためには、コスト意識を持つことが大切です。コスト配分は業態や業種によって変わってきます。創業しようとする業種ではコストはどれくらいが適切かを把握しておきましょう。
業態ごとのコスト配分は?
飲食店でかかる主なコストには、原材料費、人件費、家賃があります。一口に飲食店といっても、業態によって適切なコスト配分は異なります。
コスト配分のタイプ | 業種例 | 摘要 |
|---|---|---|
フード重視型 | バイキング、ファーストフードなど | フード(原材料費)にコストをかけ、サービスのコストを抑えた業態 |
サービス重視型 | バー、スナックなど | サービス(人件費)にコストをかけ、フードのコストを抑えた業態 |
立地重視型 | コーヒーチェーンなど | 立地(家賃)にコストをかけ、フード・サービスのコストを抑えた業態 |
費用のうち原価率・人件費率の目安は?
収支予測をする際には、創業しようとしている業種の平均的な原価率、人件費率を把握しておくとスムーズです。
飲食店開業のポイント④顧客が集まる店舗の条件
店舗の外装や立地条件の選択を誤ってしまうと、お客さんが入らない可能性も考えられます。飲食店で集客のために必要な店舗の条件を知っておきましょう。
店舗の外装・看板等
飲食店の外装や看板では、一目見て何のお店かわかるかどうかが重要です。たとえば、蕎麦屋とイタリアンのお店の外装は全く違うのが一般的といえます。お客さんが見ただけで何のお店かをイメージできるよう、色や形などを工夫しましょう。
看板では店名以外に、「喫茶店」や「居酒屋」「レストラン」であるとアピールすることも大切です。メニュー看板を出す場合にも、わかりやすい表記を心がけましょう。
店舗の階数
ビルが建っている場所自体は良くても、階数によって入りやすさが大きく変わるといえます。最も入りやすいのは1階で、ほとんどの業態で好立地となります。地下1階や2階ならまだ入りやすいと考えられますが、3階以上はエレベーターがない限り避けた方が無難といえるでしょう。
また、隠れ家的なお店であれば地下1階の方が雰囲気を演出しやすいといったメリットもあるため、お店のコンセプトに合った物件を選ぶことも大切です。
店舗で使う厨房機器
飲食店を開業する際に、厨房機器が必要になるケースが多いでしょう。西日本シティ銀行では皆さま開業支援策のひとつとして、厨房機器販売の大手である株式会社テンポスバスターズと創業支援面で業務連携をしています。
連携特典として、西日本シティ銀行経由で注文することで、通常よりも安く厨房機器等を購入できます。開業時の設備資金を抑えたい方は是非検討ください。
「株式会社テンポスバスターズ西日本シティ銀行 特別プラン」について
内容 | 飲食店のお客さまは、下記のサービスをご利用いただけます。
※覆面調査は、飲食費や交通費などの実費が発生します。 |
|---|---|
ご利用いただけるお客さま | 以下の(1)、(2)の条件を全て満たされるお客さま
(2)の利用対象者
|
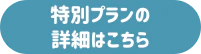
飲食店開業のポイント⑤融資を受けるための準備
創業のための資金は自己資金だけでは不足することが多いため、スムーズに融資が受けられるようにしておくことも忘れてはいけません。金融機関から融資を受ける際には、次の3点が重視されることを知っておきましょう。
(1) 勤務経験
独立開業する前に、十分な勤務経験があった方が有利になると考えられます。技術力を磨くだけでなく、店舗運営についてのノウハウも身につけておきましょう。
(2) 自己資金
まとまったお金がたまたま入ったから開業に使うというよりも、計画性を持って自己資金を貯めている方が評価されます。将来の独立開業のために、少しずつでも積立をしておきましょう。
(3) 諸支払い
金融機関にとっては、貸したお金をきちんと返してくれる人かどうかが重要です。そのための判断材料として、公共料金、家賃、住宅ローン等の支払い状況等を総合的に確認します。もし各種支払いが遅れていたりすると、信用力がないとされ、融資が受けられないことも考えられます。残高不足で引き落としされないことのないよう、お金の管理をきちんとしておきましょう。
まとめ
将来的に飲食店創業を考えている場合、自己資金を貯める、勤務経験を積むなどの準備が必要といえます。創業の目途が立ったら、創業計画を策定して創業準備を行いましょう。計画的に準備を進めていれば、金融機関からも融資を受けやすくなり、資金調達もスムーズにできると考えられます。創業計画書を一人で作り上げるのは大変なうえ時間もかなりかかります。西日本シティ銀行の「NCB創業応援サロン」では創業計画書の作成支援も行っているので、作成される際は資金調達と合わせて是非ご相談ください。
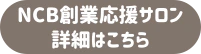
- 創業
Writer

AFP(日本FP協会認定)、行政書士、夫婦カウンセラー
大学卒業後、複数の法律事務所に勤務。30代で結婚、出産した後、5年間の専業主婦経験を経て仕事復帰。現在はAFP、行政書士、夫婦カウンセラーとして活動中。夫婦問題に悩む幅広い世代の男女にカウンセリングを行っており、離婚を考える人には手続きのサポート、生活設計や子育てについてのアドバイス、自分らしい生き方を見つけるコーチングを行っている。
このライターの記事を読む >おすすめの記事

対談記事【ビジネスのヒント】|接骨院から建設業へ。驚きの経歴と経緯
経営に関する悩みや課題を抱える事業経営者の皆さまにとって、銀行の営業担当者は心強いサポーターの一人です。そこで、リニュー編集部では、事業経営者と西日本シティ銀行の営業担当者にスポットをあててインタビュー。サポートのきっかけや、事業の成功までの道のりなどをざっくばらんにお話しいただきます。

【今月のZero-Ten Park】株式会社ストリ|心と体に美しさと健やかさを
福岡を中心に世界5カ国15拠点を展開するシェアオフィス&コワーキングスペース「Zero-Ten Park」。そこに入居している、今注目したい企業をピックアップ。今回は「株式会社ストリ」をご紹介します。

働き方改革に注力している企業ってどんなところ?|次世代ワークスタイル応援私募債「ミライへの路」
これから就職先を探している学生のみなさんにとって、どんな企業が自分にとって働きやすいのか、気になりますよね。そこで今回は、西日本シティ銀行が取り扱う次世代ワークスタイル応援私募債『ミライへの路*』を発行している企業のみなさんにご協力をいただき、その企業で実際に働いている若手の社員に直撃インタビュー。なぜ入社を決めたのか、実際に働いてみてどんな感じなのか、などをヒアリングしました。また、併せて、各企業の経営者にも、求める人材像や今後の展望などをお話しいただきました。取材に協力いただいた企業は、地元・福岡で働き方改革に注力している、優良企業ばかりです。ぜひ、就職希望先の候補の一つとして、働く先輩たちのリアルな声をご一読ください。

【ミライへの路に挑む企業】地球を守り働く人の成長を支える環境調査会社|株式会社ENJEC
多様な生き方や働き方が広がりつつある現代。企業にはこれからますます、さまざまな人が働きやすい環境を整えることが求められます。社員の働きやすさを叶える企業の取り組みとは?この連載では、実際に働き方改革を積極的に取り組む企業で働く人や経営者にインタビュー。今回は、九州を中心に、水質、大気、土壌といった環境にまつわる調査・分析の事業を手がける、福岡市の株式会社ENJEC(エンジェック)に取材しました。

質の高い人材紹介サービスで、企業も求職者も従業員も幸せに |株式会社GR8キャリア 小畑和貴さん
医療・福祉業界の人材紹介サービスをメインに事業展開する株式会社GR8(グレイト)キャリア。代表の小畑和貴さんは宮城県出身で福岡に移住し、住宅メーカーから人材紹介業界に転職したという異色のキャリアの持ち主です。創業から1年足らずでメンバーは20人ほどに増え、順調な滑り出しといえます。しかし、組織や利益の拡大は求めず、あくまでも「質の高いサービス提供」と「社員とその家族が笑顔で過ごせること」にこだわり続けたいという小畑さんに、その思いの根源や起業のストーリーを聞きました。

番組・動画制作から拠点の運営まで、幅広い事業を展開|株式会社move on.e 岩谷直生さん
20歳から放送局の番組制作に関わり、個人事業主を経て、41歳で番組と動画制作を主軸にした株式会社move on.eを設立した岩谷直生さん。長年のディレクター経験を生かして、マスメディアの番組やイベントを手掛ける一方で、子どもに向けた全く新しい事業にも意欲的にチャレンジしています。

【事業継続力強化計画認定制度】概要や認定のメリット、申請支援事業も紹介
近年、地震や台風などの自然災害、感染症の流行など、企業経営を取り巻くリスクが多様化しています。 こうした中で注目されているのが、災害や緊急事態に備えて事業を継続できる体制を整える「事業継続力強化計画(BCP)」です。 この計画の認定を受けることで、補助金申請時の加点や税制優遇など、さまざまなメリットがあります。 そこでこの記事では、事業継続力強化計画認定制度の概要や認定メリットに加えて、計画策定・申請を支援する取り組みについても解説します。

【中小企業必見】最低賃金引上げに伴う負担軽減策とは?福岡県の支援策も紹介
令和7年度の最低賃金引上げにより、全国的に人件費の負担が増加しています。特に中小企業や小規模事業者にとっては、賃上げへの対応が経営上の大きな課題となっています。 こうした状況を受け、国や自治体では、最低賃金の引上げに伴う事業者の負担を軽減するため、各種支援策を打ち出しています。 この記事では、最低賃金引上げに対応するための国の主な支援策に加え、福岡県独自の支援制度について解説します。


