事業承継とは?メリットやデメリットから成功させるポイントまで丸わかりガイド!

経営者の高齢化や後継者の不足などから事業承継がニュースになることも増えてきました。ではその事業承継とはどのような定義があり、どんな方法があるのでしょうか。今回は事業承継の方法やメリット・デメリット、事業承継における注意点と成功のポイントについて解説します。
事業承継とは
事業承継の定義
事業承継とは、会社・事業を後継者に引き継ぐことをいいます。
事業承継では、経営者交代に向けた後継者の選定と育成のほか、現金や不動産、設備といった目に見える財産から、経営理念やノウハウ、取引先・顧客との関係といった目に見えないところまで含め、会社・事業の経営に必要なすべての要素が引き継がれます。
事業承継の3つの要素 | |
|---|---|
人(経営) | ・経営権 ・後継者の選定・育成 ・後継者との対話 ・後継者教育 |
資産 | ・株式 ・事業用資産(設備・不動産等) ・資金(運転資金・借入金等) |
知的資産 | ・経営理念 ・経営者の信用 ・取引先との人脈 ・顧客情報 ・従業員の技術、ノウハウ ・知的財産権(特許など) ・許認可 |
事業承継の流れ
事業承継は、準備から実行までを次のような流れで進めていきます。
親族・従業員への場合
- 事業承継に向けた準備の必要性の認識
- 経営状況や経営課題などの把握(見える化)
- 事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)
- 事業承継計画の策定
- 事業承継の実行(株式・事業用資産、経営権等の承継)
社外への場合
- 事業承継に向けた準備の必要性の認識
- 経営状況や経営課題などの把握(見える化)
- 事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)
- マッチング実施
- M&A等の実施(株式・事業用資産、経営権等の承継)
事業承継の方法って?それぞれのメリット・デメリットを比較
事業承継には、大きく次の5つの方法があります。
それぞれの特徴と、メリット・デメリットを比較しながらみていきましょう。

(1)親族への事業承継
子やその他の親族を後継者として、事業を承継する方法です。
中小企業の多くでこの方法が採用されています。親族に後継者候補がいれば、第三者へ承継するよりも安心感のある方法といえます。
メリット
- 社内外の関係者から理解を得やすい
- 後継者教育等の準備期間を長く確保しやすい
- 相続等で財産や株式を後継者に移転できるため、所有と経営の分離を回避しやすい
- 創業家としての地位を保てる
一方で、後継者の不在は社会的にも大きな問題となっています。そのため、近年では役員・従業員への承継やM&Aによる第三者への承継など、親族外への承継が増えてきています。
デメリット
- 親族内に経営の資質と意欲を持つ後継者候補がいるとは限らない
- 相続人が複数いる場合、後継者の決定や経営権(自社株式)の集中が難しい(後継者とならない相続人に配慮が必要)
(2)役員・従業員への事業承継
親族以外の役員・従業員を後継者として、事業を承継する方法です。
社内に経営理念やビジョン、業務に精通した優秀な人材がいれば、比較的スムーズに事業を引き継げるメリットがあります。

メリット
- 後継者候補の幅が広がる
- 長年勤務してきた従業員への承継であれば、経営の一体性を保ちやすい
- 社内外からの理解を得やすい
一方で、社内に精通した人材が経営者としても優秀とは限らず、株式取得には多額の資金が必要となるなどの課題もあります。
デメリット
- 適任者がいるとは限らない(経営への強い意欲が求められる)
- 株式取得に多額の資金が必要となる
- 個人債務保証の引き継ぎなどの問題が多い
(3)M&A(企業合併・買収)による事業承継
M&Aとは企業の合併(Mergers)と買収(Acquisitions)のことであり、事業または会社を他の企業に売却して承継する方法です。
経営者や所有者(資本)は変わるものの、事業はこれまで通りに継続されます。オーナー経営者は後継者問題や個人保証から解放され、会社売却による創業者利益が獲得できるなどのメリットが期待できます。
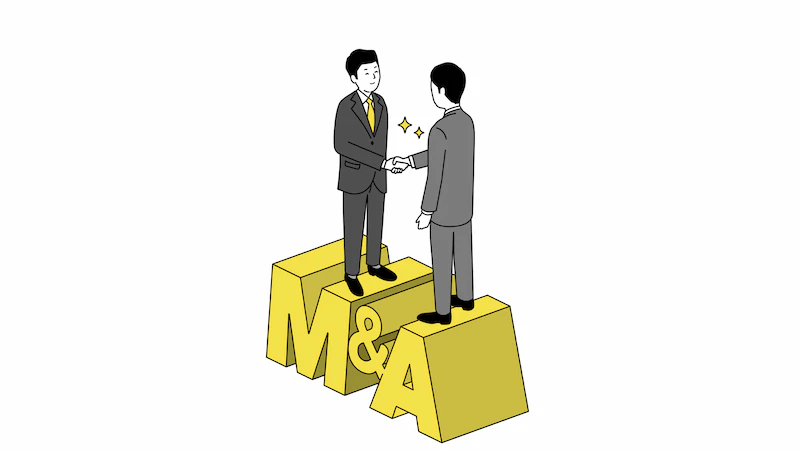
メリット
- 後継者候補の幅が広がる(後継者問題の解決)
- 現経営者は会社売却による利益(創業者利益)を獲得できる
- 経営者の個人保証が解除される
- 事業のさらなる成長が見込める
M&Aでは、希望に合う買い手を見つけられるかどうかが一番の関門であり、成功のカギを握ります。
デメリット
- 希望する条件を満たす買い手が見つかるとは限らない
- 経営の一体性を保つのが難しい
- 株式譲渡後の引継ぎに時間がかかるケースがある
(4)株式上場による事業承継
自社株式を証券取引市場に公開(上場)し、事業を承継する方法です。
自社株式が不特定多数の株主に保有されるため、経営と資本の分離が図れます。上場によって会社の信用力や知名度が向上すれば、人材採用や資金調達に有利に働きます。有利に働けば、安心して経営を託せる優秀な人材が見つかる可能性が高まります。オーナー経営者は保有する株式を売却して経営から退く以外にも、自社株式を一定数継続保有して経営に関与を続けるなどの選択も可能です。

メリット
- 所有と経営の分離が図れる
- 人材採用や資金調達がしやすくなる
- 保有株式を売却し現金化できる
- 経営への関与を続ける選択もできる
ただし上場には審査があり、基準を満たせなければ上場できません。内部統制システムの整備など、上場までに年単位の時間がかかることも想定しておかなければなりません。小規模の企業や事業承継までに時間的余裕がない企業には、ハードルの高い方法といえます。
デメリット
- 基準を満たせないと上場できない
- 上場までに時間がかかる
(5)信託による事業承継
信託は、「委託者」が「受託者」に財産を託し、受託者が財産を管理・運用して得られた利益を、委託者の指定する「受益者」が受け取る仕組みです。
信託を活用した事業承継では、経営者の意向を反映した柔軟な承継が行えて、後継者の地位が安定しやすいというメリットがあります。
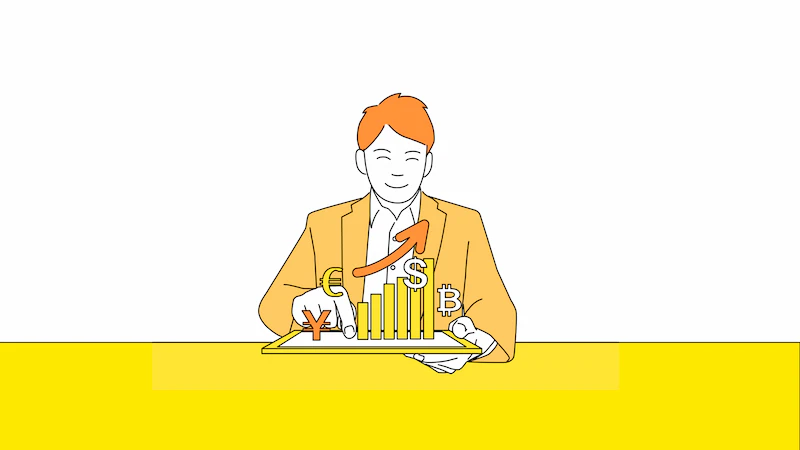
メリット
- 経営者の意向を反映した柔軟な承継が行える
- 後継者が確実に経営権を取得できる
- 第三者に株式が渡るリスクがない
- 経営の空白期間が生じない(相続発生と同時に経営権が後継者へ移転する)
事業承継税制が適用せずに信託銀行などの金融機関を受託者とする契約では、報酬の支払いが必要になるなどのデメリットもあります。法定相続人の遺留分侵害にも留意しなければなりません。
デメリット
- 事業承継税制の適用を受けられない
- 信託銀行等を受託者とする場合、報酬の支払いが必要になる
- 遺留分の侵害に配慮しなければならない
信託を活用した事業承継には、次の3つの方法があります。
(1)遺言代用信託
現経営者を委託者兼受益者、信託銀行などを受託者として信託契約を締結し、自社株式を信託します。信託契約の内容として、現経営者の相続発生後、後継者が受益者として信託財産である自社株式を取得する旨を定めておきます。
この手法では、当初は現経営者に議決権と配当などの受益権が残り、信託期間中は経営権を維持されます。相続が発生すると信託契約は終了し、受託者から後継者へ自社株が交付され、経営権が確実に承継されるのです。
(2)他益信託
現経営者を委託者、信託銀行などを受託者、後継者を受益者として信託契約を締結し、自社株式を信託します。
この手法では、信託を設定したタイミングで現経営者から後継者に自社株式が贈与されたとみなされ、自社株式の財産的な価値(財産権)が実質的に後継者に移転します。この時点で、贈与税が発生します。
一方で信託契約の中に現経営者が議決権を行使できる旨を定めておくことで、信託期間中は現経営者が経営権を維持できます。相続が発生すると信託契約は終了し、受託者から受益者である後継者へ自社株式が交付され、経営権が確実に承継されます。
将来の株価の上昇が見込まれ、早期に自社株式を承継して税負担を抑えたいものの、現時点で後継者に経営を委ねるには不安が残るケースに有効な手法です。
(3)後継ぎ遺贈型受益者連続信託
現経営者を委託者、信託銀行などを受託者、後継者を受益者として信託契約を締結し、自社株式を信託します。
この手法では信託設定時に当初の受益者に加え、当初の受益者が死亡した場合に受益者となる人を指定しておきましょう。これにより経営の空白期間を生じさせることなく、スムーズに事業を承継できます。
指定する受益者の数に制限はありませんが、指定できる期間には制限があります(信託法91条)。実務上、信託設定から30年経過後に受益権を取得した人が死亡または受益権が消滅すると信託契約は終了し、その次の受益者が指定されていても、その指定は無効になります。
知っておきたい!事業承継をする際の5つの注意点
事業承継を進めていくうえで注意すべきポイントは、次の5つです。

関係者の理解を得ながら進める
事業承継は経営者だけでなく、多くの人に影響する問題です。
親族や役員・従業員への承継の場合、後継者、親族、役員・従業員、取引先企業、金融機関など、関係者に事業承継計画を公表し、理解を得たうえで進めていくことが大切です。特に親族・社内に複数の候補者がいる場合、後継者候補と対話を重ねて密な意思疎通を図り、対立や不満を生じさせないよう配慮しながら選定を進めていきます。
一方、M&Aによる社外への承継では、準備段階まではごく一部の関係者以外に情報が漏れないよう十分に注意し、秘密裏に進めなければなりません。
後継者以外の相続人への配慮
相続による事業承継では、後継者以外の相続人に不満が生じないよう配慮が必要です。
法定相続人となる人のうち、兄弟姉妹を除く配偶者や子、父母などには、法律により最低限保証された相続分である「遺留分」があります。後継者に自社株式や事業用資産の大部分を相続させたことで、他の相続人が遺留分を下回る財産しか相続できなかった場合、遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」により、後継者に対して侵害額相当分の支払いを求められます。
会社財産以外の財産が少ないなど、後継者以外の遺留分を侵害してしまうおそれがあれば、後継者が侵害額相当額を補てんできるように対策を講じておきましょう。現経営者を被保険者、後継者を受取人とし、侵害額相当額の生命保険に加入するのもひとつの方法です。
後継者以外に自社株式が分散しないようにする
親族や従業員への事業承継では、後継者が一定以上の自社株式を保有することが安定した経営権の維持に欠かせません。後継者とその友好的な株主で、議決権の3分の2以上を確保し、株主総会で重要事項を決議できる状態が理想です。
株式が分散してしまっている場合、経営者や後継者個人による買い取り、会社による自社株式取得などにより、事業承継前になるべく買い集めておきましょう。
後継者以外が自社株式を取得した場合に備え、定款で株式に譲渡制限を設定したり、売り渡しを請求できる旨を定め、会社が自社株式を買い取れるようにしておいたりするのも有効な対策です。
事業承継には時間がかかる(後継者選定・教育、負担軽減対策、社内体制整備など)
親族や従業員への承継では、後継者の選定・教育に数年から10年程度かかることを想定しておかなければなりません。M&Aでは比較的短期間での承継も可能ですが、買い手探しが難航する場合もあり、時間的な余裕がないと条件面で妥協せざるを得なくなるおそれがあります。
自社株式の評価引き下げによる相続税・贈与税の負担軽減対策や、競争力強化などの経営改善、社内体制の整備などを行うのにも時間がかかります。
後継者に経営者としての教育をしっかり行うためや、承継後も事業を安定して継続するためなど、事業承継は時間的な余裕を持って計画的に行うことが大切です。
事業承継にはお金がかかる(税金・自社株式取得資金等)
後継者の相続税や贈与税の納税資金、従業員が承継する場合の自社株式や事業用資産買取資金、分散した自社株式の買取資金など、事業承継にはお金がかかります。
経営者の交代を境に、金融機関の融資審査が厳しくなるケースがあります。事業承継のため資金の借り入れが必要であれば、事業承継に先立ち、現経営者が金融機関に協力を取り付けておくのが望ましいでしょう。
事業承継に伴う資金不足が発生した場合は都道府県に申請し、経営承継円滑化法における知事の認定を受ければ、日本政策金融公庫や信用保証協会から融資を受けられる可能性があります。
また、税負担を軽減する特例も複数用意されているため、利用できる制度はうまく活用しましょう。
- 事業承継税制(非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予・免除制度)
- 小規模宅地等の課税特例(一定の面積までの事業用・居住用宅地の課税価格を5〜8割減額)
- 死亡退職金・死亡保険金に対する相続税の非課税枠
- 贈与税の歴年課税(年間110万円までの贈与が非課税)
- 相続時精算課税制度
事業承継を成功させるために経営者が確認すべきこと
事業承継の準備、社内体制の整備はなるべく早く始める
事業承継は経営状態の把握から経営改善、承継方法の決定、社内外の調整など、やるべきことは多く、実行までには時間がかかります。
時間的な余裕を持って計画的に事業承継を進めるため、準備はなるべく早い時期から始めましょう。

適切な相手に相談し、サポートを受ける
事業承継をスムーズに進めるため、課題や目的に応じて専門家など適切な相手に相談し、サポートを受けましょう。
- 承継準備について…商工会・商工会議所、中央会、金融機関、士業等専門家、よろず支援拠点など
- 後継者教育について…中小企業大学校など
- 自社株式の株価について…士業等専門家など
- 個人保証を外したい…金融機関、中小機構など
- 相続税・贈与税について…税理士など
- 資金調達について…金融機関、信用保証協会など
- 債務整理について…金融機関、中小企業再生支援協議会など
- 承継後の事業見直しについて…商工会・商工会議所、中央会、士業等専門家、よろず支援拠点など
- 社外から後継者を探したい…事業引き継ぎ支援センターなど
- 廃業について…士業等専門家、商工会・商工会議所、よろず支援拠点など
※よろず支援拠点は、多様な分野に精通した専門家が経営上の悩みに親身に耳を傾け、抱えている悩みの本質的な課題を明確化するとともに、適切な解決策をご提案してくれる拠点です。福岡県よろず支援拠点、東京都よろず支援拠点、大阪府よろず支援拠点など全国各地に存在します。
※西日本シティ銀行でも、同様の相談を受け付けられることをご存じですか?事業承継でお困りの際は、お近くの西日本シティ銀行までお問い合わせください。
まとめ
事業承継には5つの方法があり、後継者の有無や会社の状況、経営者の希望などにあわせて選択します。いずれの方法も実行までには入念な準備が必要であり、成功させるためには専門家などのサポートが欠かせません。
西日本シティ銀行では、事業承継やM&Aの相談・サポートを行っています。また、地域の中小企業の成長を支援するプラットフォーム「Big Advance」が提供するオンライン士業相談サービスや全国の金融機関と連携した全国規模のビジネスマッチングサービスは事業承継にも活用できます。事業承継をどう進めていけばいいか迷われている場合には、ぜひ西日本シティ銀行にご相談ください。
- 事業承継
Writer

RAPPORT Consulting Office代表、1級FP技能士、CFP(R)、証券外務員一種
証券会社・生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。お金に関するコンサルティング業務や執筆業務などを行う。ミニマリズムとマネープランニングを融合したシンプルで豊かな暮らしを提案している。
このライターの記事を読む >おすすめの記事

対談記事【ビジネスのヒント】|接骨院から建設業へ。驚きの経歴と経緯
経営に関する悩みや課題を抱える事業経営者の皆さまにとって、銀行の営業担当者は心強いサポーターの一人です。そこで、リニュー編集部では、事業経営者と西日本シティ銀行の営業担当者にスポットをあててインタビュー。サポートのきっかけや、事業の成功までの道のりなどをざっくばらんにお話しいただきます。

【今月のZero-Ten Park】株式会社ストリ|心と体に美しさと健やかさを
福岡を中心に世界5カ国15拠点を展開するシェアオフィス&コワーキングスペース「Zero-Ten Park」。そこに入居している、今注目したい企業をピックアップ。今回は「株式会社ストリ」をご紹介します。

働き方改革に注力している企業ってどんなところ?|次世代ワークスタイル応援私募債「ミライへの路」
これから就職先を探している学生のみなさんにとって、どんな企業が自分にとって働きやすいのか、気になりますよね。そこで今回は、西日本シティ銀行が取り扱う次世代ワークスタイル応援私募債『ミライへの路*』を発行している企業のみなさんにご協力をいただき、その企業で実際に働いている若手の社員に直撃インタビュー。なぜ入社を決めたのか、実際に働いてみてどんな感じなのか、などをヒアリングしました。また、併せて、各企業の経営者にも、求める人材像や今後の展望などをお話しいただきました。取材に協力いただいた企業は、地元・福岡で働き方改革に注力している、優良企業ばかりです。ぜひ、就職希望先の候補の一つとして、働く先輩たちのリアルな声をご一読ください。

【ミライへの路に挑む企業】地球を守り働く人の成長を支える環境調査会社|株式会社ENJEC
多様な生き方や働き方が広がりつつある現代。企業にはこれからますます、さまざまな人が働きやすい環境を整えることが求められます。社員の働きやすさを叶える企業の取り組みとは?この連載では、実際に働き方改革を積極的に取り組む企業で働く人や経営者にインタビュー。今回は、九州を中心に、水質、大気、土壌といった環境にまつわる調査・分析の事業を手がける、福岡市の株式会社ENJEC(エンジェック)に取材しました。

質の高い人材紹介サービスで、企業も求職者も従業員も幸せに |株式会社GR8キャリア 小畑和貴さん
医療・福祉業界の人材紹介サービスをメインに事業展開する株式会社GR8(グレイト)キャリア。代表の小畑和貴さんは宮城県出身で福岡に移住し、住宅メーカーから人材紹介業界に転職したという異色のキャリアの持ち主です。創業から1年足らずでメンバーは20人ほどに増え、順調な滑り出しといえます。しかし、組織や利益の拡大は求めず、あくまでも「質の高いサービス提供」と「社員とその家族が笑顔で過ごせること」にこだわり続けたいという小畑さんに、その思いの根源や起業のストーリーを聞きました。

番組・動画制作から拠点の運営まで、幅広い事業を展開|株式会社move on.e 岩谷直生さん
20歳から放送局の番組制作に関わり、個人事業主を経て、41歳で番組と動画制作を主軸にした株式会社move on.eを設立した岩谷直生さん。長年のディレクター経験を生かして、マスメディアの番組やイベントを手掛ける一方で、子どもに向けた全く新しい事業にも意欲的にチャレンジしています。

【事業継続力強化計画認定制度】概要や認定のメリット、申請支援事業も紹介
近年、地震や台風などの自然災害、感染症の流行など、企業経営を取り巻くリスクが多様化しています。 こうした中で注目されているのが、災害や緊急事態に備えて事業を継続できる体制を整える「事業継続力強化計画(BCP)」です。 この計画の認定を受けることで、補助金申請時の加点や税制優遇など、さまざまなメリットがあります。 そこでこの記事では、事業継続力強化計画認定制度の概要や認定メリットに加えて、計画策定・申請を支援する取り組みについても解説します。

【中小企業必見】最低賃金引上げに伴う負担軽減策とは?福岡県の支援策も紹介
令和7年度の最低賃金引上げにより、全国的に人件費の負担が増加しています。特に中小企業や小規模事業者にとっては、賃上げへの対応が経営上の大きな課題となっています。 こうした状況を受け、国や自治体では、最低賃金の引上げに伴う事業者の負担を軽減するため、各種支援策を打ち出しています。 この記事では、最低賃金引上げに対応するための国の主な支援策に加え、福岡県独自の支援制度について解説します。


