担当者必見!自社オウンドメディアの運営で失敗する要因と対策方法を一挙紹介

オウンドメディアは企業のブランディング戦略の一つとして有効です。しかし、一歩間違えると結果的にサイトの更新停止・閉鎖にも繋がりかねません。そこで当ページでは、オウンドメディアの運営でありがちな失敗事例と改善策を詳しくお伝えします。
目次
オウンドメディアで失敗するポイントとは
近年、企業のブランディング戦略とウェブ集客の施策の一環として、オウンドメディアの導入を進める企業が増えていますが、残念ながら失敗に終わってしまうケースが多く存在します。主に失敗するポイントをまとめると、以下の3点が挙げられます。
オウンドメディア失敗のポイント
- オウンドメディアの準備
- オウンドメディアのコンテンツ制作
- オウンドメディアのマーケティング
ここでは、オウンドメディアにおいて失敗に陥るケースの多い上記のポイントについて、それぞれの事例や、その改善策・回避策も交えてご紹介します。
オウンドメディアの【準備】で失敗する事例4つと改善方法
①オウンドメディアを運営する目的が曖昧
「とりあえずサイト公開しておけば集客できそう」という軽い感覚でオウンドメディアを開設すると、中長期的な運営は難しくなります。途中で「何のためにオウンドメディアの活用を続けているのか」という疑問が生まれて放置状態に・・・というパターンに陥りやすいです。
また後述もしますが、オウンドメディアはサイトを作成するだけでは終わらず、コンテンツの公開やユーザー獲得のための戦略を立てるなど、全体的に多くの工数が発生します。運用がストップする事で開設までの貴重な時間や費用が無駄になってしまい、かなりもったいないです。
②オウンドメディアのコンセプトが不明瞭
オウンドメディアのサイトコンセプトが不明瞭のまま運営を進めると、特定のファンはつきにくくなります。サイトコンセプトはユーザーが求めている情報と企業が与える情報に相違を生まないための重要な要素です。
運営開始から早い段階で明確にさせないと後々公開するコンテンツの内容やサイトイメージの方向性にばらつきが出やすくなるため、せっかく獲得したユーザーが定着せず企業が与えたいイメージや商品を提供しにくくなってしまいます。
③オウンドメディアそのものの制作にお金をかけすぎている

オウンドメディアで公開するコンテンツよりもサイトそのものの制作に予算をかけすぎると、後々痛手に出やすくなります。オウンドメディアに訪れるユーザーは知りたい情報を第一に求めている場合がほとんどであり、ニーズを満たすためのコンテンツ制作にかけるコストの方が重要になるからです。
かっこいい・おしゃれなサイトにしたいという理由から凝ったギミックやデザインのために高額な初期費用を投じてしまいがちです。しかしそれが仇となり、コンテンツ作成やサイト運用のための人件費が足りなくなって更新を止めざるを得なくなってしまったという失敗事例は珍しくありません。
④凝ったデザインやロゴの制作に注力しすぎてしまう
③と重なる部分ですが、デザインやロゴの制作に注力しすぎるのも避けた方が良いでしょう。見栄えを気にしすぎるあまりサイト公開までに時間がかかりすぎてしまうと、肝心のコンテンツ制作に至るまでの期間を先延ばしにせざるをえなくなってしまいます。
ユーザーが一番求めている情報の提供が遅れる分、オウンドメディア経由での顧客を獲得がはじまるまでの期間も伸びてしまうというわけです。これではオウンドメディアが存在していても企業の目的を果たせないため、かなりもったいない状況になり得ると言えます。
オウンドメディアの準備で失敗しないための対策3つ

オウンドメディアを運営する上で、準備段階では以下の対策を実行しましょう。
オウンドメディアの準備で失敗を避けるための対策
- 企業にとってメリットになり得る明確な目的を掲げる
- 獲得したいユーザー層をベースに具体的なサイトコンセプトを決める
- 初期段階のサイトデザインは必要最低限のシンプルな状態でとどめる
「自社商品の売り上げアップ」「ブランディングして企業のファンを獲得する」など、オウンドメディアを運営する目的を明確にしてからサイト開設の準備を進めましょう。これらは具体的であればあるほど、オウンドメディアの方向性にブレが生じにくくなります。
またおおもとの目的やコンセプトなどの土台をしっかり決めておけば、初期段階のサイトのデザイン周りや構想改装はシンプルなものでも構いません。視覚的な部分も重要ですが、この辺りの構築はユーザーが求めるコンテンツがある程度確保できてからでもいいでしょう。
オウンドメディアの【コンテンツ制作】で失敗する事例4つと改善方法

①公開しているコンテンツの数が不足している
コンテンツ数が不十分なのもオウンドメディアを運営する上でよく挙げられる失敗事例です。基本的にオウンドメディアの流入元の大半はGoogleやYahooでの自然検索からなので、公開したコンテンツは検索結果の上位に表示される必要があります。
検索順位はGoogleやYahooに存在するクローラーと呼ばれるAIが判断するため一概には言い切れないものの、コンテンツが複数サイト内にあるかどうかも判断基準の一つとして挙げられています。
そのためコンテンツの数が不足していると、クローラーは「サイト内に関連している公開ページが少ない」と判断するため、どんなに質が高いコンテンツでも評価されにくくなるというわけです。
②誰に向けてコンテンツ作成しているか不明瞭
作成するコンテンツが誰に向けたものなのかが曖昧になるのもよくある失敗事例の一つです。ユーザーは自身が抱えている悩みを解決するために検索し、サイトに訪れています。オウンドメディアにおけるコンテンツはユーザーのニーズを満たすために存在しているのです。
そのため「どういった悩みを抱えたユーザーに向けているのか」をあらかじめ決めておかないとコンテンツの方向性がブレてしまい、仮にアクセスされても「このページでは悩みを解決できない」と判断されてすぐに離脱されやすくなります。
③想定される検索キーワードの選び方が不適切
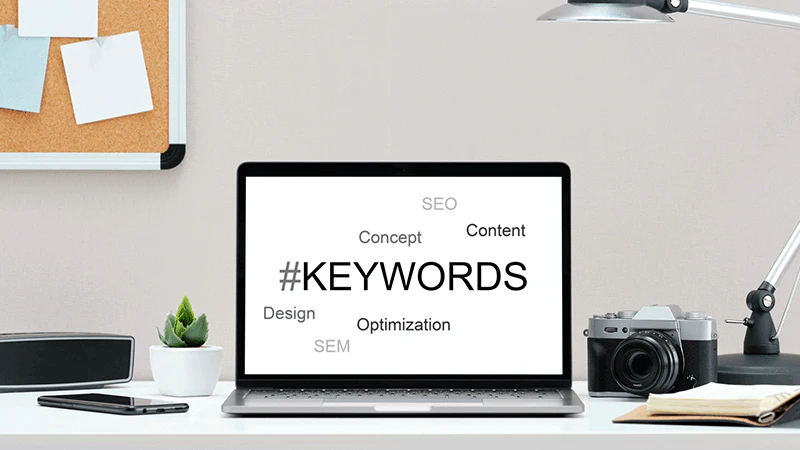
コンテンツを制作する上で、ユーザーが検索窓に打ち込むキーワードを選ばなかったり曖昧なまま進めると失敗に繋がりやすくなります。一口に検索キーワードといっても、ボリューム(検索される頻度の高さ)や検索結果に表示される他サイトの方向性が大きく変わるからです。
よくある事例として、少ないページで多くの流入を獲得したいがためにボリュームが大きなキーワードばかりを選んでしまうパターンがあります。しかしSEO的な観点から見ると、ボリュームが大きなキーワードは比較的検索結果の上位に表示されにくい傾向があり、かえって流入が見込めない可能性があるのです。
また大前提として、ユーザーが検索するであろうキーワードを想定したコンテンツを制作しないとクローラーから「ユーザーの意図にそぐわない」と判断されてしまい、公開しても上位表示されずユーザーの目に留まりにくくなります。
④全体的にコンテンツの内容が偏りすぎてつまらない
単純にオウンドメディアで公開するコンテンツの内容が偏ってしまうとユーザーにとってつまらないと判断されてしまい、固定ファンの獲得が厳しい状況に繋がりやすくなります。
ユーザーの悩みや疑問は日々増えていくので、仮に固定ファンがついたとしても「このサイトは決まった内容しか発信していない」と判断されれば離れてしまうでしょう。
また企業の身内ネタなど、ユーザーにとって関係していなかったり興味がないと思われるようなコンテンツも数が多いとしつこいと思われてしまいかねないので、そのような内容も極力避けるべきです。
オウンドメディアのコンテンツ制作で失敗を避ける対策5つ

オウンドメディアで公開するコンテンツは以下のポイントをおさえた上で作成しましょう。
オウンドメディアのコンテンツ制作で失敗を避けるための改善策
- 少なくとも50ページ前後はコンテンツを用意する
- ページごとにターゲットユーザーの特徴や想定される悩みを明確にしておく
- 少ないボリュームのキーワードから攻めたコンテンツ制作を行う
- サイトコンセプトをベースに幅広いジャンルやカテゴリーを開拓する
- SEOを意識したコンテンツを作成し検索結果の上位を狙う
繰り返しになりますが、Webサイトのコンテンツの流入の多くはGoogleやYahooの検索結果からです。検索結果のページで表示される位置が高ければ高いほど多くのPVを見込めます。そのためにはユーザーファーストと、検索エンジンの最適化(SEO)を意識したコンテンツ制作はかなり効果的であると言えます。
また1ページあたりのやキーワードの量やボリュームなどの状況にもよりますが、サイト内のコンテンツが50ページ前後を超えてから検索結果で表示される順位が上がる傾向があります。地道ではありますが、まずは50ページ公開を目標として設定するといいでしょう。
オウンドメディアの【マーケティング】で失敗する事例3つと改善方法

①自社サービスや商品の宣伝しかしていない
仮にオウンドメディアの目的が商品やサービスのPRだったとしても、自社商品や企業がおすすめしたいサービスの宣伝ばかりをするのはユーザーが求めているものと反してしまうため思うような成果は出にくいです。
ユーザーは自身の疑問や悩みを解決するためにページにアクセスします。その上で勧められたサービスや商品を利用するかどうかを判断するパターンが多いので、宣伝ばかりしてもユーザーの温度感は上がりにくいと言えます。
同時にコンテンツに偏りが出てしまい、そもそも検索結果の上位に表示され難くなるのでアクセスアップも見込み難いと言えます。
②オウンドメディアの運営体制・リソースが不十分

オウンドメディアを運営する体制が整っていないのもよくある失敗の一つです。オウンドメディア運営のためには、KPI管理や運用戦略を立てるディレクターやコンテンツを制作するライター・編集者など、規模や工数に応じたリソースが必要になります。
これらが少しでも欠けているとコンテンツの質や運営を行う上での方向性が不安定になり、オウンドメディアの確立が厳しくなります。実際に、これが原因でオウンドメディアの更新を止めてしまうという事例も珍しくはありません。
また人件費削減のため一人あたりの担当業務が多すぎると手が回らず、オウンドメディアの運営を停止せざるをえないという状況も生まれやすくなります。
③目標設定が不十分でただの便利サイトになっている
オウンドメディアを運営していく上で目標設定が曖昧なまま進めてしまうと運用する方向性を見失ってしまい、結果的に運用を停止せざるを得なくなるパターンもよくある失敗事例です。
オウンドメディアに限った話ではありませんが、サイトを運営する上で「1日あたりどれくらいの人に見てもらいたいか」「1ヶ月あたりサイト経由でどれくらい売り上げを出したいか」を明確にしてから運営方針を見出す必要があります。
この辺りの目標が不明瞭だとやるべき施策の実行を進めにくくなるため、どんなにユーザーファーストを意識したコンテンツ更新を心がけてもオウンドメディアを運営する本来の目的を果たせなくなります。
オウンドメディアのマーケティングで失敗しないための対策3つ

オウンドメディアのマーケティングで失敗を避ける方法
- 人員リソースを確保し、必要な業務を適切に分担する
- 運営体制を整えてからオウンドメディアの運用を開始する
- ユーザーが求める情報の中に自社の商品やサービスの訴求をする
初期段階の目標や規模に応じて適切なリソースを確保し、担当者の稼働時間や人数、スキルを加味して業務を分担しましょう。運営がスムーズに進み、目標達成への近道となります。
また商品やサービスは全面的に押し出すのではなく、ユーザーが知りたい情報の中にさりげなくPRとして紹介すると押し売り感が出ず悪い印象を与えにくいです。
ページごとに設定した方向性やターゲットユーザーの悩み、疑問に合わせてPRの訴求内容を適宜変更することで、商品やサービスに対しての温度感を高めるきっかけにも繋がります。
【まとめ】オウンドメディアの運営を成功させる方法

オウンドメディアを運営するには、以下の対策が成功へのカギとなります。
オウンドメディア運営を成功させるための対策
- 目的やターゲットなどの初期設定は具体的に明確化させる
- ユーザーファーストを意識したコンテンツを制作する
- SEO対策を行いオウンドメディアの流入増加を試みる
- PDCAを繰り返し、オウンドメディアのKPIを伸ばす
前述でもお伝えした通り、オウンドメディアへの流入の多くはGoogleやYahooからの検索結果からです。検索結果は日々更新されるため、ファンを獲得するには良質なコンテンツの更新だけでなく検索結果で上位表示させるためのSEO対策も大変重要になります。
オウンドメディア運営のサポートについては、Mattrz(マターズ)までお問い合わせください。
https://mattrz.co.jp/
Writer

時代と人にフィットしたテクノロジーで、企業のコアを作る「人」に寄り添ったソリューションを提供する会社。「Kurashi-no」「folk」「BELCY」等メディアの運営や、CROプラットフォーム「MATTRZ CX」及びSEO対策CMS「MATTRZ Base」の開発・運営を行う。
このライターの記事を読む >おすすめの記事

対談記事【ビジネスのヒント】|接骨院から建設業へ。驚きの経歴と経緯
経営に関する悩みや課題を抱える事業経営者の皆さまにとって、銀行の営業担当者は心強いサポーターの一人です。そこで、リニュー編集部では、事業経営者と西日本シティ銀行の営業担当者にスポットをあててインタビュー。サポートのきっかけや、事業の成功までの道のりなどをざっくばらんにお話しいただきます。

【今月のZero-Ten Park】株式会社ストリ|心と体に美しさと健やかさを
福岡を中心に世界5カ国15拠点を展開するシェアオフィス&コワーキングスペース「Zero-Ten Park」。そこに入居している、今注目したい企業をピックアップ。今回は「株式会社ストリ」をご紹介します。

働き方改革に注力している企業ってどんなところ?|次世代ワークスタイル応援私募債「ミライへの路」
これから就職先を探している学生のみなさんにとって、どんな企業が自分にとって働きやすいのか、気になりますよね。そこで今回は、西日本シティ銀行が取り扱う次世代ワークスタイル応援私募債『ミライへの路*』を発行している企業のみなさんにご協力をいただき、その企業で実際に働いている若手の社員に直撃インタビュー。なぜ入社を決めたのか、実際に働いてみてどんな感じなのか、などをヒアリングしました。また、併せて、各企業の経営者にも、求める人材像や今後の展望などをお話しいただきました。取材に協力いただいた企業は、地元・福岡で働き方改革に注力している、優良企業ばかりです。ぜひ、就職希望先の候補の一つとして、働く先輩たちのリアルな声をご一読ください。

【ミライへの路に挑む企業】地球を守り働く人の成長を支える環境調査会社|株式会社ENJEC
多様な生き方や働き方が広がりつつある現代。企業にはこれからますます、さまざまな人が働きやすい環境を整えることが求められます。社員の働きやすさを叶える企業の取り組みとは?この連載では、実際に働き方改革を積極的に取り組む企業で働く人や経営者にインタビュー。今回は、九州を中心に、水質、大気、土壌といった環境にまつわる調査・分析の事業を手がける、福岡市の株式会社ENJEC(エンジェック)に取材しました。

質の高い人材紹介サービスで、企業も求職者も従業員も幸せに |株式会社GR8キャリア 小畑和貴さん
医療・福祉業界の人材紹介サービスをメインに事業展開する株式会社GR8(グレイト)キャリア。代表の小畑和貴さんは宮城県出身で福岡に移住し、住宅メーカーから人材紹介業界に転職したという異色のキャリアの持ち主です。創業から1年足らずでメンバーは20人ほどに増え、順調な滑り出しといえます。しかし、組織や利益の拡大は求めず、あくまでも「質の高いサービス提供」と「社員とその家族が笑顔で過ごせること」にこだわり続けたいという小畑さんに、その思いの根源や起業のストーリーを聞きました。

番組・動画制作から拠点の運営まで、幅広い事業を展開|株式会社move on.e 岩谷直生さん
20歳から放送局の番組制作に関わり、個人事業主を経て、41歳で番組と動画制作を主軸にした株式会社move on.eを設立した岩谷直生さん。長年のディレクター経験を生かして、マスメディアの番組やイベントを手掛ける一方で、子どもに向けた全く新しい事業にも意欲的にチャレンジしています。

【事業継続力強化計画認定制度】概要や認定のメリット、申請支援事業も紹介
近年、地震や台風などの自然災害、感染症の流行など、企業経営を取り巻くリスクが多様化しています。 こうした中で注目されているのが、災害や緊急事態に備えて事業を継続できる体制を整える「事業継続力強化計画(BCP)」です。 この計画の認定を受けることで、補助金申請時の加点や税制優遇など、さまざまなメリットがあります。 そこでこの記事では、事業継続力強化計画認定制度の概要や認定メリットに加えて、計画策定・申請を支援する取り組みについても解説します。

【中小企業必見】最低賃金引上げに伴う負担軽減策とは?福岡県の支援策も紹介
令和7年度の最低賃金引上げにより、全国的に人件費の負担が増加しています。特に中小企業や小規模事業者にとっては、賃上げへの対応が経営上の大きな課題となっています。 こうした状況を受け、国や自治体では、最低賃金の引上げに伴う事業者の負担を軽減するため、各種支援策を打ち出しています。 この記事では、最低賃金引上げに対応するための国の主な支援策に加え、福岡県独自の支援制度について解説します。


