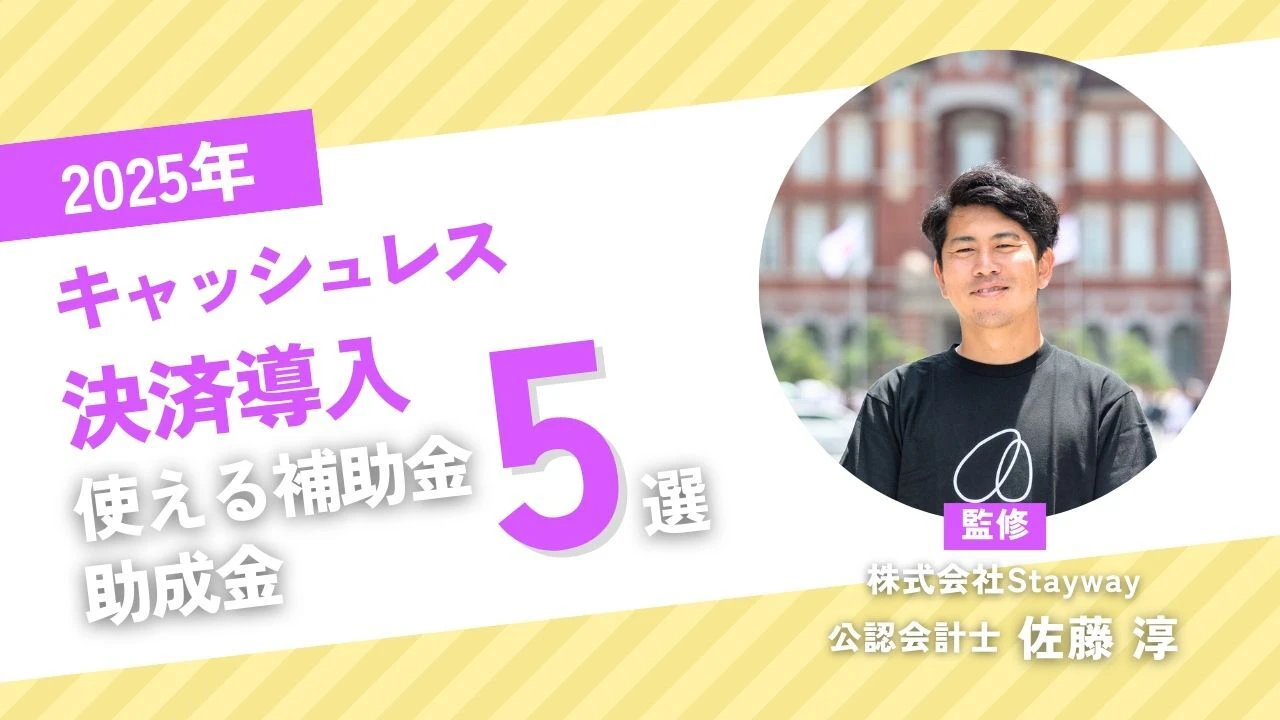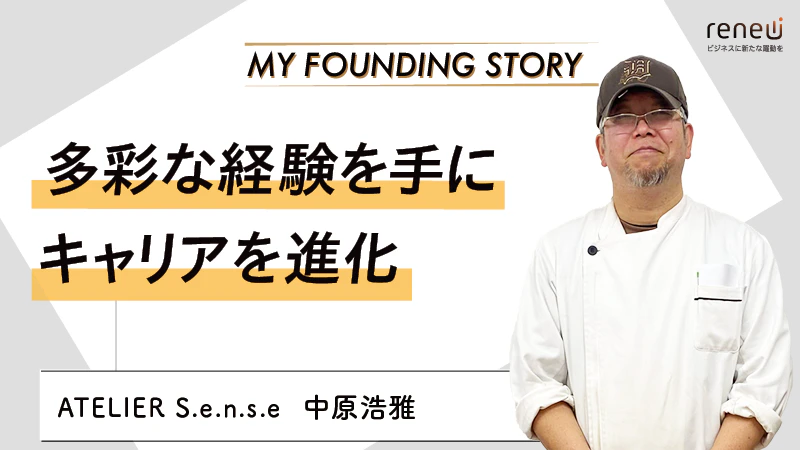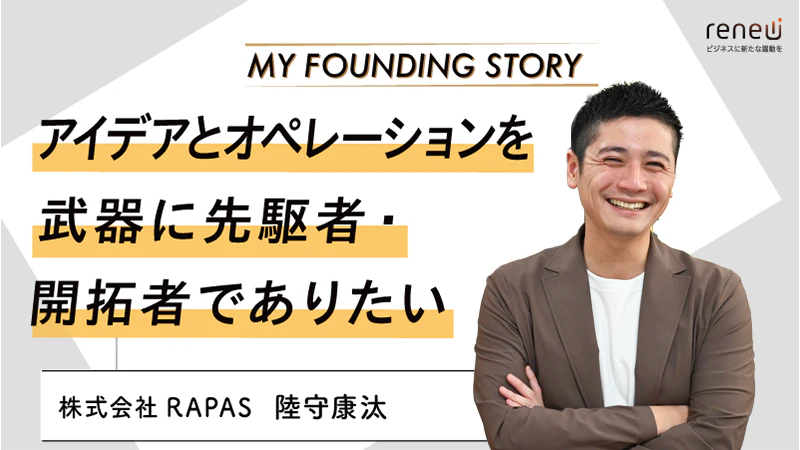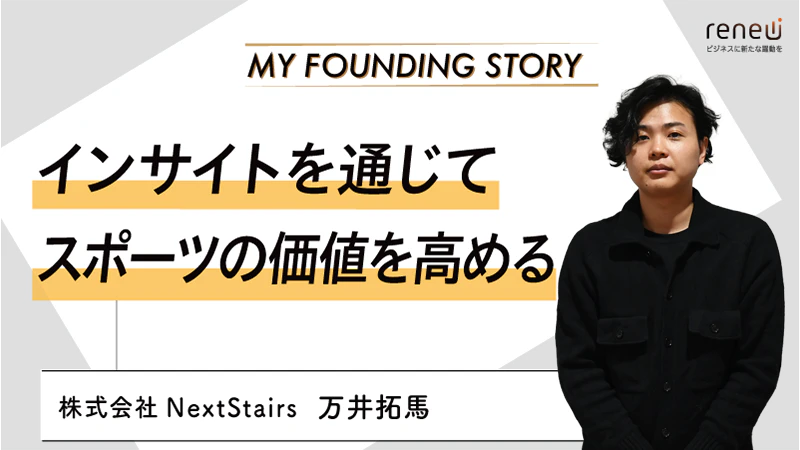競争が激化している飲食業界において、いかに効果的な集客戦略をとるかが大きな分かれ道です。近年ではテイクアウトのニーズが高まり、「Paymul(ペイマル)」をはじめとするテイクアウト予約システムの導入が成功につながる事例もあります。飲食店の集客施策について、最新情報をご紹介します。
現状を見直し売り上げアップを
世の中と同様に、飲食業界のトレンドや集客スタイルも常に変化しています。特に集客においてはライフスタイルが多様化していることもあり、今までと同じ手法だけでは効果が出ないケースが増えてきました。
集客を考えるときに押さえておきたいこと
飲食店の集客について取り組む際、感覚的なものばかりに頼るとうまくいきません。さまざまな角度から客観的に現状を把握し、そのお店なりの理論を立てて取り組むことが大切です。
飲食店における「集客」の基本構造
まず、飲食店の集客を考えるときの土台となる基本構造について確認しておきましょう。
- より多くの新規顧客を集め、その中からリピーターを増やす。
- 顧客ひとりあたりの来店頻度・客単価を上げる。
これらを常に並行して行うことが、ベースになります。1項目だけ成果を上げられたとしても、もう一方が弱いと一時的なもので終わってしまいます。このふたつをうまく循環させることがポイントです。
立地条件と顧客のウォンツを再確認
以下のような立地条件によって、利用者層が絞れます。
- 企業が多いエリアにある
- ショッピング街、住宅地の近隣にある
- 道路に面している
- ビルの上層階にある
- 地下にある
そのうえであらためて、顧客が飲食店に対して何を欲しているのか分析しましょう。たとえばランチの場合、会社の昼休みに利用するのか、友人とゆっくりしたいのかなどお店のジャンルと立地条件によりある程度絞られます。
立地と顧客のウォンツをしっかり確認しておくことは、集客戦略を立てるのにとても重要です。
集客・販促費はどの飲食店でも必要な時代に
どんなに立地がよくても周辺に競合店がない状況でも、何らかの集客アクションが必要な時代になっています。
人が食事をとるタイミングは原則、朝・昼・夜の3回がメインです。また人口の減少やリモートワーク・在宅ワークの増加といった、ライフスタイルの変化も考慮しなければなりません。
飲食店同士の競争が激化している
特に飲食業界は新規参入も多く、開業率が高いといわれています。その分、競争が激しく、廃業率も高くなっています。
また近年は、自宅で食事する人が増えています。店内飲食のみ提供していたお店がテイクアウトやデリバリーサービスを相次いで導入し、新たな集客スタイルを生み出しつつあります。競合はもはや近隣店舗だけでなく、より広い範囲・多店舗に及んでいます。
コストパフォーマンスを考えた戦略が必要
集客にかけられるコストには限りがあります。値上げしにくい状況が続いている一方、食材の価格はじわじわと上がっています。費用対効果の高い集客方法を行うために、マーケティングにも独自の工夫が必要です。
チラシや看板などアナログなアプローチが中心だった以前と比べ、近年は無料〜安価で利用できるデジタルツールが増えています。新たなツールをうまく取り入れることで、適切なコストで集客を目指せます。
認知度を上げるための代表的な発信ツール
飲食店の集客戦略で大前提となるのは、自分のお店を顧客ターゲットに知ってもらうことです。そのための情報発信に有効なツールを、以下にまとめました。
アナログツール
アナログな方法は、おもにインターネットをあまり利用しない紙媒体に慣れている層へ働きかけるのに有効です。
チラシ・DM
店頭や駅前などでの手渡し配布、個人宅や会社へのポスティング、繁華街などに設置されたラックでの配布を行います。また、新聞に折り込みチラシを入れる方法もあります。それなりの枚数を印刷・配布しないと効果が出にくく、コストの考慮が必要です。
看板・のぼり
店舗前や周辺地域の駅前、道路沿いや電柱などに設置します。主にお店の認知度を高めるのに効果的な方法です。デザインを工夫すれば、お店のコンセプトを伝えられます。一方、メニューやサービスに関する詳細な情報は掲載できず、内容の更新がしにくいツールです。
テレビCM・紙媒体広告
テレビや新聞、雑誌などに広告を出す方法です。直接的な来店動機をうながすというよりは、お店の存在を多くの人に伝え認知度を高めるツールです。イメージキャラクターを採用すればより話題性が増して集客につながりますが、コストや制作工程がかかる側面もあります。
デジタルツール
近年、多彩なデジタルツールが登場しています。インターネットでの集客も効果的です。

マップ
スマートフォンの地図アプリからお店を検索する、という人が増えています。検索結果には営業時間やメニュー、店内や料理の写真、口コミなどが掲載されており、これらをもとに予約・来店するのです。情報は店舗側も掲載・編集でき、無料で利用できるサービスもあります。
SNS
タイムリーな情報をいち早く伝えられるのが、SNSの特徴です。SNSでキーワードや画像を検索して、お店を決めるという人も多いです。無料で利用できるので参入しやすいですが競合も多く、お店ならではの特徴を出した情報発信が求められます。こまめに投稿することも大切です。
ホームページ
マップやSNSを入り口として、詳細を知りたいときにチェックするのがホームページです。自由に情報を更新でき、多彩なデザイン・構成でお店のカラーを出せます。SNSより更新頻度は少なくて構いませんが、放置しすぎるとかえってお店の印象が下がってしまうので注意が必要です。
インターネット広告
SNSやインターネットサイト、Webメディアなどに広告を出稿します。飲食店の予約情報サイトに登録することで、広告効果を得るという方法もあります。お店の顧客ターゲットと合致するメディアで出稿すれば集客につながりますが、コストが発生する場合は費用対効果を意識する必要があります。
重要なのは「掛け合わせ」。顧客を増やす効果的な方法
ここまでご紹介した主な集客ツールを活用するためにはどうすればよいか、順を追って見ていきましょう。

1)顧客が求めるサービスを再構築
立地条件や顧客のウォンツを把握し、それに合うサービス体制をつくります。お店のコンセプトと照らし合わせながら、ひとつずつ確認していきましょう。
看板メニューや価格帯の見直し
お店の顔となる看板メニューは、新規顧客とリピーターの獲得に大きな役割を果たします。「あのお店の看板メニューはおいしい」とひとつのメニューに話題を集めることで来店者数を増やし、お店の味を体験してもらうことが大切です。これは、口コミを広げるという集客戦略です。
看板メニューは、味のよさだけでなく価格も重要になります。プライシングにもさまざまな手法がありますが、顧客が迷わずオーダーしやすい設定にしましょう。そのためにはやはり、「立地条件」「顧客のウォンツ」がポイントになります。
テイクアウト・デリバリーサービスへの参入
近年需要が拡大しているテイクアウトやデリバリーサービスに参入するという方法もあります。これまで囲いきれなかった、新たな顧客を取り込むチャンスでもあります。
テイクアウトや宅配のメニューがあれば、「本当はお店に行きたいけれど少し遠くていけない」「子どもがいて外食はできないけれど、お店の料理が食べたい」というニーズに対応できます。お店が人手不足の場合でも、比較的少人数で対応しやすいというメリットもあります。

2)各種ツールの登録・活用
スマホユーザーの増加とオンラインサービスの充実により、普段顧客が使っているアプリやシステムを使えるお店かどうかが重視されるようになっています。この先のことを考えて早いうちに導入し、お店の売りのひとつにしておくことが求められます。
キャッシュレス決済システム
現金ではなく、クレジットカードやスマートフォンのアプリから支払いを行うキャッシュレス決済が、日本でも浸透しつつあります。政府がキャッシュレス決済を推し進めていることもあり、今後ますます利用者が増えることが予想されます。
決済システムは数多くリリースされており競争が激化しているため、運用コストは以前と比べて多少抑えられていますが、条件はしっかりと確認するべきです。
テイクアウト予約システム
テイクアウトサービスをよりスムーズに提供できる、テイクアウト予約システムも登場しています。オンラインでお店の検索とメニューの閲覧、注文受付、決済まで行えるので、人手がかからず顧客も利用しやすいというメリットがあります。
導入や運用のコストとサービス運営の円滑さを比較し、システム導入を選ぶお店が最近増えているのです。
テイクアウト予約システム「Paymul(ペイマル)」の場合、導入コストはかからず決済手数料が5%とコストを大幅に抑えた運用が可能になっています。全国の飲食店で利用でき、集客の費用対効果が高いのが魅力です。
手数料が低い! テイクアウト予約システム「Paymul(ペイマル)」のご紹介
3)デジタルツールを活用した集客活動
来店が見込める顧客にお店を認知してもらわなければ、集客活動の意味がありません。インターネットで検索してお店を選ぶ時代では、情報発信の意図を明確にしてデジタルツールを選ぶ必要があります。
エリアに特化した検索サイトを活用
来店につながる集客には、お店にアクセスできるエリアへの情報発信を重点的に行うことが効果的です。そのために、ある特定のエリアに特化した検索サイトを利用するという方法があります。写真や情報量が多いとより上位に検索表示され、口コミ数が多ければその分、情報の信頼度が高まります。
グルメサイトへの登録
飲食店の情報を掲載する、グルメサイトへ登録する方法もあります。よく知られたサイトであれば、ユーザーの目に留まりやすくなるでしょう。ただし、サイト内で上位に表示されるためには各種有料プランに加入しなければならず、コストと効果のバランスを考える必要があります。
4)各種ツールを掛け合わせて顧客を増やす
アナログとデジタルの両輪で集客し、顧客を巻き込みながら来店数増加を目指すというマーケティング手法も増えています。その一例を紹介します。
チラシ×SNS
チラシを配布し、割引券をつけたりSNSのフォローを促したりします。SNS上でキャンペーンを行うのも有効でしょう。
この方法は配布エリアの見込み客属性が把握でき、次の集客戦略を立てるのに役立ちます。「アナログなアプローチが有効な地域か」「デジタル世代に刺さる施策が必要か」など、見えてくるものがあります。
テレビ×SNS
テレビCMや番組の特集コーナーなどに取り上げてもらい、そこでSNSキャンペーンの告知をします。たとえば、ハッシュタグをつけてコメントを投稿すると割引券やプレゼントがもらえるなどの特典を用意します。
店舗情報を見てもらうだけでなく、負担にならない程度のアクションを直後〜近日中に起こしてもらうことで印象に残りやすく、インターネット上で情報が拡散される効果もあります。
5)協力者を増やす
できるだけ多くの人にお店を知ってもらうために、ファンや協力者を増やすことも大切です。特に口コミは、アナログ・デジタルともに最も重要な情報といっても過言ではありません。

SNSによる拡散
フォローやリツイート、Likeをいかにしてもらえるかが勝負所になります。お店のSNSは大切な資産であり、集客ツールです。定期的な更新と、思わず「いいね!」したくなる内容をアップする努力は必要になりますが、その分、反応があったときの効果は大きいです。
デジタル世代である若年層の従業員やアルバイトに情報発信を協力してもらうのもよいでしょう。SNS担当に任命する、投稿する写真の撮影をお願いすることで顧客ターゲットの心に刺さるSNS運営がしやすくなるかもしれません。
口コミやアンケートの協力をお願いする
来店した顧客に口コミやアンケートを依頼するのも、効果的です。実際に訪れたことのある顧客の生の声は、インターネットにおいても職場や友人関係の間においても重要度の高い情報として認知されます。
さらに口コミを発信した人が著名人やインフルエンサー、自分の信頼している身近な友人知人であればなおさらその情報の信用度が上がり、お店への訪問意欲が高まります。そのためにはやはり、顧客との良好な関係が必要です。
まとめ
西日本シティ銀行ではこれまで、NCBアプリや公式SNS、自社メディアを通じて地域の飲食店を紹介してきました。またテイクアウト予約システムの「Paymul(ペイマル)」についてもご案内が可能ですので、新しい取り組みとして感心のある飲食店事業者の方々は是非お問い合わせください。
使えるツールをうまく掛け合わせながら、効果的な集客を目指しましょう。
「ペイマル」資料請求はこちら