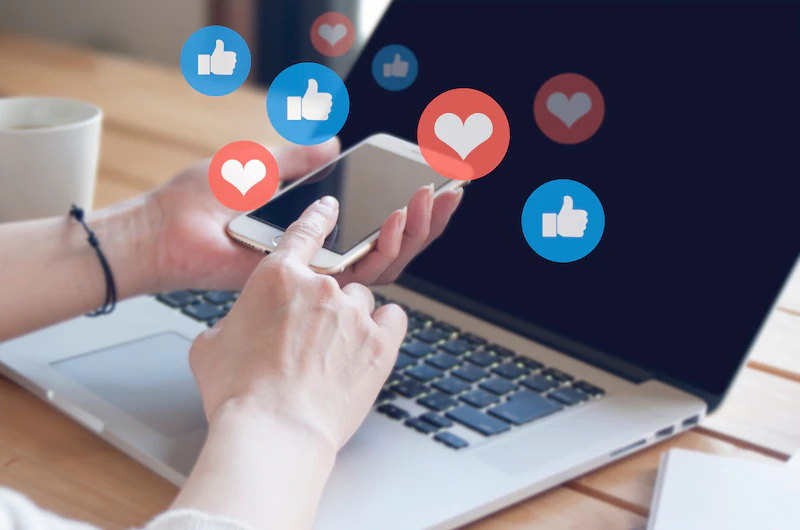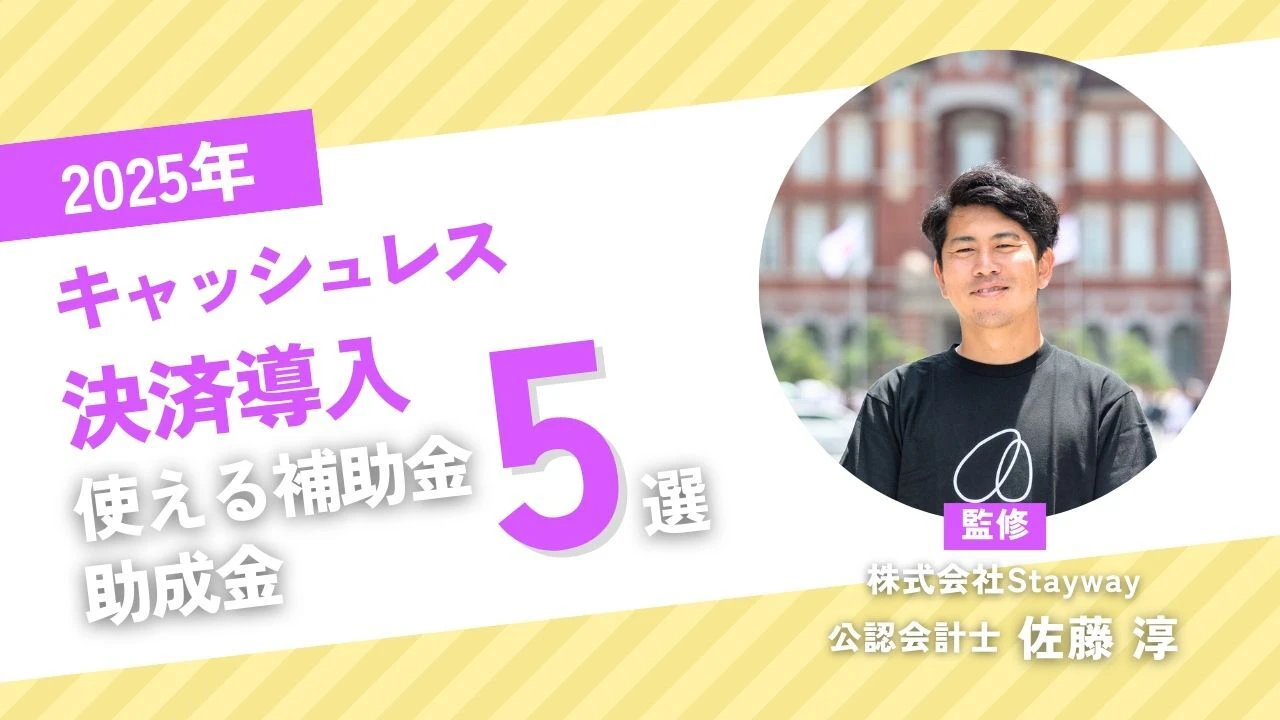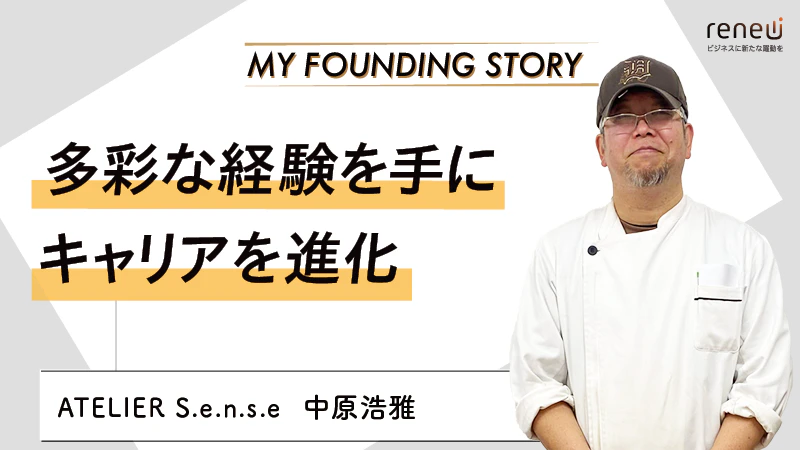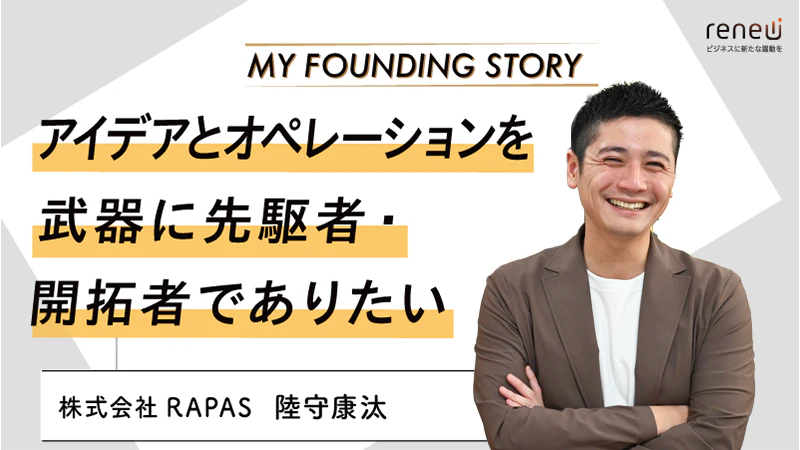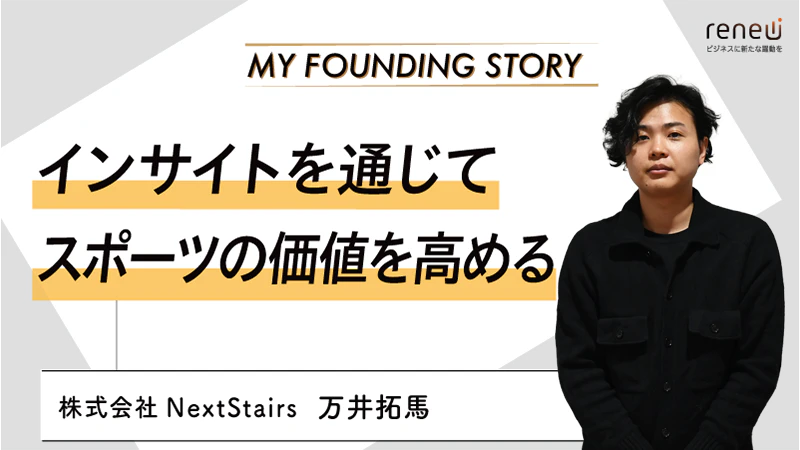コロナ禍で、売上に大きな影響を受けている飲食業界。少しでも売上向上を図ろうと新しい取り組みをはじめられるところも増えています。本記事では売上向上を図る際に必要な基本的な3原則についてご紹介します。
飲食店の経営を改善する方法とは?
飲食店の経営を向上させるには、売上を増やさなければなりません。まずは、飲食店の売上を管理するために知っておきたい基礎知識を確認しておきましょう。
飲食店の売上を決める基本的な要素
飲食店の売上高は、次の計算式で決まります。
売上高(円)=客数×客単価
飲食店の売上を向上させるには、客数を増やして客単価を上げなければなりません。たとえ客単価が上がっても、客数が減ってしまうと売上が減ることがあります。利益向上のために、客数と客単価の両方を増やすことを意識しましょう。
客数を増やすには?
新規顧客を獲得する方法と、リピーターを増やす方法があります。これまでと同じ集客方法だけを続けていても、顧客拡大は困難です。新しい集客方法にチャレンジしましょう。
客単価を増やすには?
単純に、料金を値上げすれば客単価は上がります。ただし、値上げによって顧客が離れることも考えられるため、値上げは慎重に判断しましょう。コストを抑える工夫も必要です。
売上を向上させる3つの方法
客数を増やして客単価を上げるためには、さまざまな方法が考えられます。ここでは、売上向上の3原則をお伝えします。
- コンセプトの明確化
- 集客チャネルの拡大
- FLコストの管理
以下、それぞれの原則について詳しく説明します。
その1|コンセプトを明確にして新メニューを開発
飲食店のコンセプトとは、お店のテーマや方向性です。お店のコンセプトを明確にすれば、客数を増やし、客単価を上げる策が見えてきます。

飲食店はコンセプトが重要
飲食店を利用するときには、単に和食、中華、イタリアンといったジャンルだけで選ばないでしょう。飲食店には、高級店もあれば、カジュアルで大衆向けのお店もあります。飲食店を利用する人は、シチュエーションに合ったお店を選びます。顧客に選ばれる飲食店になるためには、お店のコンセプトをはっきりさせる必要があります。コンセプトを明確にせず、あらゆる場面であらゆる人に来てもらいたいと考えていると、結局誰にも選ばれません。
コンセプト作りは5W1Hで
売上アップを考えるなら、お店のコンセプトを見直してみましょう。「いつ(When)」「どこで(Where)」「誰に(Who)」「何を(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」の5W1Hからコンセプト作りをするのがおすすめです。それぞれの業種で顧客に求められているニーズを把握しつつ、オリジナリティのあるコンセプトを作りましょう。
居心地のよい空間を作る
コンセプトに合ったお店は、顧客にとって居心地のよい空間です。食事が終わっても、ドリンクを注文してくつろぎたいと思う顧客が増えれば、客単価も上がるでしょう。何度も来店したいと思うリピーターの割合が増えれば、集客も楽になります。
ターゲットの明確化
お店のコンセプト作りは、「誰に」というターゲットを明確にすることから始めましょう。どんな人にお店に来てもらいたいか、明確になっているでしょうか。たとえば、ダイエットを意識している若い女性と満腹感を重視するサラリーマンをターゲットにするのでは、メニュー構成やお店の雰囲作りが変わってきます。ターゲットを明確にし、メニューやお店の内装を見直しましょう。
期間限定メニューを工夫する
期間限定メニューには、集客効果が期待できます。期間限定メニューは、「今しか食べられない」ところに価値がある特別感が魅力なので、顧客を呼び寄せる効果があります。ただし、どんなメニューでも顧客にアピールできるわけではありません。お店のコンセプトに合ったメニューを用意しましょう。
季節感のあるメニューがおすすめ
期間限定メニューは、季節に合ったものにするのがおすすめです。旬の食材を取り入れた季節限定メニューなら、新鮮さもアピールできます。月替わりで限定メニューを用意すれば、毎月来ようと思う顧客が増えます。
その2|集客チャネルを拡大して認知度アップ
客数を増やして売上向上を図るには、従来のアナログな集客方法だけでは困難です。現在は多くの方がスマートフォンを持ち、インターネットを活用して情報を収集しています。時代に合った集客チャネルを持ちましょう。
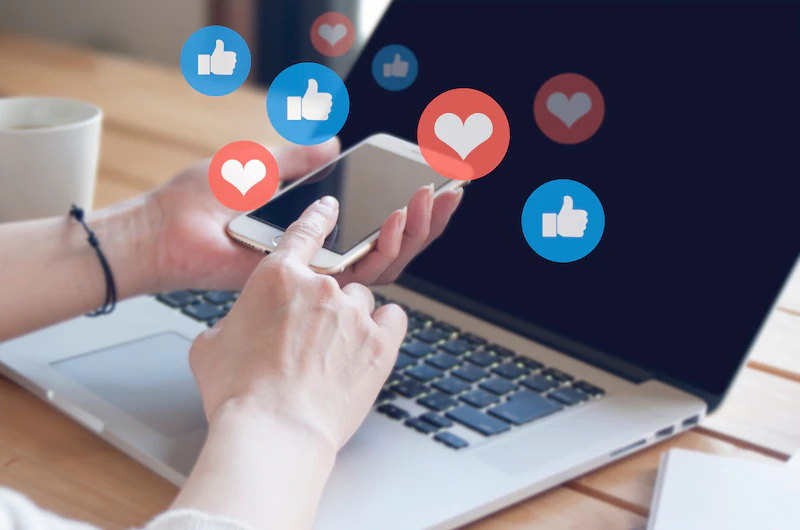
SNSを活用
インターネットを利用し費用をかけずに集客する方法として、SNSはぜひ活用したいものの一つです。
SNSにユーザーの興味を引く情報を掲載すれば、ユーザーがその情報を勝手に拡散してくれます。SNSをきっかけに、想定してなかった年齢層や遠方からの来店があれば、思わぬニーズに気付くかもしれません。
日常的な発信でお店のコンセプトを伝える
SNSを利用すれば、お店のコンセプトを伝えてファンを増やせます。SNSでは、単に発信の頻度を上げればよいわけではありません。お店らしさがわかる一貫性のある情報を伝え続けることで、「ここに行ってみたい」「自分にピッタリのお店だ」と感じる人が増えます。料理の写真を美しく撮影し、お店や料理の魅力、こだわりを伝える紹介文を書きましょう。
グルメサイトに登録
インターネット上には、地域別に飲食店の情報を集めたグルメポータルサイトがあります。こうしたグルメサイトに登録すれば、検索によりユーザーに見つけてもらえる可能性が広がります。グルメサイトに情報を載せてもらうには、掲載料がかかるのが一般的です。費用をかける場合には、料金に見合った効果があるかを検討しましょう。
デリバリーの導入も検討
コロナ禍における緊急事態宣言の影響で、飲食店のデリバリーを利用する人が増えました。デリバリーを開始すれば、顧客の目に留まりやすくなり、売上アップにつながります。これまでお店を知らなかった人も、デリバリー利用をきっかけに、お店に食べに来てくれるかもしれません。

テイクアウトもおすすめ
コロナ禍により、飲食店のテイクアウトを利用する人も増加しました。それまで来店の経験がなかった人も、テイクアウトをきっかけに来店してくれることもあります。テイクアウト予約システムに登録すれば、広範囲のユーザーにお店のPRができます。
【資料請求】テイクアウトオーダーシステム
その3|FLコストを管理して利益向上
FLコストは、飲食店で最も重視すべき指標の一つです。FLコストを見直して支出を適切に管理すれば、利益を伸ばせます。
飲食店でかかる主な経費
FLコストのFは「Food(食材)」、Lは「Labor(労働)」です。飲食店でかかるコストの大部分は、食材の原価である材料費と労働の対価である人件費に集約されます。FLコストとは材料費と人件費の合計で、売上高に占めるFLコストの割合をFL比率といいます。利益向上のために、FL比率の改善を意識しましょう。
FLコストの適正値はどれくらい?
一般的な飲食店のFL比率は55~65%ですが、理想のFL比率は50%程度といわれます。高い利益を出している超優良店では、食材費、人件費を上手にコントロールし、50%以下に抑えています。

利益率を改善する方法
FL比率を下げて利益率を上げるために、次のような点を意識しておきましょう。
Fコストの改善
材料費を抑えるには、食材ロスを減らすのが有効です。安く材料を仕入れ、できるだけ無駄のないように使いましょう。仕入先や仕入れの量を見直す、材料を共有できるメニュー構成にするなどの方法があります。
Lコストの改善
一日の間で顧客が集中する時間帯は、決まっていることが多いはずです。顧客が少ない時間帯に多くのスタッフを配置しないよう、シフトを見直しましょう。タブレットによる注文システムなどITの活用によっても、人件費を削減できます。
まとめ
飲食店の売上向上のために、コンセプトの明確化、集客チャネルの拡大、FLコストの管理を意識しましょう。テイクアウトの導入も、有効な集客方法です。テイクアウト予約システム「Paymul(ペイマル)」は、飲食店のテイクアウトをサポートするシステムです。この機会にぜひ利用してみてください。
手数料が低い!テイクアウト予約システム「Paymul(ペイマル)」のご紹介
AFP(日本FP協会認定)、行政書士、夫婦カウンセラー
大学卒業後、複数の法律事務所に勤務。30代で結婚、出産した後、5年間の専業主婦経験を経て仕事復帰。現在はAFP、行政書士、夫婦カウンセラーとして活動中。夫婦問題に悩む幅広い世代の男女にカウンセリングを行っており、離婚を考える人には手続きのサポート、生活設計や子育てについてのアドバイス、自分らしい生き方を見つけるコーチングを行っている。
このライターの記事を読む >