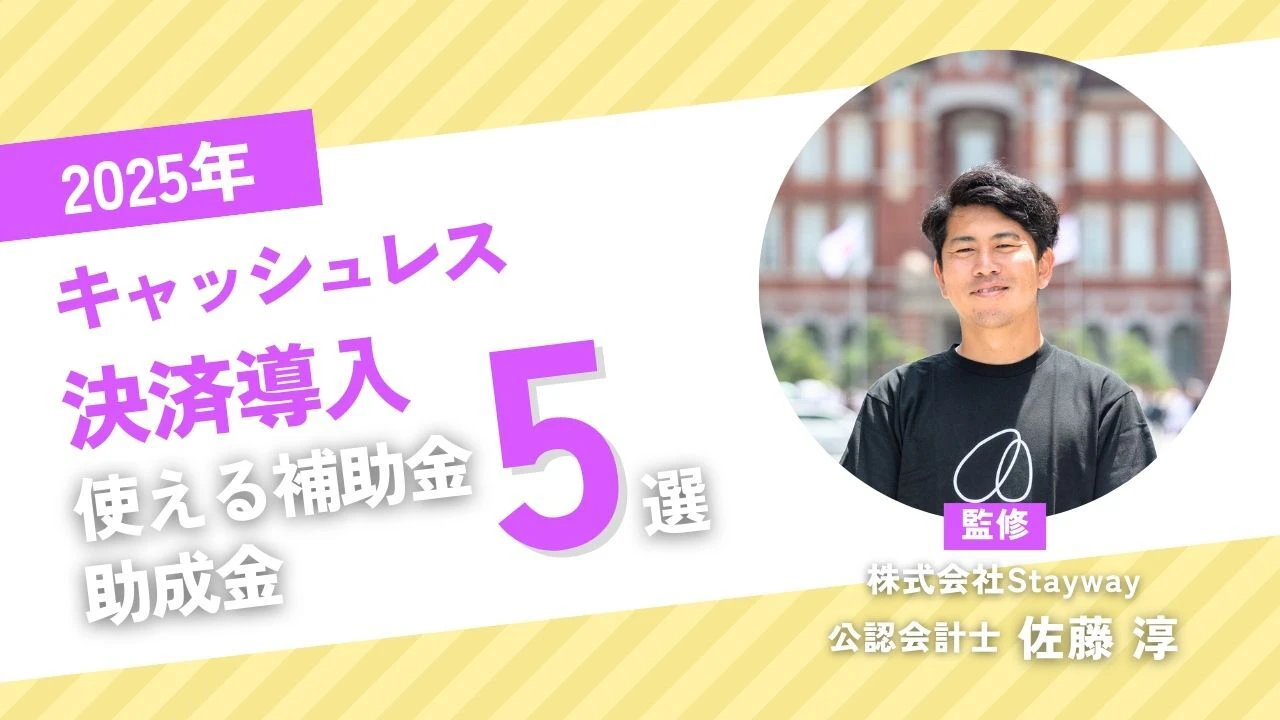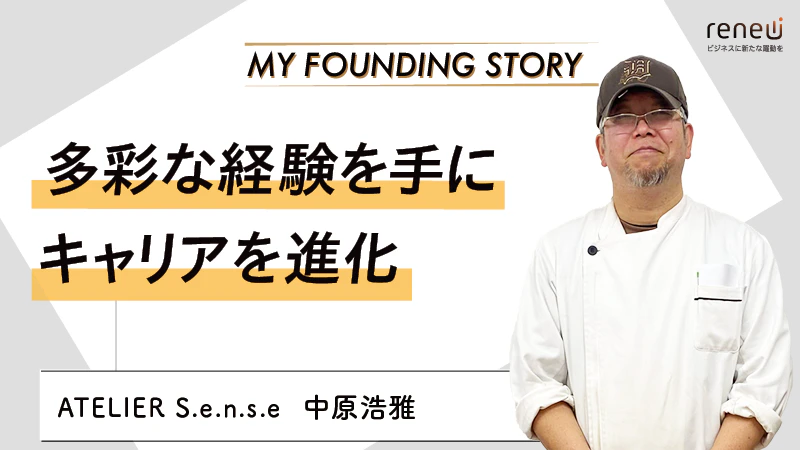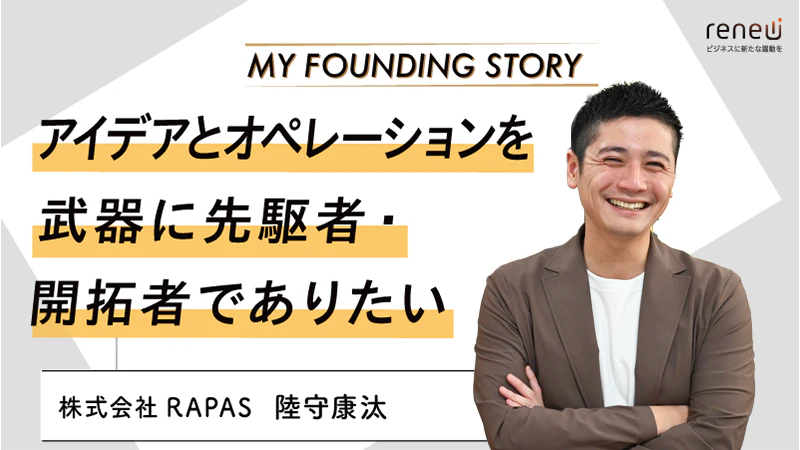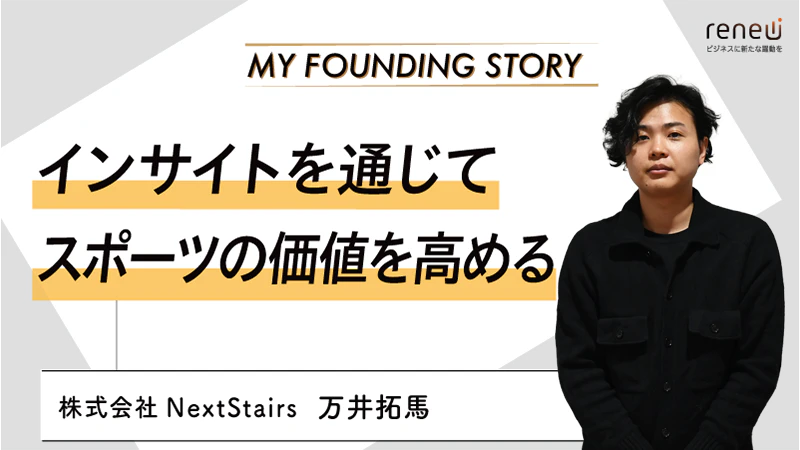コロナ禍により飲食店のテイクアウトやデリバリーサービスの導入が増えています。今回は、飲食店がテイクアウトを開始するとき、必要な準備や注意しておきたい点を説明します。テイクアウトを導入する前にぜひ一度ご覧ください。
テイクアウトで飲食店の売上をアップさせよう
飲食店のメニューを自宅にいながらでも手軽に楽しめるのが、テイクアウトの魅力。ユーザーのニーズが増えている今、テイクアウトの導入を考えてみましょう。
コロナ禍で急増したテイクアウト需要
飲食店のテイクアウト需要は、2019年(令和元年)10月の消費税引き上げ・軽減税率導入以降高まりの兆しを見せるようになりました。店内での飲食には消費税10%が課されますが、テイクアウト商品は軽減税率の8%に抑えられたためです。さらに、2020年(令和2年)から2021年(令和3年)にかけて、コロナ禍における緊急事態宣言の影響で、テイクアウト需要が急増しました。多くの人が、家にいながらでもお店の味を楽しめるテイクアウトに注目するようになったのです。
8割の人がテイクアウトの利用経験あり
日本政策金融公庫が2020年(令和2年)10月に20~69歳の男女2,000人を対象に行ったアンケート調査によると、飲食店のテイクアウトを利用したことがある人は78.3%、うち月に1回以上利用する人は58.2%となっています。また、テイクアウト利用者のコロナ収束後の利用意向は「増えると思う」が24.0%、「変わらないと思う」が59.7%です。テイクアウトが、当たり前の楽しみ方として浸透してきたのがわかります。
参考:2020年10月 飲食店のテイクアウト・デリバリーサービス等に関する消費者調査結果
飲食店がテイクアウトを始めるメリット
緊急事態宣言下での時短営業要請により通常営業ができない状況が続き、売上が大きく減少した飲食店も多いのではないでしょうか。飲食店がテイクアウトを導入するメリットは、次のような点です。
座席数・回転数に関係なく売上を増やせる
飲食店の売上向上のためには、座席数を増やして回転数を上げる必要があります。座席数を増やしたり回転数を上げたりするのは、簡単ではないでしょう。テイクアウトの場合、座席は不要で席の回転数を気にする必要もありません。テイクアウトを導入すれば、限られたスペースでも売上を大きく伸ばせる可能性があります。
人件費を抑えられる
テイクアウト販売を行う際には、料理を運んだり食器を洗ったりする手間がかかりません。テイクアウトという形で販売する商品を増やしても、新たにスタッフを追加する必要はないことも多いでしょう。人件費を抑えた運営ができるので、利益率が向上します。
お店の認知度が上がる
テイクアウト商品を購入した顧客は商品を持ち帰った後、いろいろな場所で食べることになります。これにより、お店を知らなかった人がテイクアウト商品を目にする機会も増えることが予想されます。つまり、テイクアウトには宣伝効果が期待できるのです。これまで知らなかった人にも、お店の存在やメニューを知ってもらうチャンスが作れます。
イートインにつなげられる
店内で飲食したことがない顧客にとって、テイクアウトはお店のメニューを気軽に体験できるチャンスとなります。テイクアウトでお店の味を気に入れば、今度は食べに来てもらえるでしょう。テイクアウト商品と一緒にお店のチラシや割引券を渡せば、販売促進につながります。
配達にも対応できればより効果的
テイクアウトと並んで多くの人が利用するようになったのが、デリバリーです。お店まで行けない人や買いに行くのが面倒な人にとっては、家まで配達してもらえるデリバリーは嬉しいサービスでしょう。配送スタッフを確保できなくても、配達専門の外部サービスと提携する方法があります。デリバリーへの対応も、検討するのがおすすめです。
テイクアウト開始時の対策と注意点
テイクアウトが売上アップに有効なことはわかっていても、いざ導入するとなると不安を感じるかもしれません。テイクアウトは意外に簡単に始められます。テイクアウトを始めるときの対策や注意点を説明しますので、導入を前向きに検討してみましょう。

新たな許可の要否を確認
飲食店には、さまざまな規制が設けられています。飲食店を開業するときには保健所の許可を得ているはずですが、場合によっては新たな許可や届出が必要なケースもあります。テイクアウトの内容を考えるときには、許可の要否についても確認しておきましょう。
専用の容器を手配
テイクアウトでは、持ち帰り専用の容器が必要になります。せっかくテイクアウト用の料理を準備していても、途中で容器が足りなくなれば販売できません。テイクアウトの計画を立てるときには1日の販売数を決めて、不足しないよう容器を確保しておきましょう。
テイクアウト用容器の条件
テイクアウトに使う容器は、食材や調理法に合ったものでなければなりません。持ち運び時に、具材や水分がこぼれやすいものでは困ります。温めて食べるものなら、電子レンジ対応の容器が必須でしょう。捨てるときのことを考えると、分別のしやすいものが喜ばれます。最近はテイクアウト需要が増え、料理別に持ち運びに便利な容器が多数開発されています。テイクアウト用容器はホームセンターなどでも調達できますが、業務用の資材専門店で相談すると適切なものが手に入りやすいでしょう。
カトラリーや袋も準備
テイクアウト用には容器のほかに、割りばし、スプーン、フォーク、紙ナプキンなども必要です。持ち運び用の袋も用意しておきましょう。
原材料表示が必要な場合がある
食品を販売するときには、食品表示法により原材料や消費期限、内容量などの表示が義務付けられています。店内調理した食品をその場で販売するときには、表示義務はありません。店内販売の場合には、製造者が消費者に直接口頭で品質についての説明ができるからです。これに対し、以下のような場合には表示義務が発生するので注意しておきましょう。
セントラルキッチンで調理する場合
自社工場で調理した料理を店舗で販売するようなケースです。この場合、調理する場所と販売する場所が別になり製造者が消費者に直接説明できないため、原材料などを表示して販売する必要があります。
仕入れた食材を小分けして販売する場合
製造・加工された食材を仕入れて消費者に販売する場合には、表示義務があります。業務用食材を小分けして顧客に販売する場合や、仕入れたお弁当を販売する場合などです。
料理の衛生管理に注意
テイクアウトされた食品は、時間が経ってから食べられる可能性もあります。食中毒のリスクが高くなるため従来の衛生管理に加え、次のような点を意識しておきましょう。
加熱した商品を提供する
鮮魚類などをテイクアウト販売するのは控えましょう。半熟卵やレアなお肉も、テイクアウトには不向きです。食品は中心部までしっかり火を通して提供することが大切です。
注文を受けてから調理
作ったものを長時間置いておくのは避けましょう。食べるまでの時間が短くなるよう、注文を受けてから調理するのがおすすめです。
容器詰めを工夫
食材を容器に詰める前に、水分をよく切りましょう。浅い容器に小分けすると、傷みにくくなります。
食品の温度管理に注意
食中毒菌が増殖しやすいのは、20度〜50度の温度帯です。クーラーボックスや冷蔵庫を使って調理後速やかに冷ますか、温蔵庫を使って保管しましょう。顧客の持ち帰り用に保冷剤を付けると安心です。
すぐに食べるよう告知
出来立てを味わってもらうためにも、顧客にはなるべく早く食べてもらうのがいちばんです。容器に「本日中にお召し上がりください」などのシールを貼るか、口頭で注意喚起しましょう。
テイクアウトに対応できるオペレーションを用意
従来の業務のほかにテイクアウト業務が追加されるとスタッフの対応がうまくいかず、混乱することがあります。テイクアウトを開始する前に、スタッフ全員で作業の流れを確認しておきましょう。イートインとテイクアウトを両立させてスムーズなオペレーションを実現するには、次のような方法が考えられます。
部分別調理をする
作り置きをすると時間の無駄は減りますが、食中毒のリスクが高まってしまいます。仕込み段階で途中まで調理しておき、注文を受けてから仕上げるようにすれば、効率よく料理の提供ができます。
予約販売にする
テイクアウトを事前予約制にすれば、注文をとったり厨房に伝えたりする手間がなくなります。事前にスマホで予約注文できるシステムを利用すれば、便利です。西日本シティ銀行が提供する「Paymul(ペイマル)」は、飲食店向けのテイクアウト予約システムです。テイクアウトにかかる手間を削減できるほか、集客にも役立ちます。
【資料請求】テイクアウトオーダーシステム
テイクアウトで許可が必要な3つのケース
飲食店営業許可にはテイクアウト業務も含まれるため、既に開業している飲食店は新たな許可なしでテイクアウトを開始できます。ただし、以下に説明するように、別途許可が必要になるケースもあります。自治体によって取り扱いが異なることもあるため、詳しくは所轄の保健所に確認してください。

テイクアウト用に新規メニューを追加する場合
店内で提供しているメニューと同じものをテイクアウト販売する場合には、新たに許可を受ける必要はありません。テイクアウト用に新しいメニューを作って提供する場合には許可が必要です。
テイクアウト専門の店舗を開設する場合
現在飲食店を営業している店舗でテイクアウト販売をする場合には、許可は不要です。一方、テイクアウト販売のための新たな店舗を開設する場合には、新たに許可を受ける必要があります。
肉類・菓子・冷凍食品等を提供する場合
テイクアウトで扱う食材の種類や提供方法によって別途許可が必要になることがあります。
肉類・鮮魚類
カットした生肉を包装して焼肉セットとして販売する場合には、食肉販売業の許可が必要です。切り身に加工・包装した鮮魚を鍋セットとして販売する場合には、魚介類販売業の許可を取る必要があります。また、ローストビーフや焼豚などの食肉製品の販売には、食肉製品製造業の許可が必要です。
生麺
自家製の生麺をテイクアウト用に販売するには、麺類製造業の許可が必要になります。
菓子類・アイスクリーム類
手作りのパンやクッキー、ケーキなどの菓子類を販売するには、菓子製造業の許可が必要になります。手作りアイスやソフトクリームを販売する場合は、アイスクリーム類製造業の許可が必要です。なお、食品衛生法の改正により、令和3年(2021年)6月1日以降に飲食店営業の許可を受けている場合には、新たに許可を受ける必要はありません。
冷凍食品
そうざいの冷凍品を販売するには、冷凍食品製造業の許可が必要です。
アルコール類
飲食店で提供しているアルコール類をテイクアウト販売する場合には、酒類小売業免許が必要です。
テイクアウトを成功させるための集客方法
テイクアウトを開始したら、お客さんに来てもらえるよう宣伝を行いましょう。集客を工夫すれば、売上アップが実現します。ここからは、テイクアウト成功に向けた集客対策のコツを説明します。

店頭の貼り紙やのぼり
来店した人の目につきやすいように、店頭や店内に「テイクアウトOK」などの貼り紙やPOPを用しましょう。お店の前にのぼりを立てれば、通行人の目にとまります。店舗周辺でチラシ配りをするのも効果的です。
ポスティングチラシを配布
テイクアウトを利用する人の大部分は、お店から徒歩圏内に住んでいる人です。周辺でチラシをポスティングすれば、近隣の顧客にアピールできます。
アプリやポータルサイトを活用
今は、飲食店もインターネットで検索する人が多くなっています。グルメ情報を探せるアプリやポータルサイトにお店の情報を掲載し、テイクアウトの宣伝をすることも可能です。
おすすめはテイクアウト予約アプリ
テイクアウトができる飲食店を検索し、そのまま注文、決済ができるテイクアウト予約アプリを利用する人は増えています。お店にとっても、テイクアウト予約アプリの導入は集客に役立ちます。事前決済など機能が豊富なアプリを使えば、業務効率化もできるでしょう。テイクアウト予約アプリについて、詳しくは以下の記事をご参照ください。
手数料が低い!テイクアウト予約システム「Paymul(ペイマル)」のご紹介
SNSで宣伝・告知
SNSでお店のアカウントをとって情報発信すると、費用をかけずに多くの人に見てもらえます。SNSなら日替わりメニューの情報も伝えやすく、写真を掲載するのも簡単です。メニューの種類や予約の要否、ラストオーダーの時間など、ユーザーが知りたいと思う情報も記載しておきましょう。
まとめ
テイクアウトを導入すれば、外食できない人にもお店の味を届けられます。新たな顧客層をお店に呼び込むこともでき、売上アップの実現にも有効です。テイクアウト導入の際、スタッフのオペレーションに不安がある場合には、テイクアウト予約システムを活用して効率化を図りましょう。