カーボンニュートラルとは?実現に向けた取り組みや問題点についてわかりやすく解説
By もろふし ゆうこ
|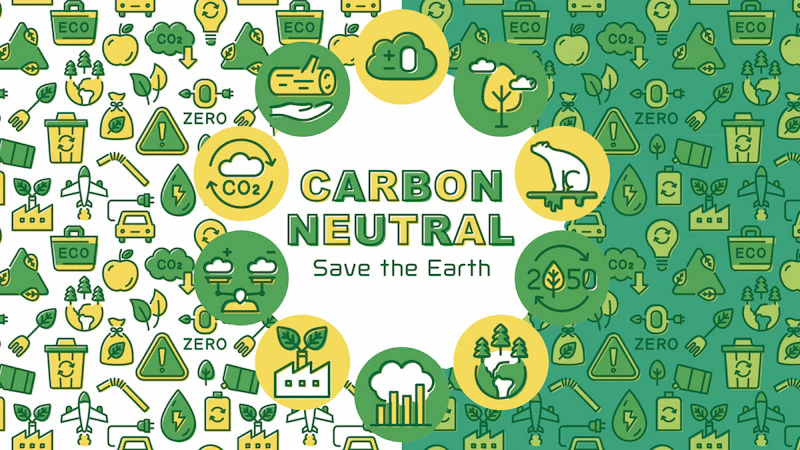
地球温暖化への対策として、カーボンニュートラルの実現が重要視されています。温室効果ガスの排出量と除去率・吸収率を均衡させることで、環境を守る取り組みです。この記事ではカーボンニュートラルの概要やネットゼロ・カーボンオフセットとの違い、課題、企業の取り組み事例を解説します。
カーボンニュートラルとは?意味と取り組みの背景
地球温暖化をどう食い止めるかは、世界中で大きなテーマとなっています。温室効果ガスが環境問題に深く作用しており、どれだけ削減できるかが今後の地球環境を左右します。
しかし、さらなる経済成長を目指すには、インフラ整備や産業発展が不可欠です。従来の方法では、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出は避けられません。
そこで導入されたのが、カーボンニュートラルの仕組みです。
カーボンニュートラルとは
カーボン(carbon)は「炭素」、ニュートラル(neutral)は「中立の」という意味があります。つまりカーボンニュートラルとは、炭素をプラスマイナスゼロの中立状態にすることです。具体的には、温室効果ガスの排出量から除去率・吸収率を均衡させることをカーボンニュートラルと呼びます。
ネットゼロとの違い
カーボンニュートラルと共によく使われるのが「ネットゼロ」という言葉です。ネットゼロとはネット(net・正味)がゼロであること、つまり二酸化炭素の排出量が正味ゼロの状態を指します。
基本的に、ネットゼロとカーボンニュートラルは同義語として使われているのです。厳密にいうと、カーボンニュートラルには排出量と除去率・吸収率が中立しているというニュアンスがあります。一方ネットゼロは、排出量から除去率・吸収率を差し引くと実質ゼロになるという意味合いが強いです。
カーボンオフセットとの違い
カーボンオフセットは、「カーボン(炭素)をオフセットする(offset・相殺する)」という意味の造語です。排出を避けられない温室効果ガスについて、ほかの活動で埋め合わせます。
カーボンニュートラルと異なるのは、温室効果ガスの排出量を間接的に相殺する点です。カーボンニュートラルは、排出量と除去率・吸収率を均衡させます。差し引きゼロにするイメージです。一方、カーボンオフセットは排出量に相当する活動を別に行い、排出量分の埋め合わせをします。たとえば活動を数値化し「クレジット」を市場で売買し、相殺します。
なぜカーボンニュートラルが必要なのか
温室効果ガスは、二酸化炭素やメタンなどの大気中に含まれるガスです。温室効果ガスが発生することで太陽の熱を地球に閉じ込め、地表の温度を上げてしまいます。
地表の熱が上がることで、地球規模の気象災害や気候変動を引き起こす恐れが高まります。このペースで気温上昇が続けば、人間の命にも関わる事態になりかねません。
カーボンニュートラルは、この状況を食い止めるために取り組まれているのです。
カーボンニュートラル実現を目指す「脱炭素ドミノ」の動き

日本政府は2020年(令和2年)にカーボンニュートラルを通じ、2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロ化を目指すことを宣言しました。
これを達成するためには温室効果ガスの排出を極力抑えるとともに、ガスを除去・吸収できる環境を整える必要があります。
環境省はカーボンニュートラル促進のためにロードマップを作成し、「脱炭素ドミノ」で重点的に対策することを決定しました。
環境省「脱炭素ポータル」
脱炭素へ移行するためのステップ
脱炭素ドミノを通じたカーボンニュートラル実現の取り組みについて、環境省は以下のステップを提案しています。
脱炭素先行地域を100か所以上創出する
基本施策として、2025年までに脱炭素に取り組む地域を100か所以上つくることが第一の目標です。脱炭素先行地域は、次の7項目を実行します。
- 再エネポテンシャルの最大活用による追加導入
- 住宅・建築物の省エネ導入及び蓄電池等として活用可能なEV/PHEV/FCV活用
- 再生可能エネルギー熱や未利用熱、カーボンニュートラル燃料の利用
- 地域特性に応じたデジタル技術も活用した脱炭素化の取組
- 資源循環の高度化(循環経済への移行)
- CO2排出実質ゼロの電気・熱・燃料の融通
- 地域の自然資源等を生かした吸収源対策等
引用元:環境省「脱炭素ポータル」
全国で重点対策を実施する
脱炭素先行地域を増やすとともに、全国各地で重点対策を実施します。地域の実情を踏まえた脱炭素活動に取り組むことで、カーボンニュートラルの実現スピードを加速させる狙いです。
日本全国に「脱炭素ドミノ」を伝播させる
2030年を目処に、脱炭素ドミノを全国に広げます。ある取り組みがビジネスや商業、自然環境や公共施設、国民の住生活へドミノのように伝播していくのが、この段階でのゴールです。
2050年を待たずに脱炭素を実現
脱炭素ドミノが広がれば、取り組み事例が蓄積され次の対策につながります。技術開発も進み、新たなビジネスチャンスの創出も期待できます。好循環をつくり、活力ある脱炭素地域を実現することで、カーボンニュートラルの目標達成を目指す方針です。
なお、脱炭素社会を目指す取り組みについては別記事でも詳しく解説しています。
renew「脱炭素社会の実現に向けた取り組みとは? 必要な対策について」
環境省が推奨する8つの重点対策
脱炭素先行地域以外のエリアについては次の8項目を重点対策とし、カーボンニュートラル化を図ります。
- 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電
- 地域共生・地域裨益型(ひえきがた)再エネの立地
- 公共施設や業務ビル等における徹底した省エネと再エネ電気調達と更新や改修時のZEB化誘導
- 住宅・建築物の省エネ性能等の向上
- ゼロカーボン・ドライブ(再エネ×EV/PHEV/FCV)
- 資源循環の高度化を通じた循環経済への移行
- コンパクト・プラス・ネットワーク等による脱炭素型まちづくり
- 食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立
引用元:環境省「脱炭素ポータル」
企業だけでなく、個人にも行動・努力を求めているのが特徴です。
日本におけるカーボンニュートラル実現の問題点

カーボンニュートラルを実現できれば、地球環境を守れます。しかし、実現にはいくつかの課題も残ります。
日本経済にも影響する?カーボンニュートラルの問題点
カーボンニュートラルの早期実現が理想ですが、世界各国が抱える実情は複雑です。特に排出基準の設定や、化石燃料から再生可能エネルギーへの移行には難しい問題が隠れています。経済活動にも影響を与えるテーマだけに、一筋縄ではいかないのでしょう。
排出基準・検証が難しい
温室効果ガスの排出基準は現在、生産行為を元に算出されています。ただ、これでは先進国の排出基準が少なめに、開発途上国の排出基準は多めに設定されてしまうのです。
これは、先進国企業が人件費削減のため発展途上国に工場を設置しており、発展途上国の排出量に算入されてしまうからです。そして、発展途上国は化石燃料への依存度が高めで、インフラ整備のためにどうしても排出量が増えてしまいます。
消費行為から排出量を算出できればいいのですが、データ計測や統計をまとめるのに限界があり、実現していません。
再生可能エネルギーの発電コストが高め
再生可能エネルギーとは、何度も再生して利用できるエネルギー資源のことです。太陽光や水力、風力などがあります。化石燃料のような、有限で枯渇する恐れがあるエネルギーに代わるものです。
世界的にも排出される温室効果ガスは、その多くがエネルギー起源の二酸化炭素で、再生可能エネルギーへの置き換えは急務です。
ただ、再生可能エネルギーは発電コストが高いという弱点があります。化石燃料よりも供給が不安定な点も、懸念材料です。とはいえ近年、再生可能エネルギーのコストを抑えて安定供給するための技術開発が進んでいます。
企業のカーボンニュートラル取り組み事例

カーボンニュートラルに向けた取り組みをしているかどうかは、企業イメージにも影響します。環境に配慮した事業体制があるかという視点で、投資先を決める人も増加傾向です。企業における脱炭素の動きについて見てみましょう。
電気の使い方を改善
すぐに取り組める対策として、既存エネルギーの使い方を工夫することが挙げられます。
省エネ対策
使っていない部屋や建物の照明を落とす、省エネに対応した機器を導入するなどです。従業員の働き方を見直すことで、省エネにつながることもあります。
「省エネ法」では、2030年までにエネルギーの消費効率を35%改善するという目標を掲げています。今後より一層、省エネ対策が求められるでしょう。
再生可能エネルギーの活用
太陽光発電パネルを工場内に設置するといった、再生可能エネルギーの活用も視野に入れる必要があります。化石燃料の利用率が依然として高めである日本においては、とりわけ意識して取り組むべきテーマです。
近年、消費者の目も厳しくなっています。企業の環境活動も経営体制をジャッジする一つの材料となっており、軽視できません。
CO2排出削減できる燃料の開発・導入
カーボンニュートラルで特に注目されているのが、二酸化炭素をできるだけ排出しない燃料です。
水素
燃焼しても二酸化炭素が排出されないエネルギーとして、活用されているものです。近年では自動車や家庭の燃料電池、発電所などで使われています。製造過程の違いによって、水素は3つの種類に分けられます。
- グリーン水素:再生可能エネルギーの電力で水を電気分解する(二酸化炭素は発生せず)
- ブルー水素:化石燃料を分解して製造する(二酸化炭素は地中に貯留)
- グレー水素:化石燃料を分解して製造する(二酸化炭素は大気に放出)
基本的に、水素をつくる過程で二酸化炭素が発生します。ただ、グリーン水素は二酸化炭素を排出せずに製造できるため、特に注目が集まっているのです。
再生可能エネルギーは、天候や時間帯により余剰が出てしまいます。それを水素の製造に活用すれば、エネルギー供給の安定化にもつながるのです。
バイオディーゼル燃料
原材料が植物由来であり、環境に優しい燃料です。使用済みの揚げ油を回収し、化学反応を発生させます。するとディーゼルエンジンで使える燃料となり、軽油の代替燃料に生まれ変わるのです。
バイオディーゼル燃料に含まれる二酸化炭素は、揚げ油の原材料である植物が光合成により大気から吸収したものです。よって、バイオディーゼル燃料を燃焼させても、二酸化炭素は増えないことになります。化石燃料の代わりにバイオディーゼル燃料を使えば、化石燃料を燃焼させたときの二酸化炭素を削減できたことになります。
カーボンニュートラルLNG(液化天然ガス)
液化天然ガスの採掘や燃焼には、多くの二酸化炭素を排出します。そこでカーボンニュートラルの考えを取り入れ、地球温暖化に歯止めをかける体制づくりが行われているのです。
具体的には、植林など環境保全活動を並行して実施し、液化天然ガスの排出量と吸収・除去量を均衡させます。この体制下で使われる液化天然ガスが「カーボンニュートラルLNG」です。日本の大手企業が相次いでカーボンニュートラルLNGの利用を宣言し、さらなる普及を目指しています。
製造工程や新素材の開発・導入
化石燃料に頼っていた従来の製造工程を見直し、研究と開発を重ねることでカーボンニュートラルに取り組む企業が増えています。特に建設業においては、鉄鋼やコンクリートの製造において二酸化炭素が多く発生します。その解決策として、新たな技術が生まれました。
ゼロカーボンスチール
鉄が空気中の酸素と結合してできた鉄鉱石が、鉄鋼の主な原材料です。鉄鉱石を鉄鋼に製鉄するためには、鉄鉱石から酸素を引きはがさねばなりません。その過程で石炭をはじめとする化石燃料が使用され、二酸化炭素を排出します。
しかし、化石燃料の代わりに水素を使うと二酸化炭素は発生せず、代わりに水が生成されます。この仕組みに注目して誕生したのが、ゼロカーボンスチールです。
ただ、この製造方法には課題もあります。大量の水素が必要になること、従来の製鉄方法では製造できないためさらなる技術開発が求められることです。
環境配慮型コンクリート
建設業界では、環境配慮型コンクリート(カーボンリサイクル・コンクリート)が誕生しました。二酸化炭素を再利用して製造するコンクリートです。
工場などで出た排気ガスには、二酸化炭素が多く含まれています。この二酸化炭素を回収してコンクリートの原材料に活用できないか、研究と開発が進められてきました。
その結果、二酸化炭素にカルシウムを反応させ、カーボンリサイクルの材料にする方法を発見しました。これによりコンクリート内部に二酸化炭素を含有・固定でき、カーボンニュートラルを考慮したコンクリートが生まれたのです。
まとめ
ここ数年、自然災害が多発しています。その要因の一つに地球温暖化の進行があり、世界全体で取り組むべき課題です。ビジネスシーンにおいても、環境保護の重要度が年々高まっています。
カーボンニュートラルは気候変動対策の一つとして、世の常識となっています。次世代のためにも、さらなる取り組みが求められるでしょう。
- カーボンニュートラル
Writer

もろふし ゆうこ
FP技能士2級、証券外務員会員一種
大手証券会社、銀行の個人営業職を経験した後、26歳で独立系ファイナンシャルプランナーとして独立。個人を対象にした相談業務やセミナー・講演会の講師業、各種メディア出演を通じてライフプランやマネープランに関する情報提供を行ってきた。現在はFPの知識を活かした執筆活動を中心に活動している。
このライターの記事を読む >おすすめの記事

お役立ち
2025.10.23
対談記事【ビジネスのヒント】|接骨院から建設業へ。驚きの経歴と経緯
経営に関する悩みや課題を抱える事業経営者の皆さまにとって、銀行の営業担当者は心強いサポーターの一人です。そこで、リニュー編集部では、事業経営者と西日本シティ銀行の営業担当者にスポットをあててインタビュー。サポートのきっかけや、事業の成功までの道のりなどをざっくばらんにお話しいただきます。

ニュース
2025.09.30
【今月のZero-Ten Park】株式会社ストリ|心と体に美しさと健やかさを
福岡を中心に世界5カ国15拠点を展開するシェアオフィス&コワーキングスペース「Zero-Ten Park」。そこに入居している、今注目したい企業をピックアップ。今回は「株式会社ストリ」をご紹介します。

お役立ち
2023.11.21
働き方改革に注力している企業ってどんなところ?|次世代ワークスタイル応援私募債「ミライへの路」
これから就職先を探している学生のみなさんにとって、どんな企業が自分にとって働きやすいのか、気になりますよね。そこで今回は、西日本シティ銀行が取り扱う次世代ワークスタイル応援私募債『ミライへの路*』を発行している企業のみなさんにご協力をいただき、その企業で実際に働いている若手の社員に直撃インタビュー。なぜ入社を決めたのか、実際に働いてみてどんな感じなのか、などをヒアリングしました。また、併せて、各企業の経営者にも、求める人材像や今後の展望などをお話しいただきました。取材に協力いただいた企業は、地元・福岡で働き方改革に注力している、優良企業ばかりです。ぜひ、就職希望先の候補の一つとして、働く先輩たちのリアルな声をご一読ください。

お役立ち
2025.07.18
【ミライへの路に挑む企業】地球を守り働く人の成長を支える環境調査会社|株式会社ENJEC
多様な生き方や働き方が広がりつつある現代。企業にはこれからますます、さまざまな人が働きやすい環境を整えることが求められます。社員の働きやすさを叶える企業の取り組みとは?この連載では、実際に働き方改革を積極的に取り組む企業で働く人や経営者にインタビュー。今回は、九州を中心に、水質、大気、土壌といった環境にまつわる調査・分析の事業を手がける、福岡市の株式会社ENJEC(エンジェック)に取材しました。

インタビュー
2025.06.11
質の高い人材紹介サービスで、企業も求職者も従業員も幸せに |株式会社GR8キャリア 小畑和貴さん
医療・福祉業界の人材紹介サービスをメインに事業展開する株式会社GR8(グレイト)キャリア。代表の小畑和貴さんは宮城県出身で福岡に移住し、住宅メーカーから人材紹介業界に転職したという異色のキャリアの持ち主です。創業から1年足らずでメンバーは20人ほどに増え、順調な滑り出しといえます。しかし、組織や利益の拡大は求めず、あくまでも「質の高いサービス提供」と「社員とその家族が笑顔で過ごせること」にこだわり続けたいという小畑さんに、その思いの根源や起業のストーリーを聞きました。

インタビュー
2025.06.02
番組・動画制作から拠点の運営まで、幅広い事業を展開|株式会社move on.e 岩谷直生さん
20歳から放送局の番組制作に関わり、個人事業主を経て、41歳で番組と動画制作を主軸にした株式会社move on.eを設立した岩谷直生さん。長年のディレクター経験を生かして、マスメディアの番組やイベントを手掛ける一方で、子どもに向けた全く新しい事業にも意欲的にチャレンジしています。

お役立ち
2025.11.25
【事業継続力強化計画認定制度】概要や認定のメリット、申請支援事業も紹介
近年、地震や台風などの自然災害、感染症の流行など、企業経営を取り巻くリスクが多様化しています。 こうした中で注目されているのが、災害や緊急事態に備えて事業を継続できる体制を整える「事業継続力強化計画(BCP)」です。 この計画の認定を受けることで、補助金申請時の加点や税制優遇など、さまざまなメリットがあります。 そこでこの記事では、事業継続力強化計画認定制度の概要や認定メリットに加えて、計画策定・申請を支援する取り組みについても解説します。

お役立ち
2025.11.25
【中小企業必見】最低賃金引上げに伴う負担軽減策とは?福岡県の支援策も紹介
令和7年度の最低賃金引上げにより、全国的に人件費の負担が増加しています。特に中小企業や小規模事業者にとっては、賃上げへの対応が経営上の大きな課題となっています。 こうした状況を受け、国や自治体では、最低賃金の引上げに伴う事業者の負担を軽減するため、各種支援策を打ち出しています。 この記事では、最低賃金引上げに対応するための国の主な支援策に加え、福岡県独自の支援制度について解説します。


